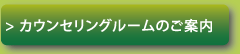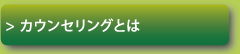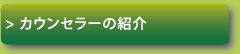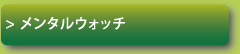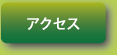★『境界線上の出来事』2015.10.17
ある出来事を境にして、自分を取り巻く環境が一変する。
そんな恐ろしいことが、昨今では、ごく頻繁に起きている。豪雨で河川の堤防が決壊して、あっという間に道路が冠水し、家屋が浸水し、間髪を容れずに家全体が傾く。余りの急展開で置き去りにされた現実と時間の感覚の中で、たった今まで普通に生活を営んでいた家が文字通り崩落する。そして、そのまま一瞬のうちに圧倒的に水量を増して激化した流れに家もろとも呑み込まれる。
凄まじい破壊力。天災とか事故では、その破壊力に因る過程が瞬時に凝縮されて完結する。そして、破壊後の経過が延々と続き、負の連鎖が新たな惨状を露呈させる。そうした中で時間を過ごしていく人たち。
あるいは、いつものように生活していて同じ動作を何度も繰り返している最中にふと感じた異変。たとえば、寝返りを打った直後に感じた痛烈な痛みとか階段の上り下りで不意に覚えた息苦しさなどが、実は、全く思いも寄らない進行性の癌の徴候であることが判明する。当然、自分自身と自分を取り巻く環境に亀裂が走る。しかし、瞬時には破壊し尽されない。破壊に到る過程が漸進的に、もしくは、ある時は急激に進行する。その壊れていく経過の無気味さ。ゾワゾワと心奥を這う空恐ろしい感じ。増量されていく、ありとあらゆる苦痛。そのような推移の中に居合わせざるを得ない人たち。
ある瞬間の出来事を境にして、それ以前とそれ以後の自分自身と自分の周囲の様相が悉く変質する。その境界線上での体験を経て、どのような生き様の内側を、どんなふうに生きるのか。
果たして、救いはあるのか。
答えが見つからない。仮に、ある人に何かしらの答えが見つかったとしても、それは、他の人には、答えにならないかもしれない。
けれども、過去と現在と未来を其々に画する境界線上の出来事が今も其処彼処で起きている。
★『窮すれば通ず!?』2015.9.9
「こんなこと、やってられない。どうして俺がやらないといけないんだ?」
「自分が本当にやりたいことに時間を使いたい。それ以外は、時間の無駄に思えて、やっていることに身が入らない」
F君(28歳)は、最高ランクの国立大学と大学院を卒業後、一流企業に就職した。その1年半後にアメリカの最高学府の一つの大学院に社費留学したが、その頃から朝起きられない・集中力が持続しないなどの不調が兆し始めた。
社費留学する場合、学生か研究生のいずれかの立場になるが、その選択は受け入れ先の状況に委ねられている。彼は院生として行くことになり、〈なんで俺が学生でいくのか〉と違和感を覚えた。社内で選抜された高揚感で充満していたやる気に水を掛けられたようだったが、それでもせっかく手に入れた機会を棒に振りたくはなかった。しかし、院生に課せられるノルマが苛酷なうえに言葉の壁も高く、F君は次第に〈勉強させられている〉という受身の感覚に陥っていった。基礎勉強でなく、自分が興味のあるテーマで自由に研究したかったが、その思惑が悉く外れたと感じた。失望感と容赦なく目先に積み上げられる期間限定の課題に圧倒される一方、〈こんなことをするために留学したんじゃない。もう少し応用的なことができると思っていたのに、ただの勉強のための勉強をしているだけじゃないか〉と徒労感を募らせて益々やる気を殺がれてしまった。
「今は、自分らしく生きられていない」
「興味のないことを無理矢理山のようにやらされて、イヤになった」
「落ち込んでみっともない自分を人に見せたくない」
F君は自分を〈臆病なライオン〉に準えた。〈百獣の王〉たる雄姿とは程遠い有様に胸を締め付けられ、ハイレベルな結果を出せない状態に自分を追い込んだ院生の立場を呪った。塞ぎ込む状態が続き、勉強がお座なりにもできなくなった。結局、F君は必要な単位を取得できず、改めて奮起する気にもなれず、一年で帰国した。留学前の職場に復帰したが、〈手負いのライオン〉のように見えない傷に悩まされ、会社に行くのが辛くなって休職した。
F君は、〈我が強い自分のままだと、この先碌なことがない〉と自覚し、自分の思い通りにならない状況でも自分が壊れてしまわないで済む在り方を手に入れることが先決だと思い至った。
「こうなったら、もう、開き直るしかない」
★『自分に繋がる』2015.7.8
「毎日毎日、朝早く起きてお弁当を夫と息子の分と二つ作って、朝ご飯を整えて、子どもを起こして、下の子を着替えさせて、ご飯を食べさせて、夫にコーヒーを淹れて、やっと夫と息子を送り出してすぐに下の子を保育園に連れて行って、帰って来たらすぐ隣に行って、お義母さんのおむつ交換をして、お義父さんのパンを焼いてる間にハムエッグを作って、お義母さんを迎えに来てくれた施設の人にお義母さんを託して、家に帰って、せわしなくコーヒーを飲んで、何かそのへんにあるものを口に入れたらすぐまた隣に行って、お義父さんに新聞を渡したり、食器を洗ったり、洗濯機を回して、また家に戻って食器を洗って、こっちでも洗濯機を回して、散らかっているものを片付けたり、ざっと掃除したりしてると、お昼になって、お義父さんの昼食を作りに行く」
R子さん(41歳)は、濁った目をして目の下に大きな隈を作り、疲労に生気を塗り固められているかのように、どんよりとくすんだ気配が全身から滲み出ている。
午後は買物に行ったり必要な雑用をこなすが、その間にも舅から携帯電話で呼び出されたり用事を頼まれる。そうこうしているうちに、息子が帰宅し、おやつを出したり連絡帳を見たり、夕食の仕込みをしてから下の子を迎えに行く。急いで帰って手早く夕食を作り、自分も一緒に食べている時に夫が帰宅し、四人が顔を揃えて片時の団欒をする。隣の夕食は仕出し屋から届けられるが、姑の就寝介助をするために、後片付けを夫に任せて隣に行く。姑の入れ歯を外して洗い、口内ケアをしてから着替えさせ、おむつを換える。
こうした毎日が一年近く続いている。舅姑には有料のシニア施設に入る経済的余裕はあるが、全くそのつもりがない。夫も「二人にはずっと家に居て貰いたい」と言う。それでも、最近になって漸く姑がデイサービスに行くのを舅と夫が了承し、月に一週間だけ舅も姑とショートステイを利用するようになった。
R子さんが「おむつ交換は大変」とこぼすだけで、夫は感情的になる。
「いったい、おむつ交換にどれくらいの時間がかかるんだ?」
「きれいに拭いたり、はみ出して汚れた服やシーツとかを洗ったりしていると、30分は軽く掛かるわね」
「一日のうち、たった三十分の仕事をして疲れるのか。お前がするのは、せいぜい一日に二、三回だろ」
R子さんは、夫がもう少し労いの言葉を言ってくれれば、もう少し元気が出るのに、と呟くように言う。
苛酷に繰り返される日々の中で、R子さんはかなり心身の限界に来ていたが、最近、ラインで中学時代の友人たちと繋がることができた。そこでやり取りしているうちに、R子さんは当時の明るかった自分の感覚を追体験し、現在の自分の本音を洩らして受け留められることで、疲労と辛さと絶望で捏ね固められて鈍磨していた自分感が清明になってきた。と同時に、可愛いものやきれいなものが好きだった自分自身が立ち現れて、たまたまラインでのやり取りを通して知ったボディジュエリーをする人になりたい、その技術を習得したい、という夢が生まれた。R子さんは、自分が自分に繋がったと強く感じた。自分が自分に無理を強いるのでなく、自分がしたいと望むことをする。そのための時間を日常生活の中に、たとえ短い間であっても、作るようにしようと決めたことで、固い泥土を突き上げて芽を出す花のように、力が湧いた。
「ただそれだけのことで、こんなに自分の中から鮮烈な力強さが湧き出てくるなんて思ってもみなかった。私が私に繋がっている…この感覚が本当に欲しかったものだったんです」
★『噂』2015.6.10
「異動してきてすぐ、ここに来て良かった、って本当に心から思ったし、職場に居る時の気持ちが前に居た時とは違ってすごく楽になったって感じた」
F子さん(32歳)は、クスリと笑いながら軽く肩を竦めて言った。本当に良かったね、と言おうとした言葉が急変したF子さんの雰囲気に掻き消された。そのまま成行きを見守っていると程なくしてF子さんが独り言のように呟いた。
「新しい所に来て早く仕事を覚えようと一生懸命にやっているのに、どうしてまた前の職場に居た時からの噂が駆け巡るんだろう?どうして違う職場に来ても、噂がいつまでも続くんだろうか?普段何に気をつけてやれば、こんなに傷つけられずに済むのか…また毎日が怖くなった」
「なにもわざわざ噂で流さなくても、私に直接言ってくれればいいことなのに、言われて分かるのでなく、自分で気づいて自分から改めるようにしないといけない。本人のことを思って周りが気を遣っているのが分かっていないのが一番困るんだ、って前の上司がこちらの課長に言ってるらしい。お二人は同期入社でプライベートでも親しいらしい」
F子さんは、自分に関わる噂をスタッフ同士が話しているのを小耳に挟んだり、自分が側に行くとそれまで話していた人たちがたちまち話を切り上げてしまうことから、噂が広がっていることを確信する。
F子さんに拠ると、その噂とは、F子さんが係長試験に本当は受かっているのに落ちたのは、仕事ができるだけが係長になる適格条件ではなく、皆と仲良くやれることも同じ位に大切だということを本人が認識するための猶予を設けるためだった。
「どうも私が変わらないといけない。仕事は一人では出来ないのだから、もっと皆に合わせて会話しないといけない。私の方から皆に歩み寄れるように、噂を流して、そうせざるを得ない状況を作ってやっているんだ。どうしてそれが分からないのか。これだけやっても、まだ分からないのか。どうもそういうことらしいんです」
「本当に私のことを思ってやって下さっているのなら、どうして私を苦しめるようなやり方でなく、私に直に言って下さらないのか…」
F子さんが噂に苦しんでいることは確かである。けれども、実際のところ、噂の実体が掴めない。もしかすれば、それは、F子さんの根強い願望とその挫折、さらには挫折に対する自分を傷つけないように無意識に気遣われた理由づけなどが渾然一体となった結果なのかもしれない。
係長になりたいという願望よりも皆の関心の的でありたい願望。皆に優しく受け容れられて相互的な交流を楽しみたいのに、うまく皆の会話の輪に入れない疎外感や取り残され感が募っていく一方、職場は仕事をする場所であってお喋りをしたり、自分の都合で好き勝手に有給休暇を取るべきではない、などといった批判を盾にして、「自分は少しもおかしいことを言っていない、むしろ、当たり前のことしか言っていないのに、どうして皆は仕事中にお喋りしたり忙しい時に休みを取る人たちの肩を持つのか。正直者が馬鹿を見るような環境はおかしい」と頑な見解を膨らませる。誰にも受けとめて貰えないけれども内面に留めておくこともできない不本意な思いが噂になって流出して自分を傷つける。
今、F子さんは、皆がする噂でなく《今、ここ》で直接接する人たちの話により注意を向けようとしている。
★『〈私〉対〈私〉群』2015.5.9
〈私〉の中に何人もの〈私〉が居る。
その各々が互いに互いを制し合って、自分こそが正真正銘の〈私〉だ、と主張する。けれども、そのどれもがあっという間に首位から脱落して別の自分に取って代られる。どの自分にも自らの存亡を賭けて必死になるだけの強い意志も大義も覚悟も手段もない。ただ、直感とか願望とか色合いの違う感情とかに搦め捕られた輩が見境もなく勝手に声を張り上げるので、全く収拾がつかなくなる。もちろん、理性や先見の明を具えた者も保身や世知に長けた人もいるが、その者たちの何れかの傘下に入って大人しく引き下がっていられない連中が再三再四騒ぎを起こす。
たとえば、A子さん(37歳)は、食べては吐き、吐いては食べることを繰り返し、時にリストカットを加える。長さも太さもまちまちの、赤みを帯びていたり茶色だったり黒味がかったミミズが何匹も左腕の内側に横並びになった状態で動かない。それらを見て、自分の確かな行跡を目の当りにして満たされることがある一方で人目から隠さずにはいられない負い目を感じて嫌悪感に囚われる。同時に、傷ついた自分を抱きしめたい愛おしさで一杯になる。が、いきなり悲しみなのか悔しさなのか憤りなのかよく分からない感情に襲われて涙が溢れていたり声を上げて泣いていたりする。
「やっていることと心の中で感じていることと考えていることが全部ばらばら。どれが本当の自分か分からない」
A子さんは、まとまりを欠いてばらばらになった自分を持て余して《本当の自分》を探している。
「本当の自分って、一人なの?」
「えっ?」
「自分の中は、全く矛盾する考えやちぐはぐな気持ちや不可解な経験や断片的な記憶などでごちゃごちゃしていて、すごく取り散らかっていても、それらは全て自分のものじゃないの?どれもみんな本当の自分じゃない?」
「本当の自分は、一人じゃなくてもいいのか。ばらばらでも、どれもみな私だとしたら、身体は一つしかないから、実際にはどうなっちゃうのか…」
確かに、ばらばらな自分の一個一個を一つの身体で生き分けるのは、不可能である。まとめ役の自分が要る。その自分は、ばらばらな自分群から《本当の自分》を探すのでなく、それらはどれも《本当の自分》だと認めて各自の声を聴き取り、そのうえで自分の内面と現実状況をしっかり見据えて判断を下す。
まとめ役の自分が居るか居ないか。居る場合、その自分は、どのように機能するのか。
まとめ役の自分は、言わば、自分群の代表である。A子さんは気づいていなかったが、彼女が「やっていることと心の中で感じていることと考えていることが全部ばらばら」と語った時、その語りの主体はA子さんのまとめ役の自分だった。何故なら、ばらばらな自分群が好き勝手にのさばっている状態を冷静に観察して支援を求めるなど対応策を講じようとしている。実に、信頼に足るまとめ役である。この自分が行方不明になってしまわない限り、多少のことがあっても、A子さんは彼女自身の道を進んで行ける。
〈私〉の中に何人もの〈私〉が居ても、〈私〉は〈私〉。
★『足踏みする人』2015.4.11
「このままでいるのは嫌だ。だからといって、この状態がすごく嫌っていうことではない。家の人が心配しているのは分かるけど、だからといって、非難じみたことをとやかく言ってきたりはしない。内心、しょうがない奴だ、くらいは思ってるだろうけど…。ただ、自分がずっと止まったままでいたくない。何もしてないのは嫌だから動いていたい」
S君(22歳)は大学3年の5月末のある日、実験中に眩暈がしてその場にしゃがみ込んでしまった。友人に付添われて保健室に行き、暫く休んで一人で下宿に帰った。実際には普通に歩けているが、自分ではふらつく感じが強くして、身体がふらふらする感覚に呑まれてしまう。それ以後、ゼミの発表に当たっていたのをすっぽかし、ずるずると大学を休んでいる。7月に入り、ゼミの教授から連絡を受けた両親が様子を見に来ていくつかの診療科を受診させたが、特に異状は見つからなかった。夏休み直前だったので、S君は両親と一緒に帰省した。そのまま夏休みが終わっても大学に戻らず休学し、就職活動や卒論などは棚上げにして気が向いた時にふらりと日帰りか2,3泊で名所旧跡に出かけたり、家で本を読んだりネットサーフィンをしたりしていた。同級生たちが卒業しても、S君は退学するか復学するかを決め切れない。自分の問題は自分で何とかするから触れないでほしいと頑になっているS君に対して、親は関わり方が分からないまま、取り敢えず休学期間の延長手続きをしていた。
「今自分がどこに居るのか、分からない。この先自分がどうすればいいのか。どうしたいのか。何をするべきなのか。よく分からなくなってる。でも、とりあえず、ここからどこかに動いて行きたい。目標…目指すものがあればいいけど、今は何もない。早くやりたいことをみつけたい。ちゃんと続くやつ」
「就活して、大学を卒業して、9時5時の仕事に就くのは嫌だ。流行とか潮流に流されない、自分の拘りを持っていたい。周りと違うように生きたいとは特に思ってないけど、周りと同じようにしようとしても、何かずれてる。自分ではどうしようもないこと。拘りっていうのは、自分にしっくりくるかどうかってことかな。やってることが自分の身になってるという実感っていうか…」
「自分が思ったことを行動に移したら、怒られたりびっくりされたり呆れられたりする。グズグズしたりビクビクしないで動こうという決断ができない。優柔不断。決めたことに自信がないのかな。自分を信用できない。失敗よりも後悔したくない。決めたら迷わない」
S君は、自分で4月から復学することに決めた。同級生たちから半年遅れて秋に卒業したい旨を、やっとの思いで指導教授に電話して伝えた。卒業に必要な単位は満たしていたので、卒業論文に代わるレポートを提出することで何とかハードルを越えられる見通しになった。
「すっきりした。度の合った眼鏡をかけて見た時みたいに、視界がはっきりした。なんでこんなに簡単なことが出来なかったんだろう。人が変わったみたい。元は変わらないけど、洋服を着替えた感じ。パジャマから外に行く服。パジャマで外に出たら変な奴。自分も楽なようで楽じゃない」
「教授に電話しただけなのに、自分に欠けたものが戻ってくる感じがした。迷子になった犬が戻ってきたみたいな…。戻ってきたから大丈夫。前と同じだけど違っている。これからかな。ビビッてないでやってみようという気持ち。やってみようと思えば、やってみればいい。やるって決める。後で後悔することがあっても、その時の自分は一生懸命考えてそう決めた、その自分を引き受ける。そして、小さな達成感を見つけていけば、心にしっくりくる体験もあるかもしれない。めげない。勝ちはしないけど負けない。何があっても自分は前に進んで行く」
「道は沢山あるけど、どこに進めばいいのか分からない。とりあえずそっちに行こうかなと思った。いずれ特別やりたいっていうのが見つかればいい。一番しっくりくるものを探し続けて結局見つからない。青い鳥を見つけても、もっと青い鳥がいる筈だ。どこに行くかは分からないないけど、とりあえず出発する。決めないといけない状況に置かれるように自分を仕向けた。ある程度の目標があった方が進み易くしてくれる。漠然とした、ここらへん。それが最高の道でなくても妥当な道。途中で新しい分かれ道に出る」
「自分って空気みたい。捕え所が無い。掴めないし見えないけど、風が吹いたら、在るのが分かる」
「亀のようになりたい。何も考えてなさそうなところがあるけど、地道に歩いて行けば兎にも勝てる。危ないなと思えば首を引っ込められる。向かうところ敵なし」
「弱い自分に対抗する力を、少しはつけられたのかな。目が泳いで、弱い自分を見れなかったから、倒れたんだろうなって気がする」
★『状況を生きる姿勢』2015.3.19
《今、ここ》での状況を生きる。その連続が、私たちの人生を紡いでいく。
〈私〉がどんな時でも必ず居合わせている《今、ここ》での状況は、背後に広大で深遠かつ複合的でダイナミックな連鎖の網の目を潜ませていて、絶えず無気味な軋み音とか得体の知れない複雑怪奇な断続音を反響させている。けれども、それらは〈私〉の耳には届かない。だからこそ、〈私〉は一見何事もないかのように目先の、あるいは感知できる周囲の事柄だけにかまけて過ごしていられる。「大丈夫!」という能天気な楽天性と「何とかなる」という根拠のない自信が〈私〉の日常性を支えている。ただ、中には、神経が非常に鋭く研ぎ澄まされているか感受性が極めて繊細で細やかな人がいて、まだ発現していない隠れた事態が醸しだすただならぬ気配を鋭敏に嗅ぎ取って不安を強めたり、独自の臨場感を鮮明にしたりなどして一緒にいる他の人たちと共有すべき体験から外れていく。
《先見の明》とか《転ばぬ先の杖》など、先々に起こり得る出来事や有様を予測して前以て色々用意したり何某かの手段を講じたりしておくことは大切である。しかし、余りにも「もし…になったら、どうしよう」と自分の身に降り掛かるかもしれないことを懸念し始めれば、《今、ここ》で生きている状況からどんどん隔てられていきかねない。そうすれば、《今、ここ》での生き方そのものが疎かになる結果、先々に起こるかもしれないと予測した良からぬことを文字通り呼び寄せてしまうことになり、「やっぱり、思った通り」と次々に不安を募らせていくループに嵌りこんでしまう。
「これからどうなるか分からない」
「何かあったら怖いから、何もやる気がしない」
《今、ここ》での状況を、どのように生きるか。なんとなく自分に自信が持てなくて絶えず心許ない感覚に囚われて及び腰でいるのか、《案ずるよりも産むが易い》《やってみなければ分からない》と前向きに挑戦しようとするのか。たとえ、気持ちは前向きであっても、自分が居合わせている状況が絶望的である場合もある。たとえば、今はまだ自覚症状がなくても、余命が既にカウントダウンの段階になっている時とか自分の力だけではどうにもならない様々な事情が絡まり合って抜き差しならない状態に陥っている時などであっても、〈私〉は《今、ここ》での状況から逃れられない。その時その場に臨む〈私〉の姿勢が、〈私〉の生きている感覚に変化を付けるように思われる。
〈私〉が《今、ここ》で内面で覚える感じの連鎖が〈私〉に人生を集約して掴ませてくれるのか。
★『ここは、監獄?』2015.2.5
閉塞感に潰される!目に見える鎖や壁や施錠された扉で自由を奪われているわけではない。けれども、見えない縛りで雁字搦めになっていて自分でどうすることもできない。
K子さん(29歳)は、4年前にカナダ人の夫(34歳)と旅先のグアムで知り合った。彼はグローバル企業の日本支社に勤務していたが、休暇で来ていた。日本に帰国後、1年ほどデートを重ねて結婚した。その2年後、彼がアメリカのマサチューセッツ州にある戦略企画部門に転勤になった。当初、K子さんは、アメリカに行ったら、先ず語学学校に行って言葉をある程度マスターしたら日本での社会福祉士としてのキャリアに更に磨きをかけるために大学院に行き、高い専門性で社会的地位が確立されているソーシャルワーカーとしてバリバリ働こうと期待を膨らませて、大学卒業以来ずっと勤務してきた保健福祉事務所を躊躇うことなく退職した。
けれども、アメリカに引っ越して日常生活が落ち着いてきた頃からこれまで経験したことがないような体調不良に陥った。吐き気と下痢が止まらない。きっとストレスが原因だろうと直感した。
〈こんな生活は厭だ。むかつく。なんとかならないか…一刻も早くこの不快な状況を無くしてしまいたい〉
まるで症状が現在の自分の心境を訴えているかのように感じた。全くこんな生活は耐え難い。たとえば、夫が出勤した後、一通りの家事を終えて買物に行こうと思っても足がない。車は夫が通勤に使っているし、バスや電車などの公共の交通手段もない。車を確保するために、夫に送迎を申し出るが、仕事で出かけることがあると斥けられてしまう。もう1台車を買うだけの理由が夫には通用しない。歩道も自転車用道路もないところで自転車に乗るのは気乗りがしない。語学学校に通うなど夢の夢である。せめて散歩でもしようとアパートの敷地内を歩き、偶に住民に話しかけられることがあっても、日本語が堪能な夫との会話で英語に不慣れなために相手の言っていることがよく分からない。会話はすぐ気まずく途切れてしまって、次に会った時はにこやかにハイと言って行き過ぎるかさりげなく視線を逸らし合ったりして孤立感が募る。それでもなんとか気持ちを持ち直して手が込んだ料理を作ったり、ネットサーフィンをしたり、英語の勉強をしたりするが、ずっと一人で家に居て夫以外の人と話す機会が殆どない状況が監獄生活を強いられているように感じられてきた。
やりたいことが思うようにできない。人との交流もままならない。自分の行動が悉く制限された状況。夫が不当な拘束を強いる看守のようにさえ感じられて、心の中がざわざわしたり苛立ったりしてくる。いっそ離婚して日本に帰ってしまいたい気持ちが浮き上がる。一方で、困難な状況に容易く尻尾を巻いてしまうのも悔しい。この窮地をどう展開させるか。自分が試されているような気もする。
現状を本当に監獄にしてしまうのか、閉塞感を縫って時折届く微かな光の帯を広げようとするのか。
〈この監獄生活を強いているのは、結局、自分自身ってこと?〉
★『年頭の所感』2015.1.7
年が明けた。
永々と繰り返される昨日から今日への移行であるにも拘らず、昨日に大晦日、今日に元旦とか三箇日という個別の名称が与えられていることで、単なる時間の流れだけではない特別の意味を帯びた推移が今後営々として続く無数の明日を引き連れて来た。
日常化した凡庸な経過の中で、この〈時〉ばかりは、惰性に由らない、なにかしら改まった気持ちになる。
〈今年こそは…〉
〈本当に、今年は…〉
〈昨日今日とは違う明日を生きたい〉
心の奥底で燻っていた想いが家中のカレンダーを取り替える行為によって揺さぶられる。その振動が加齢を数える意識に伝播して、過ぎ去った日々とこれから持ち得る限りある日々の間に一線を画させる。
〈このままボヤボヤしていれば、不本意な状態に取り残されて寿命が尽きてしまう〉
けれども、それはそれで仕方がない、已むを得ない、という振れ幅の一様でない振動も混ざり込む。
昨日から今日への流れ自体は一本調子で決して連続性を乱すことがなくても、その間に思いも寄らない亀裂が走り、その裂け目に堕ちたが最後、自らの意志と力と行動ではどうすることもできない状況に閉じ込められることがある。これまでの〈日常〉が悉くその連続性を断たれて一変した身辺の新たな〈日常〉で、これまでとは比較にならないほど過酷さを増した新たな不本意に圧倒される。それでも、生き方を司る意識に振動が断続的に伝播してくる。それを知覚して増幅させる。
〈まだ遅くはない〉
〈完全に自由が奪われたわけではない〉
〈夢を叶える〉
〈自分が心底望んだものを手に入れる生き方をしようとするくらいはできる〉
個別の名前を浮かび上がらせられない無数の存在の一つであるとしても、無名性に流されない特別の意味を帯びた存在であることを自意識に刻む。
自己満足?
大いに、結構。
結局、自分で感じる自分自身が己れの幸福を握っているのだから。
★『死』2014.12.8
死。
決して免れられない。
(自分だけは特別だ)
(自分がいずれ跡形もなく消滅してしまうなんて考えられない)
「あの人、そんなふうに言ってることがあったね。それなのに、結局、呆気なく逝っちゃったねえ」
死は、誰にでも、遅かれ早かれ、必ず平等に訪れる。
突然、事故に遭ったり、天災に見舞われたり、事件に巻き込まれたりして、全く予期しない瞬間にいきなり命を奪われることも、成行きで受けた検診とかふっと過ぎった些細な違和感から深刻な病気の兆候が発見されて、そのまま済し崩しに症状が進行して余命が尽きていくことも、充分に老齢を重ねてすーっといつも通りの暮らしの中で眠りに引き込まれたままになることもある。
自分はどんな死に方をするのだろうか。
恐ろしい問いを発して、微かな死臭を自分に嗅ぎ取りかけて、直ちにその先に続く過程が遮断される。
今でなくても、いずれ気がつけば、その過程の真っ只中に居合わせているのだろうから、まだ暫くは自動式遮断機のままにしていればいいか。
先日、自身も癌を診断されている友人が夫を癌で亡くした。彼女の方が夫よりも先に癌が発覚して夫と二人三脚で治療に取り組んでいたが、ある時、彼女の受診に同行していた夫もCT検査を受けることになった。彼には全く自覚症状はなく彼女を気遣いながら小旅行に頻繁に出かけるのを楽しんでいた。ところが、思いがけない検査結果に続いて治療が開始されたが、癌の進行が悪夢のように速く、その7ヶ月後には死が彼を攫って行ってしまった。
今はその気配が消されていて、当たり前のように繰り返されている日常がある瞬間を境にして一変する。
自分とは縁もゆかりもない他者の死。知り合いの死。身近な人の死。自分自身の死。
いつ、どこにいても、私たちは〈臨死〉の状態を秘めている。ある時、どこにでも自動設置され得る回転扉がぐるりと回れば、生と死が入れ替わる。
死という現実。
けれども、それは、本当に存在の消滅なのだろうか。
「正明は、私よりも少し早く、彼が生前大好きだった皆様に見送られて逝きました。けれども、私が生きている限り、彼は私の中で、もしかすればこれまで以上に頼り甲斐のある人としていつも側にいてくれるような気がします」
★『行動の種』2014.11.12
「何もしたくない」
「やる気が起きない」
「どうして他の人たちは、あんなに次から次に色んなことができるのか不思議でしようがない」
そんなふうに言うKさん(23歳)だが、彼女は起床して洗顔して着衣し外出するなど、既にいくつもの行動を重ねている。
「ここからそこへ動くのも生きた物語が生まれなければならない」
ある演出家の言葉である。何もない舞台空間で役者が一人左から右に普通に歩く。ただそれだけで前後の展開が何もなく終わっても、確かに、そこには、物語がある。その場の状況と人とその人の動きがあり、それらの現実と見ている者の想像力が合わさって何かしらの想いが生み出されている。仮に、‘つまらない’と辟易するだけであっても、反応が生じている。それが物語の種になり、それによって’それ’を感じた人の心を動かしていく。心が動けば、自ずと行動が引き出されてくる。Kさんの場合、何の変哲もない日常の生活空間に居るのは彼女だけで誰も見ている人がいないかもしれない。けれども、Kさん自身がそこでそうしている自分を意識することはできる。たとえば、
〈私は、今、何もしていない〉
すると、その時に何らかの身体の感覚を感じたり、退屈感を覚えたり、何か断片的な想念が浮かぶのに気づく。ただそれだけのことであっても、そこには、Kさんを巡る生きた物語が生まれている。もし、そこでKさんが自分に起きていることを意識化すれば、それが次の反応を引き起こし、その連鎖が行動を胚胎させる。
感じれば、心が動く。
やる気が失せてどんよりした自分に意識の焦点を当て、想像力を殊更に掻き立ててみる。もしかすれば、そこに、行動の種が埋もれているかもしれない。
★『この人、おかしいの』2014.10.8
週一回の俳句サークルの集まりで七、八人のメンバーがいつものように各自の句を披露してちょっとした注釈を加えたり、他の人たちがその句について各人各様の解釈や感想をあれやこれや言い合ったりしていた。そうしているうちに、なんとなくその句に対する口々の評価がある方向に収束していくのを頃合にして、次の人が新たに自分の句を詠む。そうしたことを順々に繰り返していた。
そうした流れの中でAが収束していく方向とは異なる見解を述べた。その直後にAの隣に座っていたBがAに背を向けて上体を斜向かいのCの方に乗り出させて言い放った。
「この人、おかしいの」
その鋭い語調はその場で一瞬の閃光を発したが、話はそのまま本筋に沿って流れていったので、Bの言葉は跡形もなくなった。けれども、その言葉と語調がCの耳底で残響し、異質感を増幅させた。
Cにとって、その異質感とは、何だったのだろうか。もちろん、C自身が公然と自分を否定され尊厳を蔑ろにされたわけではない。言われた当人のAを見ても、その様子に特段の変化は見受けられない。ただ、Aの内面を透かし見ることはできないので、もしかすれば、Aの心の中では誰もが自己愛を傷つけられた時に往々にして覚えがちな激しい憤りと自己の核心を抉られるような痛みが蜷局を巻いていたのかもしれない。そうした一般的にありがちな反応とCの目に映るAの冷静な様子とのギャップにCが違和感を覚えたのでもない。むしろ、Cが感じたのは、自分の方に上体を向けて同意を求めるように言ったBに対する違和感である。同時に、突っ込み方次第で深い議論ができる芽を摘まれたような、肩透かしを食らったような失望感だった。BがAの発言の内容に反応するのでなく、発言者の人格否定を行ったことに対する驚きが強く、Bに対する異質感が募った。自分とは異なる感性や視点の展開や解釈の多様な可能性などを巡って話を交わしたり議論をしたりすることで互いに研鑽し合うのが愉しいのに、その可能性に異物が混ざっているのを見つけて、恰も会自体が貶められたかのようで、多分に興醒めしてしまった。
「あなたの方がおかしいわよ」
ブーメランを投げるかのように、Bに自らの言葉を受け取らせたい衝動に鈍く駆られたが、それはCを突き上げるよりも前に拡散した。それにしても、Cは何故これほどまでに強い反応をBのAに関する言葉に対して起こしたのだろうか。
「私って、おかしくない?」
こうした不安や疑念がCにも、そして私たちにも、こころの洞のどこかに巣食っているからなのかもしれない。
★『欲求は、いつも単純明快?』2014.9.10
「自分に話が振られるのがいや。大したことは言えないし、話し方が変じゃないか気になる」
「一対一ならまだいいけど、複数になったら、話に集中できなくなって、皆が何を話しているのか分からなくなる。半分上の空なのに、顔だけはにこやかにしているけど、皆がいっせいに笑う時にひとりだけずれていたりする」
「人と話すのは苦手。相手が何を言ってくるか分からないから、すごく緊張する。他の人たちが楽しそうに長時間お喋りしていられるのが不思議」「私が話し始めたら、その場の雰囲気がなんとなく盛り下がる気がする」
「私がつまらない話でも聞いてあげている間はずっと話しているのに、私がちょっと意見を言ったり自分のことを話そうとすると、聞き流してすぐまた自分に話を戻したり、話を打ち切ってしまったりする。これって、対等の友達関係って言える?」
「俺は相手の方が今の職場では先輩だと思うから会えば挨拶するのに、向こうは擦れ違っても知らん顔している。俺から言わせれば、傲慢。いったい何様のつもりなんだ!」
人間関係が煩わしい。そんなふうに思うことがよくあっても、私たちの心のどこかには必ず人との繋がりを求める気持ちが埋もれている。ただ、自分にとって好ましい繋がりばかりを求める気持ちが強すぎて却って臆病になったり冷淡になったり憤激したり苦悩したりする。
本来、欲求はいつも単純明快である。私たちは、寒い時には暖かいものを求め、暑い時には冷たいものが欲しくなる。それは、生理的な事柄だけに限らない。心理的にも悲喜交々の場面で慰めとか共感とか思い遣りなど心に快く響くものを一心に求めている。けれども、心が望み通りに満たされることは殆どない。むしろ、満たされないことの方が圧倒的に多い。それでも、私たちはその満たされない辛さに耐えながら何某かの満足を見つけて過ごしていくが、実はその満たされない辛さが私たちに様々な反応を起こさせていて、自分でも全く気づかないうちに私たちの生き方を複雑怪奇に仕立て上げていたりする。
私たちは、もし自分の方に何かが向かってくれば、咄嗟に避ける動作をしているし、足元が危ういと反射的に何かに?まろうとする。心も平穏を壊されるような事態に出くわすと殆ど自動的に動揺や衝撃を回避する手立てを講じて、〈私〉を苦痛から救おうとする。ただ、その方策が有効に機能する場合とそうではなくて新たな生き辛さを持ち込んでいることもあるが、私たちはそうした事態を当たり前のように無自覚に引き受けて苦しさだけを感じ取る。
自分の本当の欲求を棚上げして、周辺の事柄に意識を向けて弱気になったり憤ったりしていることがよくある。上述したいくつかの言葉の背後?人に対する弱気とか憤りの根元?には、心が乱されるのを怖れて神経を研ぎ澄ませている傷つきやすい〈私〉がいる。そして、〈私はここにいる!〉と自分自身の存在価値を〈私〉に感じさせて心を満たしてくれる糧を求めて声にはならない大音量で叫んでいる。けれども、どこからも心にしっくりと響いてくる応答を得られない。そんなふうにして、〈ない〉ことで抉られていく心が少しずつ穴ぼこだらけになっていくにつれて空虚感や悲しみや苛立ちや猜疑心などが穴の中に積もっていく。穴が深ければ深いほど、大きくなればなるほど、〈私〉は不安定になり、自分で自分を支えていられなくなる。自分を保たせてくれる繋がりをひたすら求めて呻吟するうちに、いつの間にか自分の中にある筈の穴に自分が落ちていて、いつ来るとも分からない救援を待ち続けるだけになりかねない。
穴から這い出ること。それ以前に、なんとか穴に落ち込まないでいる手立てを自らの力で工夫すること。
人との繋がりがもたらす過不足のある、時として抜き差しならないほど致命的に欠けている満足度でも持ち堪えていくには、どうすればいいのだろうか。答えを得ることはなかなかできないけれども、心のどこかで〈自分で自分を持て余してしまったらまずいよなあ〉というか細い声がしていたりもする。
★『二つに一つ』2014.8.5
「なんだかんだ言っても、結局、するかしないか、二つに一つなんじゃないの?」
一回限りの人生。どのように生きるか。それは、〈今、ここ〉で、それをするのか、しないのか、その大なり小なりの選択の連鎖である。それをしない代わりに、あることをする。それをしないことが、その瞬間(とき)は大して深く考えていなくても、その後の人生を方向づける分れ目になっていることがある。その時々にした行為のひとつ一つが人生を織り上げる緯糸(よこいと)になり、寿命に向かって一直線に通っている経糸(たていと)の間を縫って、その人独自の紋様を織り出していく。
「僕は今、何もしないことをして生きている。そのことで今、特段困っているようには自分で感じないけど、何もしてないのは嫌。止まっていたくないから動いていたい」
卒業論文だけを残して留年を続けている茂君(24歳)は、家族と普通に会話をして何事もないかのように毎日を過ごし、少し前までは気が向くと近隣の散歩やプラネタリウムやスカイツリーなどに出かけて夕食の時間には帰宅していた。けれども、最近は余り出かけない。かといって、自室に閉じ籠っているわけでなく、休暇で帰省したかのようにまったり過ごしている。そうした様子が腑に落ちない両親が〈何を考えてるの?〉、〈せっかくの学生時代がもったいないよ〉、〈とにかく大学は卒業しろ〉などと言うと、話を遮断して固まってしまう。
「これから先のことが見えない。目指す目標があればいいけど、今は何もない。自分が知らないとこに行きたい」
茂君には、「自分が知らないとこに行く」ことがとりあえず「目指す目標」にはならないようである。
当面は「動いていたい」欲求に身を委ね、前以て行先など定めずに、風の吹くまま、気の向くまま、成行き任せに動くのか、動かないのか。もしかすれば、その動いている過程で今後に繋がる〈目標〉に出くわさないとも限らない。
茂君は比較的近場の、自分が知らない所には行くことができるが、遠い所へ旅するのは怖いのか。あるいは、自分が知らない、慣れないことをするのが苦手なのか。
一人で未知の空間/事態を動き回るには、行為の主体としての〈私〉がそこそこしっかりしている必要がある。どのような事態に居合わせても、〈今、ここ〉でどれだけ自分として有効な動き方ができるのか。
留年二年目になる茂君には、いくつもの選択肢がある。先ずは卒業を目指すのか、目指さないのか。このまま留年を続けるのか、続けないのか。退学するのか、しないのか。他にも、〈今、ここ〉で何をするか、日常生活の場でも細かい選択が目白押しである。
自分がすることによってのみ、自分自身の全存在が集約された行動によってのみ、唯一無二の人生が織り上げられていく。
★『万事、結果次第?』2014.7.9
「そりゃあ結果は大事だよ。だけど、それだけがすべてではないだろぉ。仮に、その時はこれといった結果を出せなくても、そこで色々考えたり工夫したり試行錯誤して得た経験や知識は必ず次に何かを産み出す肥やしになると思うよ」
「よく、失敗は成功の母って言うものね。結果はパッとしなくても、そこで挫けないで、とことんやり続けていくかどうか…結果は刻々と更新され続けると信じてさ…」
「自分は本当によく頑張ったって自分自身に偽りなく心底思えれば、外からの評価は大したことなくても、それはそれでいいんじゃない?結果よりもプロセスでしょ、その人にとっての主観的体験ってことの意味が大きいっていうか…」
「そこが一流と二流・三流を分けるポイントなんだよ。一流は、自分の限界を超えるほど頑張っても結果を出せなければ意味がないと感じて、とことん公共的価値の高い結果を求めて四苦八苦を続けるけど、二流・三流は適当なところで打ち切って、我ながらよくやったよ、そう思えただけでも意味があると満足するんだ」
「一流とか二流っていうより、結果の公共性とか社会的価値のレベルってことかなあ。誰が何をやっても、それなりに何らかの結果はあるわけだから、結果が個人のレベルに留まるのか、より多くの人と有利に分かち合われるのか…自分だけの満足とか失望に終始するのか、他の人にも是か非かの影響を及ぼすものなのか。やっぱり、社会的な場面でなんらかの結果を出していかない限り、顕在化した結果はないわけだし、自分の存在感が稀薄になってしまうよな」
「大した結果でも取るに足りない結果でもとんでもない結果でも、とにかく、一つの結果が次の結果のきっかけになっていくし、自分とは無関係な結果に巻き込まれてしまうこともあるし、ま、ありとあらゆる結果の複合的な連鎖でもって、人生が出来上がっていくってことか…」
「“終わり良ければ、すべて良し”って人生の最期に思いたいな」
やはり、とどのつまり、万事、結果次第?
★『できない!』2014.6.7
できない!
その衝撃に打ちのめされる。一瞬、身体全体がかっと熱くなり、動悸が音を立てて速くなる。同時に、手が震える。その震動が全身に伝播して姿勢を保っていられない。自己の核心が穿たれでもしたかのように、自分が総崩れになってしまう恐怖に煽られる。
「大丈夫。そういうことってあるよ」
「落ち着いて何回かやってみたら、必ずできるようになるものだよ」
「誰だって一回でぱっとできたりしないさ」
「できないところからスタートしていけばいい」
そうした励ましや慰めの言葉など、ただの雑音でしかない。惑乱した意識の表層で即座に弾かれる。そして、〈できない自分〉に呑み込まれていく。その自分に歯止めを掛ける代わりに、その自分を拒絶して決して顧みようとしない。だから、それはできる必要があることなのかできなくても済むことなのかを見極めもしないで、とにかく〈できない自分〉から一目散に逃げる。逃げて逃げて逃げまくり、自分が少しでもうまくできる自信が持てないことは、頑としてしようとはしない。
そんなふうにしているうちに、A君は浪人生活が五年目になった。受験を錦の御旗に掲げているが、勉強しようとすると気分が悪くなり、予備校にもほとんど行かれない。勉強しなければいけない気持ちに鞭打たれはするので、机の前から片時も離れられないが、ただ椅子に座ってぼんやりしているか何となくパソコンをいじっている。
B子さん(26歳)は、仕事が長続きしない。初日で辞めてくることもある。「すぐにできなくてもいいよ。少しづつ覚えていってくれたらいいから」と言われても言外に『こんなこともできないのか』と見下されている感じがする。そんなに嫌な思いをしてまで頑張らなければいけない仕事だとは思えないのに、どうして無理して続ける必要があるのかと自問自答して、いつも同じ結論を導き出す。
C夫さんは職場にいるだけで緊張して声や手が震えるのが気になって仕事に集中できない。普段の作業でも同僚や上司とのちょっとしたやり取りでも万全でないことを過度に気にして、くよくよと反省モードに陥ってしまう。『もっとちゃんとやれ。できる筈だ』という自分と『ダメだ。やる気にならない』という自分の間で引き裂かれている。頭痛がしたり身体がだるかったりするので、医者通いを続けるが、症状は一向に改善しない。
誰の心の奥底にも〈できる自分〉とか〈すごい自分〉に対する憧れが埋まっている。けれども、〈できない〉ことは、日々の生活の中で数え上げるだけでも、ピンからキリまで色々たくさん有り過ぎるほど有る。〈できない〉ことよりも〈できる〉ことに焦点を当てていくことが大切には違いないが、〈できない自分〉をとことん嫌悪して排除しきってしまうわけにもいかない。何かできないことがあれば、自分をまるでダメ人間のように感じて激しく落ち込んでしまいがちだが、〈できない自分〉の存在も認め、そのうえでどうするのがいいか、冷静に作戦を立てられないものだろうか。
できない!
その衝撃に打ち克つ力と術を身に付けようとすることが、どれくらいできるだろうか?
★『青天の霹靂』2014.5.2
日常生活に亀裂が走る一瞬がある。その〈一瞬〉が十年一日の如く馴染んだ連続性を断ち、悉く異質なものを雪崩れ込ませてくる。四囲の状況が一変し、ありとあらゆるものが壊れ、奪われ、生死の境界が入り乱れる。そうした、これまでの〈現状〉と不連続な事態を起点にした連続性が以後ごく当たり前のように進行していく、抜き差しならない〈現実〉。
天災。事故。事件。不意に牙を剥く圧倒的な力に対しては抗いようがない。自らの生命・存在・人生に直結する重大事であるにも拘らず、全くの受身で在るほかない。徹底的に打ちのめされる。それでも、九死に一生を得たのであれば、〈青天の霹靂〉以後も生き続けなければならない。悉く過酷な状況下で自らが持ち得ているものを数えて最大限有効利用しようとする気力と術をどのように持ち合わせているのか。
ここ数年、年に一回人間ドックを受けていたA氏(51歳)は、今回も健康のお墨付きを貰うつもりで結果を訊きに行った。そこで医師から肺に見落としてしまうほど小さな白点があるので、念の為に精密検査を受けるように言われ、その場で予約を入れた。数日後、その結果について医師から癌性の疑いも否定できないので更に精密な検査を受けることを勧められて癌の専門病院を紹介された。そこで、いきなり肺癌4期だと告げられて仰天してしまった。
末期の肺癌。まさしく青天の霹靂だった。手術も放射線治療も適用外、化学療法だけが唯一の治療手段だが、根治ではなく延命と緩和が主目的になると説明された。医師の声が意識から遠ざかる。衝撃が真っ黒い渦を巻き、A氏をあっという間に呑み込んで奈落の底に放り出した。A氏は、その後自分がどのようにして帰宅したのかよく憶えていない。
人は誰でも死ぬ。早いか遅いかの違いはあるが、死ぬ運命を免れる人はいない。そう思う一方、早いか遅いかの違いは大きい…と見えない〈蜘蛛の糸〉を手探りする気持ちに駆られる。しかし、すぐに抑える。代わりに、〈死〉がぐっと身近に迫る。寿命が尽きていく音が衰退を予見する体感を縫って響いてくる。幻聴なのか。恐怖心なのか。絶望なのか。戦慄が全身を締め付ける。
A氏は、今、治療を続けながら、自らが生きている時間を生きている。A氏が、そこで見出すもの?それこそが唯一無二の〈蜘蛛の糸〉のような気がする。
★『思うようにならない時』2014.3.6
「思いを遂げたいんです」
思いを遂げる。その起伏ある連鎖によって、個々の人生が特徴づけられていく。
遂げたい思い?欲求?は、私たち自身のあらゆる活動?生命活動・心理活動・社会活動?の細部に行き亘っていて、私たちは欲求のネットワークの中で生きている。
ありとあらゆる思いが次々と遂げられていくのであれば、苦悩も悔恨も恐怖も味わわなくて済むかもしれないが、その分思いを遂げた幸福感も満足感も達成感も鈍磨して、欲求さえも曖昧になってしまいかねない。むしろ、遂げられない思いがあるからこそ、遂げられた思いが光彩を放つ。同時に、思いを遂げるために思案や工夫を重ね、そうした過程を通して独自の人生を創り上げていくために必要な知識や技能が鍛錬されていく。
それでは、思いを遂げたいのに思うようにならない時にどうするか。先ずは、その苦痛な事態に耐えて持ち堪えなければならない。どんなにひどく打ちのめされていても、湧き起こる雑多な感情の濁流に溺れていても、縋る〈藁〉を探し求める意識の部分がどれだけどのように保たれて機能しているのかが明日に思いを遂げるための鍵を握っている。
逆境でこそ自分自身の在り方が問われる。
あれもこれも思うようにならない〈今、ここ〉に、〈私〉だけは自分を見棄てないと誓える〈私〉が本当に身近に居てくれているのだろうか。
★『二つの現実』2014.2.1
〈私〉はいつも二つの現実を同時に生きている。こころの現実と外的世界での現実との間を自分なりにうまくバランスを保ちながら際限なく行き来している。けれども、その行き来に決して慣れることはない。毎回その過程では予期しない吉凶の出来事が起こり、どのような事態であっても臨機応変に対応しなければならない。
こころの現実は〈私〉だけにしか認識されない。そこでは、〈私〉は万能の力を持っているかのように、自分の思いのままにありとあらゆるものをジャグリングして森羅万象を手中に収める。〈私〉が願ったことは直ちに十全に叶えられる。それなのに、何故か満たされた実感が持続しない。満足感が幻のように得体が知れないばかりか、いつのまにか空虚感にすり替わっている。願った通りのご馳走を思い通りの状況でたらふく食べたし、望んでいた仕事も立場も得たし、疎ましい人間たちは悉く悲惨な事態に陥っている。しかし、こころの現実世界から出て周囲を見回すと、不幸な筈の人たちが溌剌として活動している。なのに、〈私〉は空腹なまま手持無沙汰な様子で一人その場から浮いている。〈私〉の存在を、良くも悪くも気にかけている人など誰もいない。それどころか、〈私〉がどれだけ欲しても決して手に入れられないものを持っているのを常態とした人たちが更なる充足を目指している。こんな居心地の悪い世界には片時も居たくない。いったいどこに身を置けばいいのか。身の置き所もこころの拠り所も無ければ、〈私〉はどのように生きればいいのだろうか。
泰子さん(36歳)は、好意を寄せる正明さんが最近冷たくなったと感じて苦しんでいた。少し前までは正明さんの方からメールがよく届いていたのに、最近は泰子さんがメールしても返信がない。電話してメッセージを残しても折り返されない。泰子さんは意を決して正明さんが理学療法士として勤めるクリニックに出向いた。受付で正明さんに来院を伝えて貰ったが、「施術が立て込んでいて会えない」と言われた。泰子さんは家から持参していた果物ナイフをバッグから取り出して、「生きている意味がないから死にます」と手首を切ろうとした。受付の人たちや近くに居た患者たちがびっくりしてあたふたしているうちに3、4人の警官が来た。パトカーで精神科のある病院に連れて行かれた。泰子さんは入院を希望したが、医師の判断で自宅に帰された。
その後、泰子さんは両親の計らいで地元を離れ、都内に住む父親の妹宅に身を寄せた。叔母宅は子どもたちが独立して夫婦二人暮しで面倒見が良く、泰子さんにとっては自宅に居るよりも居心地が良かった。泰子さんは家事を手伝いながらカウンセリングを受け始めた。
「今は正明さんと会えないけれども、いつかきっと何か関わりを持てると思って死にたくなるのを抑えている。もし今後一切正明さんと関わりを持てないのであれば、そのことがはっきりすれば、私は自殺する。いったん死ぬと決めれば、その前に正明さんと関わりを持つことを一度はする」
泰子さんが必死に考え出したこころの現実と外的現実の連結方法である。これで、泰子さんはどのように満たされるのだろうか。こころの現実が実生活の世界に浸透して、二つの現実が渾然一体となっている。こうした〈現実〉では、こころの中で湧き起こった欲求を外的現実の世界で有効に満たすために機能する〈私〉が全く姿を消している。〈私〉がこころの現実に呑み込まれた状態では、二つの現実の間を恙無く行き来することはできない。けれども、泰子さんは、正明さんに関すること以外は、極めて真面で家事などの手際も優れている。
〈私〉は二つの現実を同時に生きているとは言っても、やはり、自らの生身の姿を如実に晒して生きている現実に重きを置かないわけにはいかない。しかし、果たして本当にそうなのだろうか。まさか、そこに〈夢の橋〉を架けるわけにはいかないか…
★『新春』2014.1.7
どこか向こうから駿馬が駆け込んできた。あっという間に傍らを通り過ぎて、後姿が既に視界から消え去ろうとしている。松飾りも今日で取り払われ、時間は刻々と経過して行く。新しい生命が生まれると同時に既に在る生命の寿命は容赦なく削がれていく。夢想する時間は可逆的でアクロバティックに翻りながら放射状に拡がるが、現実の時間は決してペースを乱すことなく四季を循環させながら前進するのみである。
時に夢想しながら、それでも前進を続ける時間から降りる術もなく、眠っている間さえもひたすら前に向かって進んでいくしかない。ふと、どういうわけか、シシュフォスの姿が意識を掠める。来る日も来る日も絶えず転がり落ちる大石を山頂へ押し上げ続ける様子は、来る日も来る日も絶えず巡ってくる朝とか昼とか夜を果てしなく〈次〉へ押しやるしかない自分の生き方に重なるのか。
生きていれば、新春はまた来年も訪れる。今年の新春と来年の新春は自ずと同じではない。そんな当たり前のことが〈今〉やけに意味深長に感じられる。敢えて、その〈違い〉に賭けてみようか。
駿馬に跨って駆け抜ける一年に思いを馳せながら、〈未〉に乗り換えて走る道を思い描いてもみる。それは半ば夢見の意識なのか。今一度、新春が霞の洞から立ち現れる。
★『迫られる決断』2013.12.10 (火)
ある日曜日の昼下り、彰子さん(44歳)は夫と子ども達がゲームソフトを買いに行くのを送り出してからお気に入りのハーブティーを淹れて寛いでいた。電話が鳴り、普通に受話器を取った。声を聞いた途端、強い衝撃が心臓を貫いた。全身が一気に強張り、動悸が打楽器を響かせているような音を立てた。惑乱するのを必死に抑えてなんとか理性の片鱗に縋りつき、「考えてみる」とだけ言って電話を切った。
十年間関係を断絶していた二歳下の妹からだった。妹家族の住まいに近いアパートで一人暮しをしている母親が生活保護の申請を検討しなければならないほど困窮しているので援助して貰えないかという依頼だった。彰子さんは母親ともずっと関係を断っていた。ようやく平穏な気持ちになってきていた時にいきなり有らぬ方から散弾銃を発射されたかのように過去の記憶の断片が瞬時に意識全体に飛び散り、それと同時に不安や空虚感や憤りや淋しさや忌々しさなどありとあらゆる負の感情が噴き出て、彰子さんは大混乱に陥ってしまった。
彰子さんの記憶の中では母親も妹も我ばかりが強くて自分勝手であり、辛かったという印象ばかりが強い。自分が不当に利用されてきたように感じて、彰子さんは十年ほど前に自分から二人との関係を断ち切った。それ以降、連絡を取り合っていない。
彰子さんが小学校5年生の時に両親が離婚し、姉妹は母親に引き取られた。母親はずっと定職に就いていたし、姉妹が成人するまで父親から養育費が支払われていたので、生活には不自由しなかった。しかし、3人の生活は決して快適でなかった。彰子さんは家族の生活に支障がないように努めて家事を担うようにしてきたが、いつのまにか母親も妹もそれを当然のように当てにしているのが不満だった。母親も妹も自分の都合ばかりを主張して、彰子さんの気持ちを汲んでくれようとはしない。彰子さんが少しずつ彼らから距離を取るようにすると、二人から事あるたびに非難された。そうこうする過程を経て完全断絶になってしまった。
彰子さんには、母親が生活保護を必要とするほど経済的に行き詰っていることが俄には信じられない。長年働いてきて貯蓄もあるだろうし、退職金もいくらかは得ている筈である。何かに投資でもして多額の損失を蒙ったのか、詐欺にでも遭ったのか。色々な疑問が湧いてくるが、妹にも母親にも問い合わせる気が起こらない。一回だけの金銭援助で済むのか、継続的なのか。彰子さんには、お金のこと以上に再び母親や妹とやり取りをしなければならなくなるのが負担である。彼らによって今現在の日常性を浸食されたくない。だからといって、放置してもいられない。進むに進めず、退くに退けない。
「いったい、どうすればいいだろうか?」
「老親に対する子どもの義務って…人間的には…」
彰子さんは、早急に決断しなければならない。
★『生き方、二つに一つ?』201311月7日(木)
面談が終盤に差し掛かった頃だった。康夫さん(39歳)から零れた一言は、目には見えないブーメランに乗って約三年間に及ぶ内的作業の時間帯を横断した軌跡のような、内面から芽を出して外側に伸び出て、そのまま自然に半回転してまた内面に戻っていくような不思議な力を宿していた。それは、彼が深く了解した境地から零れ出た言葉だというのがはっきり分かった。言葉が纏う雰囲気には、そうした深い情趣とくぐもり、重み、そして独特の脹らみが醸し出されていた。
「結局、生き方には、するかしないか…しかないんだな」
少しの沈黙の後、康夫さんは言葉を継いだ。
「これまで色んなことを想ってきたし考えてもきた。むしろ、考えすぎるくらいだった。自分では逃げるつもりは全くなかったし、精一杯やってきたという自負もないわけではない。それなのに、心のどこかでもっとやるべきだったという悔いがある。大切な局面で楽な方に流れて、まがりなりにもそこそこの恰好が付くことに甘んじて逃げてきた…その想いが今棘になって気持ちに刺さっている。あの時もあの時も、すれば良かったことをしなかった報いが今なんだ。現状は、自分がしてきたことによって一応支えられてはいるけれど…」
〈今、ここ〉でそれをするか、しないか。些細なことから重大なことまで、人生は選択の連続である。何をして、何をしないか。重層的で複雑な状況を生きるのは、なかなか困難で多様的ではあるけれども、康夫さんが言うように、結局は、二つに一つ、極めて単純明快なのかもしれない。
実際、他者に助けられることも運に味方されることもある。けれども、康夫さんが行き着いた了解に深く頷ける。
「人生、自分がしたことによってしか報われない」
★『良質な人間』2013年10月2日(水)
人間の品位とか品性もしくは人間性の質などは、学歴とか肩書きとか財力とか日常の暮しぶりなどでは計り知れない。非常に洗練された装いで上品な雰囲気を醸し出している印象の人が必ずしも高邁な人徳の持ち主であるとは限らない。
B子さん(41歳)は、現在7歳と3歳の子どもを育てる専業主婦である。彼女とは、彼女が20台後半の頃から10年余りオフィスでお会いしてきている。当初、彼女はある優良企業で総合職として働いていらしたが、疲労感や吐き気が強くなり、会社に近い病院の内科を受診された。暫く服薬を続けていたが、症状が一向に改善しなかった。それどころか吐き気が四六時中して動悸と胸痛も加わった。何回か病院を変えて検査をしたが、これといった所見は認められないまま対症療法的に処方される薬を飲み続けていた。そうこうしているうちに1年間休職し、その後退職した。その前後頃から精神科を受診するようになり、そこでカウンセリングを勧められた。
初めて来談された時、彼女の身なりはセンスよく整っていたが、表情は暗く沈んで締りがない感じだった。半ばよろけるような独特の歩き方で椅子に崩れるように坐られた。そして、「どうぞ助けて下さい。もうどこにも縋れるところがないんです」と言って頭を膝の上にぴったりくっつけたまま、数秒間そのままでいらした。
「1日中ずっとむかむかしていて吐きたいのに、吐くのが恐くて絶対に吐けない。いつも込み上げてきそうになるのを抑えている感じで気持ちが悪い。吐けば、楽になると思うけど、大切なものまで一緒に吐いてしまいそうで恐い。」
毎回定刻に来談されるが、次第に服装の組み合わせが色的にも材質やデザイン的にも全くちぐはぐになり、一度に10万円以上の買物を頻繁にしたり、誰彼なしに遊んでセックスしたり、過食・リストカットをしたり、彼女がどんどん壊れていくのを目の当りにして、私自身、戦慄を覚えながら対応に四苦八苦していた。それでも、毎回定時にオフィスに現われる彼女との間で少しずつ相互に取り込まれていった信頼感が関係性の底に堆積されてきているのを感じてもいた。
彼女がある時、通りがかりにふと立ち寄ったキリスト教会で偶々出会った男性と意気投合した。彼は30台半ばを過ぎていたが、知的障害のある姉がいて、これまで付き合った女性との結婚が具体化すると破談になることを一度ならず経験していた。彼は彼女の話に耳を傾けて心の叫びを聴き取ろうとしてくれた。丁度その頃、カウンセリング過程でも新たな展開があった。
「吐くのが恐くて懸命に抑えている感じは、小さい時にお母さんに言いたいことがあるのに、言って怒られるのが恐くて我慢していた時の感じと同じ…」
彼女は、自分にとって大事なことだとして結婚後もカウンセリングを続けることを彼に了承して貰って結婚した。彼の両親と同じ敷地の別棟に住み、普段は全く独立した生活をしているが、週末に義姉が入所している施設から帰宅する時は自分から姑を手伝いに行った。彼女には、まだ非常に不安定な部分があり、それが時折牙を?くことがあって突拍子もない額の買物をしてしまったりしていたが、第1子の妊娠に気づいた頃から〈子どもを守る〉という生き甲斐を強く感じ始め、子どもの為に少しでも多くお金を使えるようにしておくことを心がけるようになった。心の中に確固たる礎が据えられ、彼女は見違えるようにしっかりしてきた。彼女は育児に夢中になり、第2子も生まれて多忙な毎日である。
最近、姑の認知症が進行して身の回りの世話も舅を煩わせるようになった。彼女は結婚する前は義父母と同じ敷地内に住むことを嫌がっていたが、「お義父さんが元気とはいえ高齢なのに可哀想。私ができることは助けてあげたい気持ちになった」と言う。毎朝、夫と子ども二人を起こして朝食を取らせてから各々会社と小学校と保育園に送り出した後、大急ぎで自分も朝食を済ませ、後片付けはしないで隣に行って義父母の朝食を準備し、1時間近くかけて義母に食べさせ、入れ歯を洗い、後片付けをして、義母が零した食べ物で汚れ放題のダイニングキッチンの床を拭き、いったん自宅に帰って朝食の後片付けをする。一服する暇もなく、掃除や洗濯をして買物とか銀行に出かける。そうした生活をずっと続けている。
彼女は、これまでの長い間自分が幼少期に負った根深い傷に気づかないまま訳の分からない体調不良とその苦痛に苦しみ、自己崩壊の瀬戸際でのたうっていた。その人が目前で不自由や不如意な状態を強いられている人を放っておけなくて気遣いを示す。その心意気。優しさ。深い慈しみ。
本当に、今、私の目の前にいる人は、あの破茶滅茶だった彼女なのだろうか。
全く思いがけないところで、不意に良質な人間に出会った感動で全身が熱く漲った。
★『不戦敗!?』2013年9月5日(木)
由梨さん(29歳)は、小さな貿易会社で事務をしている。その仕事に就いてから2年余りが経ち、派遣から正規雇用になるのを期待していたが、次回で契約を打ち切ると通告された。
その会社で正社員になるというのは、何も根拠のない、由梨さんが勝手に抱いた淡い期待だった。けれども、高校を卒業してから殆ど日替わりと言っていいほど仕事を次から次に辞めてきた由梨さんにとって、現在の仕事は、これまでで一番長く続いていて、その間には数え切れないくらいの不本意な事柄や傷つく場面があったが、「このままでは自分がダメになる」という危機感で今にもすぐに辞めてしまおうとする自分と闘ってきた。最も苦手だった〈地道な努力〉もしようとした。その甲斐があってパソコン検定に合格した。自分の中に一本の杭が打ち込まれたかのように、ずっと曖昧だった自分がぎゅっと凝縮された質量感を鮮明に感じた。初めての経験だった。少しずつ自分がより好ましく変わっていく手応えを感じ始めていた矢先での契約の打ち切り通告だった。
「やっぱり私のような人が頑張ったところでたかがしれている…」
「私のような人を雇ってくれるとこはあるのだろうか。」
再び根深い疑惑が浮き出てきた。
「私のような人が必要とされることはあるのだろうか。」
「私のような人にできる仕事など無いんじゃないか。」
「私のような人が生きていて自分も周りの人も楽しくなることなんてあるんだろうか。」
〈私のような人〉と由梨さんは否定的な意味を込めて何度も言う。〈どうしようもない人〉〈ダメな人〉という自己イメージがこびりついている。そのために、どれだけ由梨さんはこれまで自分がしたいと思うことをしたり、欲しいものを手に入れようとする前に諦めてきたことか。今も職場に好きな人がいるが、〈私のような人〉の気持ちが相手にばれるのが恥かしくて素知らぬふうを装っている。
〈どうせうまくいく筈がない〉と及び腰で事に当たれば、当然何事もうまくいく筈がない。不戦敗である。今回も由梨さんは、事務職で長く働ける仕事に就きたいが、〈どうせ無理だ〉と決め込んで求人情報を見る気にならない。ようやく自分の力を少しは信じてみる気になりかけていたのが敢え無く挫けてしまった。
それでも、由梨さんの意識の片隅でパソコン検定に受かった時に覚えた濃密な感覚が残響を放っている。
「あの感覚。全身からひたひたと寄せてきて、私に私自身を強くはっきり感じさせてくれた。あの感覚を一回だけのことにしたくない。」
「あの感覚は、私自身がしんどい思いをしなければ、得られなかった。あの時ほど一生懸命に勉強したことはなかった。」
「つつましいものでもいい。人から見れば全然大したことでなくても、あの感覚がまた持てたら、私なりに元気になれると思う。あの感覚を得るために、本気を出して自分の力を出せるだけ出してみたい。自己満足でもいい、ですよね?今は、そんな生き方に憧れみたいなものがある。」
「とりあえず、職探し、やれるだけやってみます。」
★『声なき声』2013年8月6日(火)
「自分がどんなふうに動いたらいいのか分からなくなって、辛い。他の人は自分が思ったことを思った通りにやって、どうして認められるんですか?」
法子さん(21歳)は、介護老人ケア・センターで車椅子を片づけている最中にいきなり涙が溢れて床に蹲ってしまった。すぐに気づいてくれたスタッフに休憩室に連れて行かれて暫く休んでから早退した。翌日は午後から出勤だったが、そのまま仕事に行けなくなってしまった。
「自分では早く介護の仕事に慣れたいと思って自分で気づいたことをやっていた。入浴介助の時に綿棒で耳を拭いてあげていたら、そんなことしなくていい、と先輩から怒鳴られた…おむつ交換の時に、この方は量が多いからと思ってパットを挟んだら、そんなことはしなくていい、って苛々した声が飛んできた…自分がいいと思って何かしようとしても、金縛りにあったみたいに体が動かなくなった。何をするのが良くて、何はしなくていいのか、分からなくなって…何かしようと思うと、そんなことしなくていいっていう声が飛んでくる気がして怖い。それでもお年寄りの方が少しでも気持ちいい方がいいよねと自分に言いきかせてやっていると、こんなことをしていていいのかと思ってきて、どうしたらいいのか分からなくなった。」
「他の人は必要なことがちゃんと分かってできているのに、私がやっていることは他の人から見れば、しなくていいことで、私は余計なことばかりをしているのかと思ったら自信がなくなった。」
法子さんがしていることは、すくなくともお年寄りにとってはどれも好ましいことである。けれども、沢山の入所者がいて一人ひとりに掛けられる時間や労力および経費が制限されているというスタッフもしくはセンター側の立場からすれば、なかなか奨励し難い側面もあるのだろう。
高齢化が進む昨今、法子さんの不調は〈介護〉の本質を問う重要な問題を示唆している。彼女が介護の現場で居場所を確保して彼女らしい資質を活かした働き方ができるように、どのような対策とか工夫を講じられるのか。
『早くセンターに戻ってきてね。あなたにして貰いたい。』
法子さんの耳にお年寄りたちの〈声なき声〉が届くだろうか?
★『葛藤会議』2013年7月1日(月)
「ねえ、君には自分が何人いるの?」
「え?俺はいつだって自分は一人だよ。君は、そうじゃないの?」
「っていうか、今こうやって汗を拭きながら話している僕は一人だし、一人が当たり前だと思って暮らしているよ。だけどね、一人のくせに、僕の体の中に僕が何人も詰まっている気がして、騒がしくて疲れてしまうことがあるんだ。そんなことって、全くない?」
「俺にはないけど、なんとなく君が言っていることも分かるかな…」
浩司君(17歳)は、何をしていても、また、何かをするにしても、四六時中騒々しくていっこうに収まらない内面の喧騒に否応無しに巻き込まれて消耗し切っている。
浩司君が風呂に入っていても、受験勉強をしていても、即かず離れずの距離からずっと監視している人がいる。背後霊のような人で、時によって怒っていたり、嘲っていたり、ニヤニヤしていたりする。それだけでも実に鬱陶しいのだが、時には「ダメな奴だ」とか「器が小さいな」とか「甘いんだよ」とか野次を飛ばしてくるので、気が散って仕方がない。
さらに、そうしたことにも況して、浩司君が今一番困っているのは、時と場所など全くお構い無しに勝手に始まる葛藤会議にいつもいつのまにか引き摺り込まれていることである。つい先程も、友人にメールをしようとしていると会議の真っ只中になっていて、「メールしたくないんだったら、無理にすることないじゃん」と言う奴、「その日は都合が悪いと予め伝えておかないと、あいつだって段取りに困るじゃないか」と助言する奴、「まだ先のことなんだから、今メールしなくてもよくない?」、「さっさとしちゃいなよ」、「なんでそんなことにそれだけ悩むわけ?」などなど。会議が延々と続いた。
毎度のことながら、会議に任意で出席して口々に意見を言う連中は何人かいるのだが、それらの意見を取り纏める進行役が、どうもいないわけではないらしいが、今一つ頼りない。浩司君が携帯を手にしたまま、既に40分が過ぎていた。「こんなことをしていられない」と苛々が募って焦ってきた。このまま棚上げすれば、必ずまた葛藤会議が始まるに違いない。「いやだっ!」という全面拒否の気持ちで一杯になった。その気持ちに背中を押されて、浩司君はメールを書き終えて〈送信〉をクリックした。
葛藤会議は引っ切り無しに行われる。それでも、以前と比べて最近は、葛藤会議で結着のつくのが一段と早くなった。而も、そればかりではなく、以前には無かったことだが、葛藤会議が直前で中止されたり延期されたりすることがあるようになった。そうした変化に伴って浩司君は、穏やかな気持ちでいることが増えて元気になってきた。
★『結局、自分で選んできたんだな』2013年6月4日(火)
「こんなところに来たかったわけじゃない。なのに、今はここにいて、きっとこれからもずっと不満をいっぱい抱えてここにいるんだろうなあ。いったい私は何をやってきたんだろう。このまま年だけ取って…これからも毎日、私は本当に何をやってるんだろうと思って生きていくのかしら…」
真菜さん(48歳)は、母親と二人で暮らしている。短大を出てから数年間は地域の信用金庫に勤めていたが、30歳になる直前に好きな手仕事に携わりたい気持ちが強まって退職し、洋裁の学校に通うことにした。そしてその頃、癌を患っていた父親の希望で母親と在宅看護をしていた。父親が少しでも快適に過ごせるように細やかに気遣うと同時に体の弱い母親に負担がかからないように自分が率先して動くようにしていた。けれども、結婚して近くに住む姉が余り親身に関わろうとしてくれないことに不満を募らせてもいた。姉は、来てもすぐに帰ってしまう、ちょっとした気掛りを姉に話したくて電話しても「今忙しいから」とすぐに切られてしまう、「私には私の生活があるのだから、そんなに実家のことに時間を使えない。お父さんを家で看てあげたくても出来ないのであれば、やっぱり入院して貰うのがいいんじゃないの?」と進言される。
父親が亡くなった後、真菜さんは既に洋裁学校を二年で修了して自分でブラウスやワンピースなどをデザイン・縫製して知合いのブティックの一角に置かせて貰ったり、ショッピング・モールの手作りコーナーの棚を借りて展示販売をしたりしていたが、色んな気持ちや想いが入り乱れて不安定になってしまった。自分では二進も三進もいかなくなり、自分から希望して精神科を受診して入院した。三ヶ月ほどで退院したが、それから数年間は自分自身の土台が磐石でない感じに侵されて闇雲に何か縋れるものを求めて足掻き続ける苦しい日々だった。
「私には何もない。母がいなくなったら、私一人になって、その先ずっと一人で生きていかなきゃならない。そしたら、いったい私はどうなってしまうんだろう…?」
最悪な事態を想定した悲観的な考えが次から次に津波のように押し寄せて、真菜さんの現状での安全な生活を根こそぎ呑み込んでいく。そうした惨憺たる状況に曝されながら、真菜さんはカウンセリングに通い、当初はやり場のない苦痛と不安の叫びをあげて激しく嗚咽するばかりだったが、そのうちにそうした自分の声が他者の声のように自分の耳に入ってきて、少し冷静に自分でそれらを聴き取れるようになってきた。そうした過程を通して、叫ぶ自分に対峙して聴き取る自分の存在がはっきりと自覚されるようになっていった。そうした中で、最近は、気持ちが大分落ち着いて、これまでとは様相の異なる新たな感慨を覚えるようになった。
「けっこう一人でいることに抵抗がなくなってきた。色んな人生があって、私は一人で生きていく人生なのかな。自分が壊れてしまうくらい悩んできたし、決して人が憧れるような人生ではないけれど、やっぱりいくつもの大事な局面で私はその都度自分で心地良い方を選んできたんだよな。そう感じたら、それならそれで自分の人生を引き受けて充実させればいいじゃん、と思えた。だけど、人生の最期に自分が納得して〈これで良かった〉と思えるには、今のままではダメ。いつまでもぐだぐだしていないで、もういい加減、洋裁しか取柄がないなら、それで人とか社会に関わっていくことを自分なりにやっていけるといいのかな。」
★『失われていた記憶とその痕跡』2013年5月8日(水)
電車に乗るのもエレベーターに乗るのも怖くてパニックになる紗希さん(41歳)は、そのために外出することも仕事に就くこともままならない。自宅から車で通えるドラッグ・ストアでパートをしているが、ずっと独身で生きていくために安定した収入を得られる正規雇用の仕事をしたいと思っている。けれども、車通勤が可能でなかったりオフィスがビルの階上だったりして、なかなか思うに任せない。現在は、親と同居して比較的裕福な生活を享受しているが、パートの収入だけでは将来的な生活の安心を見込めないので、早く自分の状態をなんとかしたいと焦っている。それに、何よりも今のままであれば、彼女自身が買物に行くにしても友人と一緒に行動するにしても不自由であり、日々の暮しが制限されて生きにくさが募っている。
こうした紗希さんの症状が出現したのは、彼女が専門学校を卒業して家電量販店でアルバイトを始めた頃である。それまではなんとなくいつも一緒に居る人が数人いて、彼女が一人で行動したり何かを任せられたりすることはなかった。しかし、アルバイトを始めると与えられた仕事を一人でこなして責任を負うことが求められた。彼女は簡単な作業であっても自分がしていることに確信が持てなくて、これで合っているのか、何か指摘されないか、と不安に駆られて不要に時間がかかってしまう。そのことを注意されると、自分はダメだという思いを強めて仕事を辞めてしまうといったパターンを何回か繰り返した後、自分に自信をつけるために資格を取って自宅で開業できればいいと考えて司法書士を受験するための予備校に通い、数回試験に落ちてから通信教育に切り換えて約10年を過ごしたが、合格に至らない。暫くの間勉強から離れたくてドラッグ・ストアでのパートを始めた。
電車とかエレベーターに乗るのが怖いという症状について、紗希さんは「乗ってる時間が長いか短いかは関係ない。混んでいるとダメだけれど、私がパニックになるピークは、乗りました、ドアが閉まりましたというセットの状態。動悸が激しくなって息ができなくなる」と言う。カウンセリングを始めた当初は、「降りたくても降りられない。自由に動けない」という拘束感とか無力感に着目していたが、そうした症状を持つ人に共通する「美容院や歯医者に行くのが怖い」という訴えは無く、四方が物理的に開かれた空間はなんともない。決死の覚悟で電車に乗った場合、ドアの近くに立てば直ちに金縛り状態になってパニックに陥るが、窓の前であればまだ少しはましとのことである。
不可解な症状である。これまでにいくつかのメンタル・クリニックを受診して系統的脱感作法や自律訓練法を試したりもしたが、一向に改善しなかった。彼女自身、「どうしてただ乗るだけのことができないのか本当に不思議」。
ある時、カウンセリングのセッションで紗希さんは幼年時代のことを話していた。
「幼稚園でトイレに行けなかった。家のトイレは広かったけれど、幼稚園では狭いとこに鍵をかけて閉じ籠らないといけない。先生が外でドアを押さえてくれていてもダメ。トイレがすごく怖くておもらしばかりしていた。それに昔は暗いとこもダメだった。けど、今は大分平気になった。それでも今も寝る時は真っ暗にしないで豆電球を点けたままにしている…母は私がものすごく小さい時、クローゼットに閉じこめた。一畳位のスペース…わんわん泣いても出して貰えなかった。母は怖いというよりもいつも正しい…正しいことしか言わない人…」
これまでもカウンセリングで幼年期のさまざまな出来事について話されることは度々あったが、このエピソードはずっと忘れていたとのことだった。幼い紗希さんにとっては、余りにも恐ろしい体験だったに違いない。絶体絶命の恐怖感。その出来事の一部始終は瞬時に凍結して意識の奥底に隔離保存されたが、最も強烈な知覚体験だけが断片的に記銘された。クローゼットの中に入った、扉が閉まる、鼻先で扉が閉まった、出られない。その状況は、まさしく電車やエレベーターに乗った、ドアが閉まる、ドアが閉まった、降りられない、であり、過去の圧倒的恐怖の体験と重なり合う。
幼児期では、まだ体験を言葉で把握しきれない。それゆえ、一つの強烈な体験はまとまりを欠いた外傷的な情動記憶として銘記され、当時の出来事に類似した体験刺激を通して恐慌的な恐怖感が喚び起され続ける。けれども、今回、長い苦痛とその治療過程を経て、自ずと凍結度が緩まりつつあり機が熟していたのだろう。紗希さんは忘却の彼方から蜃気楼のように浮上した外傷記憶を言葉にした。そのことによって、隔離を解かれた記憶は紗希さんの人生を物語るひとつの構成要素として新たに保存され直す。
今後、求職だけでなく外出や買物での選択肢を広げて楽しむ紗希さんの姿が見られそうである。
★『真っ暗いトンネルのただ中で』2013年4月3日(水)
綾香さん(33歳)は落ち込む気分にどんどん引き摺り込まれていくのをどうすることもできない。どこに助けを求めればいいのか。現状を変えることはできないのだから、自分が里美さんのようになりさえすれば、今の状態がごく当たり前の家族の生活になって、そこで起こるさまざまな出来事に一喜一憂しながらそれなりに恙無く暮らしていけるのに。里美さんは美代ちゃんが呼びかけに応じなくても癇癪を起こして奇声を張り上げても泰然自若として優しく受け容れている。美代ちゃんが可愛くてしようがないという様子で定型発達の子どものお母さんたちに交じって娘の言動をあれこれ披露して屈託なく笑っている。努力してそうしているというふうではなく、全く自然で違和感がない。ありきたりなお母さん同士のお喋りに溶け込んでいる。綾香さんはそうした里美さんの姿を目の当りにするたびに「どうしてあんなふうにあっけらかんとしていられるのだろうか」と捉え処のない謎が深まる一方、「あんなふうになれたらどんなに楽だろうか」と定型発達児のお母さんたちに引け目を覚える自分を顧みて憧れる。
綾香さんは子どもができたのを知った時は本当に嬉しかった。自分の中に日々育っていく命が在るということで強く、かつ深く、満たされた。熱い感動で全身が浸されて自ずと生気が漲り、今まで経験したことがない濃密で鮮やかな感覚に包まれていた。良太君が生れて一、二年は、仕事と育児で大忙しだったが、とても充実していた。けれども、少しずつ良太君の様子が保育園で見かける同年齢の子どもたちと違うことが気になり始めた。名前を呼んでも反応しなかったり微笑みかけても微笑み返さなかったり視線を合わせることが少なかったり言葉が遅かったり、他のお母さんが子どもの指差す方を見て楽しそうにやり取りしているのに、良太君は勝手に動き回ってばかりいる。
良太君が3歳になって暫くして発達障害と診断された。その頃から綾香さんの気分が落ち込み始めて、段々全身がだるくなって動くのが苦痛になった。休職してなんとか良太君を保育園に預けて最低限の家事と育児をこなしていたが、吐き気と頭痛もひどくなるばかりで動こうと思っても身体が言う事を聞かない。夫は仕事を休むことはできないし、実家の両親は自営業で手伝いに来られない。夫の両親が一時的に地方から来てくれたりするが、それほど頻繁にも長期的にも家を空けられない。夫からも親たちからも「あなたがしっかりするしかない」と口々に言われるし、綾香さん自身も「このままではいけない」と焦っているが、自分で自分をコントロールすることができない。
「神様はその人が背負える試練しかお与えにならないと言うけれども、それなら神様は私のことはよく分かっていらっしゃらない。どうして私なのか。良太は定型発達の子どもと本当に違うし、育てた先にある彼の姿に夢を描けない。もううんざりだと思う自分が許せない。良太ができて、本当に幸せだった自分を失いたくない。もう一度良太がいるというだけで身体の奥からエネルギーが溢れ出てきていた自分に戻りたい。」
綾香さんは、今、真っ暗なトンネルの中にいる。出口が見えない。塞ぐ気持ちを取り直そうと思う矢先に気持ちが沈む。どんより淀んだ気配に打ちのめされる。泣いても事態は動かない。いったい救いはあるのか。どこに?どんなふうに?この現状の中でどうすれば、より明るい明日を迎えることができるのだろうか。
綾香さんは暗い心の片隅で決して逃げ切れない現状に深く関与することによってしか救いに繋がるルートは無いように感じている。ただ、今は身体が付いてこない。
厳しい現実と千々に乱れる心の中の世界との間で、綾香さんは今後どのように動いて行くのか。その軌跡には、唯一無二の人物像が鮮やかに映し出される。
★『弱腰の波紋』2013年3月4日(月)
中堅企業で経理の仕事をしている由紀さん(29歳)は、ここのところ、企画開発室で事務をしている同い年の里美さんに対して「やっぱり変だ」という感じと苦手意識をどんどんエスカレートさせていた。一緒にランチをしたり合コンに行ったりもしていたが、最近はなるべく関わらないようにしているが、どうしても仕事でやり取りをしないでは済まされない。
その日、由紀さんが席で仕事をしていると、里美さんがいきなりすごい剣幕で食ってかかってきた。
「ちょっとぉーっ、山口係長の出張は明日なのに、出張費はどうなっているのよ!」
「事前払いの申請書が出ていないと思うけど、確認してみます。」
「ちゃんとしてよ。私が係長に訊かれて杜撰だと思われてしまうでしょ。本当に経理があなただと困るのよね。」
里美さんは捨て台詞を残して行ってしまった。由紀さんは言われっ放しになって悔しかったが、とりあえず自分が申請書の提出に気づかなかったのではないかと思って、まさかこんな所にある筈がないと思うところまでも念入りに探したが、見つからない。その旨、由紀さんが電話で伝えた時、
「申請書は室長の机の上に置かれっ放しになっていた。室長の認印を貰ってすぐそっちに持って行くから今日中に出金できるわよね。」
と里美さんは自分の非を棚上げにして高飛車に言い放って電話を切り、すぐに由紀さんの所にやって来た。由紀さんは、恐らく里美さんが室長に何も告げずにただ申請書を彼の机の上に置いておいたことが事の顛末に違いないのに、里美さんが一言も詫びようとしないことに内心憤っていたが、里美さんとの話が長引くのが嫌でそのことには触れずに話を進めた。
「出金は、小切手を銀行で現金化しなければいけない経理の手続き上、最短でも申請書が提出された翌日になります。」
そうしたことは里美さんも熟知しているので、今回はいったん係長に出張費を立て替えておいて貰い、事後出金ということで結着すると由紀さんは思っていた。それで、通常の事後申請の手続きとして申請書と一緒に出張報告書を提出して貰うように蛇足と思いながら伝えた。その途端、里美さんの表情が険しくなり、
「申請書は経理で預かっておけばいいじゃないっ…その方が二度手間にならないでしょ」と声を荒げた。
「でも、普通、事後出金の場合は、いつでもそうしてきているでしょ…?」
由紀さんは、これまでも何度も出張費の出金を里美さんとの間でも繰り返してきているので、思いもよらないことを言われてたじろいでしまった。〈この人、変だ〉と思いながらも気持ちがどんどん怯んでどうすることもできない。言葉がもたつきしどろもどろになる。結局、申請書を由紀さんの机に置いたまま、里美さんは行ってしまった。
由紀さんは自分の弱腰が相手を付け入らせるのだと分かっている。明らかに相手の方に非があると思っているのに、どうしても毅然とした態度を取ることができない。由紀さんは悔しくて「あんな人、死んでほしい」と憤る一方で不甲斐ない自分が嫌いだと言う。
「私がビシッと言えないのは、自分に確信が持てないから…特に、相手が強く出てくると弱腰になる。私が思っていることが合っているのか。この考え方で本当にいいのか、はっきり分からなくなってしまう。」
由紀さんの弱腰の根元には、自分を信じられない由紀さん自身がいる。そうした自分であるのには、もちろん、それなりの理由がある。根っこの深い問題であり、その波紋は由紀さんの生活のさまざまな場面で同心円状に拡がっていく。
★『旅の麻酔作用』2013年2月12日(火)
トルコを旅した。僅か10日間だったが、イスタンブルからアンカラ・ポアズカレ・カッパドキア・コンヤ・パムッカレ・エフェソス・エイドレミット・トロイなど、日中の気温がマイナス2度から20度に変化する地域を移動し、ボスフォラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡を通る際は場所によってヨーロッパ大陸側とアジア大陸側を一望して東西文化の交流の有様の一端を目の当りにし、現代から紀元前に跨る時間を行き来した。紀元前の遺跡群やヘレニズム時代・ローマ時代・セルジュクトルコ時代・オスマントルコ時代のモスクや隊商宿やハムス(公衆浴場)、現在も賑わう歴史的な由緒のあるバザールや市街や港、黒海・地中海・エーゲ海に通じる新旧の道や海沿いの道、パムッカレの石灰棚やカッパドキアの奇岩群など数千万年前からの自然の営みの様子などを次から次に巡り続けているうちに不思議な現実感に捉われた。
時間と空間が縦横無尽に移行したり重層したりして錯綜する。自分は日本国籍を持つ旅人であるが、馴染みのない言葉と人々および文化と景観と習俗の中で見当識を失い、半ば夢遊病者のように異界を彷徨っているかのようだった。時折、インターネットや衛星放送で日本のニュースを見聞したりもしたが、それらも〈今、ここ〉での現実とは別次元の出来事に過ぎない。そうした独特な現実感の中で、まるで魔法の絨毯に乗って移動しているような感覚で帰国の途についたので、飛行機が着陸して暫くは〈浦島太郎〉のように竜宮城から持ち帰った玉手箱を不用意に開けたわけではないのに、自分が周囲にそぐわない身元不明者のように感じられた。
トルコはエキゾチックで眩惑されることが多かった。イスラム教の国らしく至る所に尖塔のあるモスクがあり、一日に何度か祈りの声がマイクを通して聞こえてくるが、他のイスラム圏の国とは違って政教が分離していて戒律はそれほど厳しくない。飲酒禁止ではなく、旅行者でなくても、レストランで酒類を普通に楽しめ、スーパーマーケットでも手軽に買うことができる。女性の服装もスカーフで頭髪を覆っている人は多く見かけたが、顔を隠している人や真っ黒い布をすっぽりと全身に纏って目だけを出しているブルカを着た人は殆ど見なかった。それでも、道端に漂う多種多様なスパイスの香りとかどこでも供されるチャイ(お茶)の真ん中がくびれたガラスのグラスとかカラフルでデザイン性に富んだタイルとか、四方八方にエキゾチシズムが溢れている。
今回の旅で印象的な事柄はいくつもあるが、その一つに洞窟住居で暮らす家族との出会いがある。「妖精の煙突」と呼ばれる奇岩群で世界遺産になっているカッパドキアに近いギョレメには、沢山の洞窟住居がある。6、7世紀頃、ローマ皇帝やアラブ・イスラム勢力の弾圧から逃れたキリスト教徒たちが隠れ住むために巨岩群を利用した。それらが今も尚住居として用いられていたり、洞窟ホテルになっていたりする。
私が訪れた洞窟住居は3階建てになっているとのことだった。洞窟の中に階段は無く、全体的な洞窟の構造はよく分からないが、言われて帰りに見ると、洞窟の外側に階段が作られていた。洞窟の入口には木製のドアが取り付けられ、床には隙間なく絨毯が敷き詰められている。ドアの内側はすぐ台所になっていて、近代的な流しとトルコ独特の2段式の薬缶が湯気を立てているガスコンロと大きな冷蔵庫があり、岩を刳り貫いて作った2、3個の棚に食器が重ねられている。台所の奥はほぼ円形の、13畳位の空間があり、壁に沿っていくつかの電球が垂らされているが、中はかなり暗い。壁際にテレビ・二つの寝台兼椅子が置かれ、煙突を取り付けた薪ストーブと小さな座卓と織機がある。多少凸凹感があるが肌触りの良い絨毯を敷いた床に坐って娘さんが持ってきてくれたチャイを頂く。温かくて、なかなか居心地が良い。トイレは、入口を出た先の小屋にトルコ式の便器(和式に似た便器を跨いで屈んで用を足す)が据えられている。トルコ式では、紙は便器の中でなく側に置かれた入れ物に棄て、バケツに溜められた水を汲んで便器に流すようになっている。風呂はなく、湯をたらいに入れて体を拭く。日本での便利な暮らしに慣れていると、トイレと風呂は些か難儀するが、そこで暮らす家族の表情は穏やかで満ち足りているように見受けられた。特に、母親は、その環境で家事と育児をこなし、暗い部屋で売り物になる細かいレース編みをしたり絨毯を織ったりする。その繰返しの生活にしっかりと根を下ろして家族を大切に思う気持ちが根源的に豊かな雰囲気を醸し出している。娘は母親とは異なる生き方を選ぶのかもしれないが、その洞窟住居に充満している濃密な温かさと家族で一日に何度もチャイを飲む安らぎを心の底に蓄積させて新たな土地を遊牧(?)する逞しさを養っているに違いない。
世界中どこにでも人々の生活がある。旅をしてそれらを垣間見ることは、不思議な麻酔作用を及ぼされるように、自分の日常では体験することがない感覚や認知をもたらされて自分自身の深い部分が反応する。その過程は、私にとって、必ずしも快くはない場合もあるが、自己の意識変容の機会は何物にも代え難い。
★『途切れない〈今〉を寿ぐ2013年1月5日(土)
新年が明けた。
時間は決して途切れることはない。
自らの尾を銜えて環になった蛇(ウロボロス)のように。
時間は非可逆的で直進するのみではあるけれども、
元旦は前の年の大晦日を呑み込んでグルグル塒を巻きながら時を刻み、
再び新たな元日にその大晦日を銜えられる。
グルグルグルグル
始まれば終わる。
終われば始まる。
グルグルグルグル
心の中の時間は蛇行する。
逆行し、途切れ、飛躍し、停止する。
前後左右を自在に跨いで放射する。
グルグルグルグル
2013年
平成25年
巳年
世界の、
日の出る本の、
再生する生き物の、
〈私〉の、
改まった年
グルグルグルグル
混沌(ウロボロス)から統合(シジギー)へ
そして再び混沌から統合へ
グルグルグルグル
巡る時は、途切れない〈今〉
〈私〉は放射する時間を、直進する時間を、生きる。
終わりが始まる〈今〉まで、ずっと…
★『生きる姿勢』2012年12月6日(木)
『置かれた場所で咲きなさい』
非常に印象的な言葉である。
本当にそうだよな、と余韻がじんわりと心の芯に染み入ってくる。
ノートルダム清心学園の理事長でシスターの渡辺和子氏の著書(幻冬舎)のタイトルである。
「暗いと不平を言うよりも、すすんで灯りをつけましょう。」
「どのような状況や立場であっても、そこに置かれている間は、置かれたところで自分しか咲かせることが出来ない花を一生懸命に咲かせる…」
「自分は自分のままで置かれたところで精一杯に咲いていればいい。」
「咲くということは、笑顔で生きるということ。明るく前向きに生きていくということです。」
私たちは、日々の生活の中で、〈ここではないどこかに行きたい〉とか〈こんな筈ではなかった〉と現状を辛く思って不平や不満を募らせることがよくある。自分と他の人たちを比べて劣等感や羨望で苛まれることもある。そうであれば、自ずと気持ちが暗くなり、やる気が失せ、周囲の人たちを恨み、明日に希望を見出せない。絶望して自暴自棄になるか、心身を病むか、衝動的な行動で自分と他者を傷つけるか?自分で益々自分を窮地に陥れていく。
〈今、自分が置かれたところ〉を逃れても、またすぐ新たに〈今置かれたところ〉に居合わせなければならない。ただ逃げるだけでは、決して逃げ切れない。
逃げても、逃げても、そこは、〈今、置かれているところ〉。
〈ここではないどこか〉に楽園が本当にあるのか。それは、際限なく追い続ける〈見果てぬ夢〉なのか。
大切なのは、〈今、置かれたところ〉がどんなに不本意であるにしても、そこに置かれている間は、その状況と立場を受け容れて自分なりに一生懸命に生きようとすること。苦悩に搦め捕られてしまわない部分を少しでも多く保って、最大限主体的に、自発的に、自分が持っている力を懸命に発揮しようと心がけること。そうした生きる姿勢だけが明日の幸福に繋がっていく。
人目に付かない泥地や荒れた地でけなげに咲く小さな花は、美しい庭園で華麗に咲くバラやカトレアよりも見劣りがするだろうか。むしろ、各々の花が其々に置かれたところで咲く個々の特徴的な生色に心を奪われるのではないだろうか。
私たちの円滑で快適な日常生活は、私たちのひとり一人が個々に置かれた場所と立場で自らの役割を引き受けて自分なりにベストを尽くそうとすることで営まれている。そして、そのことが自分自身と他の多くの人たちを連鎖的に幸福にしていく。
『置かれた場所で咲きなさい』
思いがけない啓示を得て、生きる姿勢を下支えされるかのようだ。
こうした姿勢を、たとえ、崩しがちであっても、なんとか貫こうとすることが出来れば、きっと独自の色合いを細やかに、けれども、鮮やかに放つ〈華〉のある人生が〈今、置かれたところ〉の延長線上のどこかで見つかるに違いない。
★『欠けている一片』2012年11月8日(木)
このところ〈終活〉とか〈老活〉という言葉が流行語のようになっている。今や四人に一人が六十五歳以上の高齢者という超高齢化社会になった日本の現状に因んだ現象の一つだろう。
〈終活〉は人生の最後を自分らしく締め括るために自らの手で葬式の手配を整え、飾る遺影を撮影したり気に入った写真を選び、遺言状をしたためたりする。〈老活〉は現役を離れてから長期化するシニアライフを満喫するために自分らしい内実性のある過ごし方を積極的にする。両者とも自分自身と人生を直視して自分が生きた意味を問い、自分なりに得た結論を〈形〉にしようとする。それらは、個としての生き様というかその人独自の精髄をダイジェストしてさえいる側面がある。言わば、自らの自己像を得心がいくように仕上げる大詰め段階での活動である。
「過去に色々してきたことが受容できずトラウマになっています。そのため、経済的には安定していますが、悠々自適の老後とは参りません。なんとか心を整理して落ち着いた老後の人生を送りたいと思っています。」
A氏(66歳)は昨年三十余年勤めた会社を退職された。二人の子どもたちはそれぞれ独立して夫婦だけの毎日である。健康にも資産にも恵まれておられるが、「あの頃の自分は何だったのかと思えてなりません…心に負担になっています」と来談された。
A氏のトラウマになっている「あの頃」とは、大学院時代のことである。楽しい大学生活を送ったA氏は研究者を志して大学院に進学し修士課程を経て博士課程に進んだ。そこで指導教授と学問的に意見が合わず、関係もぎくしゃくして研究室に居辛くなり、中退した。四六時中誰かに責められている感じが昂じて精神的に追いつめられ、自分から希望して大学病院の精神科に入院した。短期間の入院と退院を二、三回繰返し、その過程で結婚して一年の妻と離婚した。その後、精神の危うい均衡に揺れながらなんとか危機的状況を脱し、「このままずっと何もしないでいるわけにもいかない。とにかく人格の破滅だけは避けたい。食っていくために働かなければいけない」と自らを諌めて三十四歳の時に父親が経営する会社で働き始めた。再婚して娘と息子に恵まれ、社長が父親から兄に代わってからも役員として無事に勤め上げ、六十五歳で退職した。
「今までずっと生きてきて、滅茶苦茶な人生と言ってよろしいと思う。私としてはPh.Dを取って研究者としてやっていきたかった。親父の会社に入りはしたが、敗北感が強い。仕事はきちんとこなして部下にも信頼されたが、自分をどう評価していいか分からない。いつも心の奥底に違和感というか…自信喪失状態にある。最も大切なものが欠けている感じで焦りと不安が強い。」
「今から考えても、自分の歴史学に対する認識は間違っていなかったと思う。けれども、当時は指導教授との感情的軋轢や研究室の雰囲気に耐えられない弱さが自分にあった。皆と対立した自分の考えを保証する意味でも何か仕事を残さなきゃと思ってる。後十年位研究に時間を費やして残せる仕事をしたい。仕事しなきゃという焦りと自信のない自分を抱えている。年齢的な限界も能力の限界もあるけれども、私としては、そういうとこに生き甲斐を見出すことにしか私の老後はないと感じる。」
「もう引退したし、これからは自分の世界に入っていたい。ずっと欠けていた一片を完全には埋められないにしても、その努力をしていきたい」
A氏はこれまでを振り返って「滅茶苦茶な人生」と言われる。A氏には、父親の会社であるにしても、長年そこで五百人の従業員がいる組織の管理職として役割を充分に担ってきた実績よりも自分が志した道を歩めなかった挫折感の方が強く感じられている。そのために、「自分は何であるのか」を問い続けずにはいられなかった。けれども、漸くA氏はその問いに対する納得できる答えが〈研究する自分〉であることを見出し、今後は思う存分研究に従事して行こうとされている。
自分が内面で覚える自己像とそれに伴う情緒や感覚が心の安定を左右する。そして、自分が自分自身の意を汲み、本当にしたいことに携わることで〈欠けている一片〉を自らの手で埋めようとする。そこにこそ生き甲斐があると予感される明るい見通し。〈老活〉を通して自らの人生に決着をつけ、自分なりに肯定できる自己を確立した充足感で深く満たされる歓び。
A氏がこれから向かう方向にどっしりした台座の上に立つA氏の堂々とした像が彼自身で据えられる日が見晴らせるかのようである。
★『今話している相手は誰?』2012年10月2日(火)
芳江さん(47歳)は、心を許してプライベートなことを相談できる中学時代からの友人である節子さんをとても頼りにしていた。けれども、心にずっと引っ掛かっていることが一つあった。芳江さんは、これからもお互いに大切な友人として付き合い続けていくために、心の奥底に蟠っていたしこりを解消させてすっきりしたいと願い、思い切って節子さんに積年の想いをぶつけてみることにした。
「もう三十年近く前のことになるけれど、今でも自分の中でどうしてなのだろうとあれこれ考えて堂々巡りしていることがあって苦しいから、一度あなたの口から聞いておきたいと思ったの。私は自分があなたの結婚式に呼ばれないなんて思ってもみなかった。私からすれば、当時私よりも親しくなかったサチと佳奈は呼ばれているのに…どうしてなの?」
芳江さんと節子さんは中学を卒業後、同じ高校に進学して部活も同じで仲良しだった。高校を卒業後、芳江さんは専門学校に進み、節子さんは就職した。節子さんはその勤め先で知り合った男性と2年後に結婚した。
「高校を卒業した後、あなたは地元を離れて余り会わなくなったけど、サチも佳奈も実家から短大に通っていて結構頻繁に連絡を取り合っていたし、よく一緒に映画に行ったり食事したりしていた。当時の私の気持ちの中では、あなたは少し遠い人になっていたからじゃないかしら…それに、呼べる友達の数も限られていたし…」
芳江さんはその節子さんの説明で納得した。長年引っ掛かっていたことを直接本人に言えて、真正面から応えが返ってきたことで気持ちが軽くなり、自分の結婚式に節子さんを招待したのは良かったと改めて思うことができた。
しかし、数日後、節子さんから電話がかかってきて言われた言葉に引っ掛かってしまった。
「この前あなたと話した後、なんで今頃になって昔のことを持ち出してきたのか、すごく嫌な気持ちになった。だけど、あなたはアダルト・チルドレンぽいとこがあるから、本当はお母さんに言いたかった長年の恨みをお母さんに言う代りに言い易い私に言ったのだと思ったの。そしたら合点がいった。私にとったら、とんだとばっちりだけど、これまであなたからさんざん話を聞いてきてるから、ま、そういうことも有り得ると分かるから気にしないことにするわ。それから、あなたが少し前に話していた浪江ちゃんのことだけど、浪江ちゃんが仕事辞めたいとか言ってたり肩に入れ墨を彫ったりしてるのをすごく怒っていたけど、それだってアダルト・チルドレンのあなたが自分の思い通りにならない憤りをぶつけ易い浪江ちゃんや私にぶつけているのよ。そうじゃなければ、お母さんに褒められたことがないと感じているアダルト・チルドレンのあなたが嘗て自分がお母さんにされたようにしているのよ。とにかく、あなたは自分の母子関係を引き摺って周りを振り回しているのよ。そんなことをしていたら、私が自分勝手で気の強い母に近づかなくなったように、浪江ちゃんだってあなたを離れて行くわよ。本当に気をつけた方がいいわよ。」
芳江さんは、確かに自分が昔のことを引っ張りだしたのは唐突だったと反省する気持ちもあったが、あのやり取りをするのは自分としては已むを得なかったし、結果として良かったと思っている。あくまでも、その話をしたのは、自分が節子さんに対して抱いていた蟠りに因るのであり、節子さんを母親の身代わりにしたと捉えられるのは心外であると同時に的外れに感じられた。また、娘のことを母親として友人である節子さんに真情を零したのに、何故カウンセラーまがいの態度で的外れな解釈をされなければならないのか全く腑に落ちない。
「節子の方こそ自分と浪江を重ね合わせて私を彼女のお母さんに見立ててヒステッリクに言ってきたとしか思えない。彼女自身が自分でも言っていたけれど、アダルト・チルドレンそのものでしょ。もう彼女には何も話したくなくなった。」
芳江さんと節子さんの〈今、ここ〉での友人同士の話がいつのまにかアダルト・チルドレンと幼少期の母親との話に摩り替えられている。
いったい〈今、ここ〉で話しているのは、誰と誰なのか。〈私〉の話し相手は誰なのか。
確かに、〈今、ここ〉にいる〈私〉の心の深層には、自分でも知らないうちに刻印された対人関係のパターンがある。そのパターンは、〈私〉がこの世で初めて密接に接した相手である母親との関係性が基になっている。とはいえ、〈今、ここ〉に一緒に居合わせて話している当人同士の会話に身を入れずに〈今、ここ〉に居ない人との会話に気を取られてしまうならば、話は混線するばかりであるし、話をする者同士の関係も徒にこじれるばかりである。
とりあえず、〈今、ここ〉では、〈私〉は目の前にいる〈あなた〉と話しているという現状認識が大切である。
★『包丁が自傷行為の代償?』2012年9月4日(火)
泰子さん(42歳)は、四六時中包丁を手放せない。身近に包丁があると心が安まるので、自分の部屋にいる時や寝る時は枕の下に包丁をガーゼのタオルに包んで置いているし、パートの仕事に行く時も仕事以外で出かける時も必ず包丁をリュックの底に忍ばせている。それを使ってどうこうするつもりは全く無く、ただ包丁を持っていることで精神的に安定する。
泰子さんにとって包丁を持っていることは、絶えず自分が自分を罰していると同時に罰されている状態にいることになる、とのことである。
「包丁を持っていなければ、自分で自分を処罰せずにはいられなくなる衝動で実際に自分を傷つけてしまうと思う。お前は碌でなしだ!大飯喰らいの役立たず!性根が腐ってる!死ねっ!次から次に自分を罵倒する言葉が湧いてきて、生きていてはいけない気持ちになる。すごく辛い。だけど、包丁が側にあれば、自分が仕置に耐えている気持ちになって、変だけれども、落ち着くし新聞を読んだりできるようになる。」
泰子さんが包丁を片時も手放せないのは、そうした独特の深い意味があってのことである。そして、そこには、生き地獄のような内面の世界がある。
泰子さんは自分がする事なす事すべてが自分勝手に思えて、そんな我儘な自分が平然と生きているのはとても罰当たりなことだと心得ている。けれども、死ぬだけの意気地もないので、せめて自己処罰に勤しむことで周囲に受け容れて貰える自分であろうとしている。
「自分のことばかり考えるのは止しなさい。お母さんはそんな我儘勝手な子が一番嫌いなのよ。」
「いつも人に喜んで貰えるようにしなさい。それが、結局は自分の為になるのだからね。」
泰子さんは小さい頃からよく母親に言われてきた。だから、泰子さんは母親の期待とは異なる欲求を持ったり母親の意向に反する自己主張をしたりするなど、母親が喜ばないことをして母親を傷つける自分を責めて激しい罪悪感に囚われる。そればかりでなく、母親に嫌われる怖さと悲しみで心を引き裂かれる。
それが、いつしか、母親だけでなく誰に対しても繰り返されるようになり、どこで何をしていてもまるで生きた心地もしない。
「偶にぶち切れて布団を頭から被ってエグエグ泣く。そしたら、いつのまにか疲れて眠ってしまう。布団は柔らかくて温かいから、布団に包まっていれば楽になる。その時だって、枕の下にある包丁が私を罰し続けているから、そうしていても赦される。」
泰子さんにとって、包丁はただの包丁ではない。
常に包丁を身近に置いて置かずにはいられないという強迫行為であっても、そのことが、取り敢えず、泰子さんの身体と日常を安泰に保っている。
包丁を手放さないことは、泰子さんが地獄の沙汰を生き抜くために編み出した奇想天外な代償行為であるとはいえ、極めて有効な“救命”手段でもある。
★『いじめ』2012年8月8日(水)
何故、いじめが跡を絶たないのだろうか?
いじめは、なによりも先ず、いじめる人ありき。
いじめる人がいなければ、いじめは起きない。いじめる人は、それによって何を得るのだろうか?
いじめでやっていることは、強要・脅迫・暴行・傷害。そして、たとえ自分が直接手を下していないにしても、殺人。
いじめは、美輪明宏氏(歌手)の言葉を借りれば、歴とした「犯罪」である。美輪氏は、「実態をちゃんと表すために”いじめ”ではなく”犯罪”という言葉を使うべき」と提言し、いじめを黙認する人は、犯罪の共犯者だと糾弾される。確かに、その通りである。
最近、マスコミで話題になったいくつかのいじめでも、最も有効な解決策の一つは、いじめられた側がいじめた側を刑事告発することだった。いじめが学校で起きても、現場の教師たちは黙認するか、いじめた子たちを一、二度注意するだけの手ぬるい対応しか取らなかったり、いじめられた子に「お前にもいじめられるだけの理由があるんじゃないか」と生半可な両成敗で決着させたりする。たとえば、いじめで腕に二十二回の根性焼きをされた仙台市の高校二年生の男子は警察に傷害容疑などで被害届を出したことで漸くいじめの実態調査が始められるようになったが、学校側は、当初彼が友だちがいなくなるのが怖くて「やられた」と言えずに「自分でやった」と言ったのを真に受けて、その後彼から真相を打ち明けられた母親が担任に事情を話したにも拘らず、退学を促していた。教師や教育委員会なども不適切な対応が目立ち、自分たちの責任を逃れようとする姿勢が際立っている。
いじめられた子が勇気を奮って大人に打ち明けても、全く力になって貰えないばかりか「いじめられることに自分でも何か心当たりがあるんじゃないか」と逆に反省を促されたりすれば、その子は更なる苦痛と不信感を募らせるしかない。そして、学校という逃げ場のない環境で日常的な人間関係の中で繰り返されるいじめによって、どんどん追いつめられて行く。
滋賀県大津市や茨城県取手市で中学二年生の男子が自宅マンションから飛び降り自殺したのは、いじめが原因だとされている。どれほど苦しんだ挙句の決断だったことか。これから楽しいことが必ずいくつかは待ち受けている人生が突然断たれてしまった。本当に取り返しがつかない。親にすれば、この事実を到底受け入れ切れない。余りにも無慚である。
心身共に成長していく過程にある子どもたちにとって、いじめは、自分がどのような立場?いじめる立場・いじめられる立場・いじめを見ている立場?で関わっていようとも、抜き差しならない影響を受ける。そのいじめが生命をも奪う事態にまでは到らない場合であっても、いじめを体験したことが、普段は特に意識しないで過ごしていても、ふとした瞬間に意識を過ぎり、当面の生き方だけでなく後年の人生にも作用を及ぼされかねない。
もし、いじめが自分の切羽詰った問題になったら、どうすればいいだろうか?
朝日新聞で連載中の記事から印象的だった著名人たちの、いじめを巡るいくつかの言葉を記しておこう。
「あなたがやってることは正しい?…一回だけの人生がこれから面白くなるって時に、つまらないいじめなんてやってる場合じゃないのよ。」(マルシア歌手)
「そんなくだらん世界からは”全力で逃げろ”。いじめられてる子はもちろん、付き合いでいじめてる君も。…散り散りに逃げて、生き延びるんや。」(井筒和幸映画監督)
「大好きで夢中になれる”何か”を見つけてほしい。それはきっと海に投げ出された時にしがみつけるブイのように、つらい現実で溺れそうな自分を救ってくれる。…つらい状況に追い込まれる前に夢中になれるものを見つけて、自分の心を豊かに強く保ってほしい。」(辻村深月作家)
★『神様、私を赦して下さるのですね』2012年7月6日(金)
「世の中は意地悪だ。」
「世間の人は、いつも私の粗を探していて、見つけると直ちに罰してくる。」
「そんなのじゃダメ。こうしなさい。」
早苗さん(54歳)は自分に価値があるとどうしても思えない。だからこそ、学歴とか社会的地位とか人に認めて貰い易い価値を求めて手に入れてきた。それでも、「そこがダメ」と自分を糾弾する鋭い声が絶えず心の中で飛んでくる。片時も気持ちが安まることがない。職場で仕事をしていれば、「お前は大して役に立っていない。給料泥棒!」と後ろ指をさされているように感じ、子どもの弁当を作れば、「他のお母さん達はもっと愛情の籠ったお弁当を持たせているよ」と責められている気がしてくる。いつどこで何をしていても、針の筵を強いられる。逃れたくても、逃れようがない。
「どうして人は“この人いいな”と思うのか…自分がどうすれば人によく思って貰えるのかが分からない。」
「私は基本的に人がこういうものを求めていると思うと、それに染まるべきだと思っている。」
数年前位から早苗さんはそうした自分の基本姿勢が母親によって刷り込まれたと思い始めた。小さい頃、「あんたのこういうところがダメ。お母さんだから言ってあげるのよ。他の人はみんな嗤っていても面と向かっては何も言わないものよ」と母親から四六時中シャワーのように浴びせられていた。
〈お母さんだけが私のことを心から心配して言ってくれる。〉
〈お母さん、助けて。私はどうしたらいいの?〉
母の導きに沿って、早苗さんは名門の小学校、中学校、高校、大学と成功体験を重ね、自分が本当はどんなことが好きか、何をどうしたいかなどは意に介する必要もないくらい日々の生活に順応していた。大学生の時には一年間アメリカに留学する機会にも恵まれた。ホスト・ファミリーとの生活で、「早苗はどうしたいの?何が好き?」と訊かれることが多く、当初はこれまでの習い性で相手が期待していると思うことを言ったりしていたが、そのうちに〈私〉という主語と動詞を明確に意識するようになった。自分の好みや意向を表出しても、「そんなのはダメ」と否定されずに「OK」とごく自然に受け容れられる体験を重ねた。心地良かった。
〈私はこれでいい〉と感じることができた。アメリカが大好きになった。世の中は意地悪ではない。というか、意地悪でない世の中もある。少なくとも、お母さんの言う通りにしなくても自分だけでうまくいくことがある。
けれども、帰国後、再び粗探しをする〈目〉に曝された。
〈それではダメ。ほら、ここが…そこも…〉
元の木阿弥になってしまった。自分が如何にダメかばかりが強調されて感じられる。
〈私はどうせダメ。この点でもあの人に負けている。私の努力が足りない。怠けて豚のように太って、肌もカサカサ。私が苦しいのは、自分の至らなさに対する罰。母も世の中の人も皆、私を罰する人。私は罰されて当然。だって、私はこんなに行き届かないのですもの…ごめんなさい、と心から言うと、僅かに私が存在しても良いスペースが生まれる。だけど、少しでも“私は”と主張すると、“何を偉そうに”と一蹴される。〉
根深い自己否定感に苛まれる早苗さんであるが、心の片隅に留学時代に実感した快い自己感覚の余韻が残っている。懸命にそれに意識を集中させて増幅させる。もう好い加減に心の中に居座る母の声に耳を塞ぐべきだ。母から離れよう。離れられない。老いていく母が可哀想。凄まじい葛藤。
そうした最中、最近、早苗さんはフィンランド人女性の宣教師に出会った。
「神様は、過去を掘り起こして、お前は、あの時、あんなことをしたのだから罰してやるとはおっしゃいません。神様が望んでいらっしゃらない人間になっていると、あなたは自分を責めるけれども、神様は既にあなたを赦していらっしゃるのですよ。神様に赦されているご自分を感じなさい。」
早苗さんは、必ずしも特定の宗教の神というのではなく、なにか大いなる力、人知の及ばないスピリチュアルな存在によって自分が赦されているのを感じた。すると、これまで自分なりに勉強し、仕事をし、結婚して子育てをし、子どもも無事に成長していることなどが嘗てとは異なる様相を呈して思い描かれてきた。
〈私なりに精一杯頑張って生きてきたんだ。〉
〈私は、これで良かったんじゃないか。〉
〈これからも、私はこれでいいんだ、としっかり思って生きたい。〉
早苗さんは、大いなる霊的な存在に対して深く頭を垂れて心の中でそっと呟く。
〈神様、私を赦して下さるのですね。〉
★『栄転で暗転?』2012年6月4日(月)
松田氏(37歳)は大学卒業と同時に大手銀行に就職し、これまで4つの支店で営業を担当してきた。仕事はノルマなどのプレッシャーはあったが、お客様のニーズを聴いて商品を紹介したり、マネージャーの立場で数人の部下を束ねて助言したりするなど、結果が目に見えて現われて面白かったし遣り甲斐があった。
そして、昨年末、本社に異動になった。栄転だった。これまでの自分の仕事ぶりが認められたのだと嬉しかったし、妻も喜んでくれた。待望の子どもが生まれたばかりの時期でもあり、来る年は良い年になりそうだ、と全身にエネルギーが充満し、意欲が湧いた。嘗て味わったことがない、非常に濃密で凛然とした感覚が鮮やかに意識され、自分の内面に一本の上質で堅固な柱が据えられたかのようだった。これ以上は望むべくもない幸福感に浸された。
年が改まり、本部での毎日が始まった。これまでと仕事ががらりと変わった。人事育成に携わることになった。人事育成のツールを企画・実施するのが主な業務であり、上司からはこれまでずっと営業畑にいた経験を活かして先ずは新卒採用された若手の営業職を対象にした研修の企画と運営を任された。確かに支店に居た時は、さまざまな個性を持つ部下たちを指導し、顧客との間でトラブルが生じたりした時などは自分から進んで相談に乗るようにもしてきて、営業職向きの性格特性や逆に営業に不向きな人の特徴などを自分なりに把握して個々の場面での対応法や促進するべきスキルや改善すべき事柄などをメモしたりもしてきた。そうした自分なりに蓄積してきた知見やアイデアを参考にして、研修企画を立てようと意気込みはするが、全く何も考えが浮かんでこない。自分でも不思議に感じるくらい発想が出てこない。研修の実施日が刻々と迫ってくるが、出だしで躓いて、仕事がまるで進捗しない。
「周りの人たちがすごく出来ているように見えて、自分が付いていけている感じがしない。まだ何も表立った問題は起きていないけど、自分が一向に出来ている感じがしないのが辛い。」
「支店では、小さなことであっても、いつも何かしら成果が見えていたんですよ。それが、本部に来てからは、全く成果物が出せない。自分が成長できている実感がない。こんなに能力的に…物分りが悪い人間だったのか…何をやっても出来ない…昔は出来てると思い込んでいただけで、あの時も本当は出来ていなかったのか…」
松田氏の自信がどんどん崩されていく。ここ最近は、「自分はフロアで一番出来ない奴だと自覚している」。
「とにかく今いる場所から逃げ出したい。もうちょっと自分が役に立てるとこに行きたい。ここでやっていける気がしない。」
松田氏は、支店での仕事と本部での仕事の違いについて、「今までは単純にやることで良かった。ところが、今は自分の考えを深く多面的に巡らせて具体的な形に仕上げなければならない。部課長クラスの人たちにも、こういうふうに指導して下さい、と発信しなければならない。間違った発信はできない」。
松田氏は、生来、じっくり考えるよりも行動派であり、企画よりも実動の仕事が向いている。そのため、異動によって適合不良に陥ってしまった。加えて、〈出来る自分〉に強く拘泥して性急に成果を求めるきらいがあり、異動してきてまだ5ヶ月とは思えず、もう5ヵ月と思い、以前からその業務に携わってきている人たちと比較して、これまで恙無く頑張ってきた実績までも否定しがちになっている。
うつが次第に靴音を大きくしながら近づいてくる。
栄転で暗転?
それとも、異動直後の適応試練を通過して、自己育成にも携わっていけるのか。まさしく松田氏の手腕というか生き様が問われている。
★『こんなことが…』2012年5月2日(火)
まさか、と思うことが起こるのが、むしろ、日常茶飯事でありさえする。このゴールデンウィーク中にも楽しい気分で出掛けた筈のツアー旅行が一転関越自動車道での大惨事になり、7人が死亡し39人が重軽傷を負った。山梨県では近所の人と立ち話をしていた女性が飼主と散歩中に首輪が抜けた土佐犬に突然襲われて死亡した。奄美大島でヨットレースに参加していた男性が海に落ちて死亡した。当事者もその家族もまさかそうしたことが自分の身に起こるなどとは全く思ってもみなかっただろう。
一寸先は闇。不意に日常生活に亀裂が走るように、先刻までの状態がいきなり不連続になって全く見知らない惨憺たる渦中に投げ込まれている。その、取り付く島もない圧倒的なリアリティ。
K氏(53歳)は、先日、妻が難病に罹っていると医者に告げられた。まさに青天の霹靂だった。想像すらしたこともない。まるで現実だとは思えない。K氏はセカンド・オピニオン、サード・オピニオンを求めてインターネットで検索した然るべき病院に妻を受診させたが、どこでも同じ内容のことを告げられた。完治に到る薬もこれといった治療法もなく、回復は見込めない。症状の進行速度には個人差があるが、一般的には進行は遅い。しかし、徐々に運動失調症状が顕著になり、歩行や話したりすることが困難になると聞かされた。その直後から肩と胸に凄まじい力がかかってギュッと締め付けられる感じがしたり、首根っこをガシッと掴まれている感じがして身動きがしにくい感覚に捉えられた。実際には支障なく動けるのだが、身体が硬くなって動けなくなりそうで外に出るのが怖い。かといって家でじっともしていられない。一体どうすればいいのか、途方に暮れる一方で不安がどんどん膨れ上がってくる。
最初に妻を受診させる2、3日前、妻が「なんだか歩くとふらつくわ」と言ったが、その時は「疲れているんだろう」とK氏は軽く流した。妻が再度同じことを言った時も「更年期障害が出たんじゃないのか」とからかったが、「ま、一度医者に行っとけばいいよ」と安易な気持ちで受診を促した結果、突拍子もない事態に陥った。K氏はすっかり動顛してしまった。
「これから一体どうなるんだろう。」
今、妻は家の中では一人で歩けるが、外出する時には車椅子を必要とするようになった。K氏は、自分の想いを安心して話せる場をカウンセリングに求めて少し落ち着かれ、現実に対処していこうと懸命に生活スタイルを改変しようとされている。
★『応答するパチンコ』2012年4月6日(金)
「パチンコ依存だなんて安易に言って貰いたくない。私にとっては、一人で淋しくて堪らない時に心行くまで慰めてくれる唯一の相手なのだから…」
いつ子さん(38歳)は毎日帰宅が深夜になる夫との生活に空しさを感じていた。彼女は、小学校低学年の息子を育てながらパートで平日5時間働いている。育児も家事も仕事も苦ではないが、楽しいことも心を潤わせてくれるものもなく、ただ今しなければならないことを順々にこなしていくだけのモノトーンな日常性の中で索漠たる気持ちに蝕まれていた。子どもが9時に床に就いた後、身体は疲れているのに目が冴えて寝付くことができない。自分に向けられる眼差しも声も気遣いも何もない。テレビの音はうるさいだけだ。無性に他愛もない会話を交わしたい想いに駆られる。だからといって実家や友人に電話をする気にはならない。一つ屋根の下で一緒に暮らしてはいるけれども、夫は遠い人に感じられる。休日に彼が家にいても、殆ど寝ているかパソコンでゲームに興じているかでいつ子さんに無頓着な様子である。いつ子さんが話しかけても短く応えれば良い方で会話が続かない。用事以外のことで彼から話しかけてくることはないに等しい。いつ子さんは一人で居る時も夫と一緒に居る時も心を鋭く抉ってくる激痛で叫び声を上げるが、深く内攻する声は誰の耳にも届かない。いたたまれなくて、いつ子さんはパチンコ店に向かう。そんなふうにしているうちに、お金がどんどん消えていく。偶に稼げる時があるが、大半は瞬く間に摩ってしまう。預金にも手をつけ始めていて、もう止めようと何度も思うが止められない。
「私はただ私に関わってくれる相手が欲しいだけ。私に関心を持って、私のことを分かってくれる人、私のすることや気持ちに反応してくれる人が一人でも居てくれさえしたら…」
いつ子さんの目から涙が溢れて次から次に流れ落ちる。
「パチンコで当たると、私のことを分かってくれた。心が通じた感じになって、気持ちがすごく浮き立って晴れやかな気分になる。それだけで充分なのに、時々大当たりして、思いがけないご褒美をくれる。私の心からの欲求にパチンコだけが応えてくれる。パチンコだけが私に歓びを与えてくれるから…」
いつ子さんだけでなく、誰もが自分を受け容れて親身に応答してくれる他者を求めている。それなのに、情緒的に擦れ違ってしまうことの方が多くて遣り切れない。
情緒的に応答してくれる他者を求める切実な気持ち。心に響き合う関係への憧れ。他者に対する自らの応答性についても心を砕くことがあれば、日常性が今よりも少しはカラフルになるだろうか?
★『自己像の波紋』2012年3月5日(月)
大手電気機器メーカーに勤めて約20年の吉崎守さん(43歳)は、現在、休職して8ヶ月になる。1年半前に同じ技術部の別の課に異動になり、仕事量も部下の人数も増えた。技術部での異動は異例なことであり、殆どの人がずっと同じチームで業務に従事するが、守さんが所属していた課自体が整理されたための処遇だった。
守さんはこれまでの実績を買われて異動先の課内でいくつかあるグループの一つのリーダーを任された。その仕事の分野は守さんの専門領域の一部であり、彼は非常に強い関心と可能性を感じて張り切っていた。しかし、彼が着任する以前から継続されているプロジェクトの細部や個々の具体的な内容や経過などをうまく把握し切れないもどかしさに苛立ってもいた。当初はグループメンバーの人たちに説明を求めたり訊いたりもしていたが、そうすることに抵抗も覚え始めていた。次第に、集中力がなくなり、色々のことを忘れてしまうようになった。それは一度訊いたことなのか、その日何をしたのか、必要だったメールをしたのかどうかさえ思い出せなくなり、不意に大声で叫びたい衝動に駆られる。自分の席に坐っていても落ち着かないし息苦しい。
「そんなこともまだ分からないのですか?」
「もう何回か説明しましたよ。いい加減にして下さい。」
そんなふうに言われそうな気がして、守さんはスタッフに訊きたいことがあっても訊けないことが多くなってきた。頭では自分はずっとここで仕事をしてきた彼らとは違うのだから必要に応じてこれまでの業務内容について尋ねるのは当然だと思う一方、自分がごく初歩的な事柄さえ分かっていないということではないかという疑問が湧いて、自信が根底から覆ってしまう。
「今さらこんなこと訊けない。」
「これは異動云々とは関係なく知っていて当然なのではないか。」
「こんなことも分からない自分が腑甲斐なくて嫌だ。」
「自分は技術者として駄目かもしれない。」
「これから本当に大丈夫だろうか。やっていけるのか?」
どんどん自信が損なわれると同時に、周囲の人たちに対する恐怖感が膨らんでくる。周りから「リーダー失格」だと非難されているように感じるが、守さんはそれが自分の思い過ごしであることも分かっている。実際には支障なく仕事をこなせていたにもかかわらず、守さんは出社するのが辛くなり休職に追い込まれた。
《技術者として駄目な自分》という自己像が守さんの内面から毒矢を放って彼を仕留めてしまったようだ。毒が彼の社会的生命を奪ってしまわないように、どのような解毒剤を処方すればいいのだろうか?
守さんは、異動後自分が思うようにこなせないと感じる事柄ばかりを集めて《技術者として駄目な自分》という特徴的な自己像を作り上げ、それを吟味する間もなく自らが産み出した像に翻弄されてしまったかのようだ。今一度、それなりに仕事をこなせていた自分など、自分をさまざまな角度から観察し直して改めて自己像を再構成してみるのも良いのではないだろうか?
★『見たくない自分を見ちゃった』2012年2月4日(土)
「4月から新しく始めることにした。自分でさんざん考えて体験入学もして決めたことだし、入学手続きに必要な書類もお金もすべて準備できているのに、どうしてもそこから先に進めない。明日は必ず手続きに行こうと思うけど、朝になると気分が悪くて息苦しくなり、外出するのは到底無理な状態になってしまう。親が心配して代りに手続きしてきてあげると言ってくれるけど、もう子どもでもないし、まだ手続き期限までに猶予があるので、頼まないままでいる。改めて自分が本当にしたいことを自分自身に確かめようとすると、もう気持ちの整理はついているという想いが強まる一方、社会に進出していくことに対する恐怖心が湧き起こって自分をコントロールできなくなるんじゃないかという不安に打ちのめされる。」
恵美子さん(23歳)は、大学の卒業を1年遅らせたので今春卒業する。父親が大学教員、母親が塾講師、兄も大学教員という家庭環境にあり、ずっと教育関係の仕事をしたいと思っていた。入学当初から教員採用試験対策のためのセミナーや講座に通い、障害児のためのキャンプでボランティア活動をし、新聞や情報誌などを通して教育現場の様子や課題に関心を向けてきた。そして、満を持する思いで大学4年の時に教員採用試験を受けたが、不合格だった。その直後から気分が非常に落ち込んで何もする気がなくなり、卒業後の進路が絶たれてしまった気持ちで留年した。もう一度教員採用試験を受ける気持ちになれないまま暗澹として毎日を過ごしながら、うつ状態で何もできない自分に苛立ちを募らせるが、その悶々とする苦悩の持って行き場がない。
「ある日、ふと思い立って庭に出た時、冬の厳寒の真っ只中で生きている木を見て涙が出た。全く思ってもみないことだったので自分でもびっくりしたけど、状況が悪い中でも生きている姿に感動した。私もそんなふうに在りたい、と励まされた。」
恵美子さんがそもそも教師になりたいと思ったのは、人のためになる仕事をしたい、一人ひとりの在り方や生き方を前向きにさせたり促進させてあげたりする仕事に就きたいという思いからだった。木を見た時、教師という職業に拘らなくても自分の夢を叶えられると思った。木を見て感動する時、言葉などは不要で気持ちに直接触れてくる。言葉以前の段階で立ち上がる気持ちにさせるのは自然ではないか。身近に植物があることによって心が救われて前向きになる。園芸とか造園は魅力的な仕事だと思った。自分の中でやっと教師との見切りがついた。まだ未練はあるけれども解放感が広がった。ガーデンデザインの専門学校に行こうと決断した。
自分の気持ちを正直に汲んで決断したにも拘らず、何故行動しようとすると身体が動かなくなるのか。そればかりでなく、勝手に涙が溢れてくるのは何故なのだろうか。美恵子さんは、その謎を解かなければ、自分がさらに深く傷ついていくような気がして内面を探究せずにはいられなくなった。
「試験に落ちてうつになって何もできなくなった時、苛立ちだけでなく、もう人間として生きている資格も価値もないと思った。今までずっと順調で、それは自分で努力してきたからだという自負があった。でも本当は親とか友達に支えられていた。人のためになりたいというのも、すごく上から目線で言っていて、私が導いてあげるという感じ。人を社会的地位で見るとこがあって恰好をつけたがる。見栄っぱりだし、できる自分、強い自分を見せたい。悲しいと思ったり、できないと言って諦めてしまう自分は弱い。そんな自分は見たくないし見せたくない。なのに、そんな自分がいきなり現われた。」
「初めて挫折して、何もできなくなるくらい辛い気持ちがあるのに気づいた。社会的地位がなくても懸命に生きている姿が大切だという価値観に変わってきた。見たくない自分を見ちゃった。今、外に出るのが怖い。どう恰好をつけたらいいか分からない。私が社会に出て行くのを促すような気分と身体になりたい。」
美恵子さんは、頭では尤もらしい理屈をつけて専門学校に行くことを納得しているが、気持ちは教師になることに対する未練に引きずられている。薄々気づいてはいるものの、再受験してまた不合格になって傷つくのを未然に防衛している。けれども、「感性までも理性で変えちゃおうとしている」と言う恵美子さんは、見たくない自分を見ることができている。その先を、これから彼女はどのように進めていくだろうか?
★『再び、新しい年』2012年1月6日(金)
年が明けた。幸運と強烈なパワーの象徴とされる辰年、自在に願いを叶えることができるというドラゴンボールを追いかけて天翔る龍のように力強く希望に向かって昇り続けていけるだろうか。
震災後の復興を目指す槌の音が被災地だけでなく日本のあちらこちらで響いている。全く思いも寄らない震災と原発事故の爪痕が未だに生々しく、瓦礫の山々を見聞するだけでも途方に暮れるばかりだが、今も今後も現在進行形であり続ける放射能汚染に対しては絶望と不安の向こうに浮び上るべき希望の形さえ見えない粒子に塞がれて見えてこない。
私たちの身の上には、震災などに限らず、思いがけないことが吉凶いろいろ取り混ぜて起こり得る。どのような場合であっても、何万年も昔にいったん放たれた時間の矢は、決して止まることなく、ひたすら一直線に進み続ける。ましてや決して逆行することはない。ただ前にだけ向かって常に同じ速度で進行する。時間は無慈悲である。いかなる斟酌も猶予も融通も全く取り沙汰されない。時間はあらゆる出来事を貫通しながら坦々と前進するのみである。けれども、そうした時間の経過そのものが癒しになったり、最善の解決策になったりもする。また、時間を経ることで失われてしまわない実のある大切なものに気づかされたりもする。時間の審判とでも言うか、特に人と人との関係性において理性とか取り繕いの及ばない精髄を見極めさせる。
時間の矢は、一瞬にして《今、ここ》を通過して延々と明日に向かって突き進んでいく。新年が明け、また、新年が明け、そしてまた、新年が明ける。その過程で数々の生命体の寿命が尽き、新たな命が生れる。マクロ・コスモスでもミクロ・コスモスでも、そこを通過する時間の矢はただ一本である。
ミクロ・コスモスで暮らしを営む私たちにとって、それでも、暦に刻まれる2012年という新しい年の到来は、心機一転の機会であり、恰好の節目になる。社会情勢に鑑みて《復興元年》として位置づけることでさまざまな共同体が新たな創造を志し、個人的にも一年を振り返って自分自身を見つめ直したり、これまでの生き方を改めたり、何か新しいことを始めたり、あることを吹っ切ったりする切っ掛けになる。
願わくは、この辰の年、是が非でも運気が全般的に龍(隆)盛を極めますように。
★『冠が好き』2011年12月8日(木)
どういう人であれば、周囲から評価されるだろうか。学校では、スポーツが得意で勉強ができる奴。職場では、タフで仕事ができる人。三谷智彦さん(32歳)は、常に《できる人》に思われるように意識して行動してきた。その証として《冠》に憧れた。誰でも知っている学校とか企業を目指して頑張り、それを全うすることで《すごい自分》を作り上げてきた。
第一志望だった大学で学生生活を送り、誰もが知っている会社の子会社に内定した時、子会社であっても、誰でも知っている会社の名前が冠に付いているので満足した。友人達の中にはなかなか内定を貰えない人や企業名が全く知られていない中小企業に決まった人たちがいたが、それらの仲間達に比べて《優秀な自分》を実証できた気持ちで非常に満たされていた。入社後4,5年は、同期の誰よりも先んじて主任の冠を得ようと張り切り、冠にふさわしいのはどういう人間なのかを余念なく研究し、「上からのリクエストは百パーセントこなそう。百パーセントの成果を上げて、上司に認められたい。重要な仕事を任されていくことで周囲にできる自分を見せたい」と一心に業務に携わった。けれども、成果を上げようと懸命になるほど、思い通りに進んでいかない。苛々が昂じると同時に、目先の仕事に取り掛かろうとすると、〈うまくいかなかったらどうしよう〉という不安が意識を過ぎるようになり、その不安が次第に膨れ上がってきた。それでも、仕事の手順をあれこれ思い描いて、とにかく早くやってしまおうと気持ちを持ち直すが、身体が動かない。全身が重くなって金縛りにあったように身体の自由がきかなくなり、すべてを投げ出してしまいたいという強い衝動が身体の奥底から湧き起ってくる。差障りのない理由を言って有給の範囲で時折会社を休むことで、なんとかやり過ごしていた時に異動になった。智彦さんは、社内的に評価の低い部署に異動になったと感じて益々働く意欲を失くしてしまった。医師のうつ病という診断書を会社に提出して休職し、転職を志した。運よく休職期間が終わる3ヶ月後に冠のある会社から内定を貰うことができ、その達成感で再び全身に生気が漲るのを感じた。上司に退職を申し出て、約1ヶ月後に再就職した。
転職した当初、智彦さんは非常に幸福だった。今度の会社は、冠のある企業の子会社ではなく、正真正銘の冠を戴く大手企業だった。智彦さんは、上司の期待に百パーセント応えようと仕事に全力投球した。その甲斐があって上司に一目置かれるようになったが、その分上司からのリクエストが多くなった。自分は上司に気に入られているという自負に支えられて、智彦さんは上司に言われたことは完璧にこなしたいという拘りに駆られた。すべてが自分の意図した通りにカチッとうまく嵌って進むことが快感だった。上司はそこまでは求めていないと分かっているが、自分の中で勝手に完全な状態を定めて、それに見合わなければ気が済まない。カチッ、カチッ、カチッ。その快感に囚われているうちに、次第に仕事が回らなくなってきた。智彦さんの意識の中で「自分は優秀だ」という想いと「自分は駄目だ」という想いがめまぐるしく反転し、そのバランスがうまく取れない。上司に些細な指摘をされるだけで身が竦み、無力感に襲われて自分は生きる価値がないとさえ思ってしまう。「もう大きい仕事をするのは自分には無理ではないか」、「上司は自分のことを期待外れに思ってないか」、「死んでしまおう」などといった自分を否定してしまうような辛い感情が次から次に起ってくる。智彦さんは、再びうつの波に浚われて来談された。
「人並に見られたり、軽く見られるのが、いや。なによりも、自分の中で駄目だなあという気がする。」
「冠があると安心する。だけど、今は冠に潰されかけている。冠が似合っている人が羨ましい。自分がどういう状態になれば、冠にふさわしい人間になれるのか教えてほしい。」
「これまで人の前で素の自分を出したことがない。根っこに自分で自分が嫌い、憎しみに近い感情がある。だから、上司に咎められたら、自分は駄目な奴という思考になって、自分で自分を追いつめた。冠を付けたら、ちょっとましな自分になって、自分を好きになるんじゃないかと思っていた。でも、どんな時でも、自分のベスト・フレンドは自分であるべきなんですよね?自分だけは自分の味方でいてあげようと心の底で思えるようになりたい。そうなれば、上司の期待に沿わなくても、自分は一生懸命に頑張ったのだからいいよと自分に言ってあげられる。楽になれる気がする。」
智彦さんは、これまで人前で素の自分を出さなかっただけでなく、自分に対しても素の自分の想いをとことん出させなかったことに思い到った。そして、素の自分を無視して《できる人》を強要していたことに気づき、今は落ち込む素の自分の期待にこそ寄り添いたいと思い始めている。
★『あーぁっ! わぁーっ! ぎゃーっ!』 2011年11月2日(水)
気がついたら叫んでいた。
「あーぁっ!」
「わぁーっ!」
「ぎゃーっ!」
なんとも索漠としていて気が滅入る。辛うじて職場では叫びそうになるのを煙草を吸ったりすることで抑えていられるので、恐らく周囲の人は誰も自分が内面の戦場で手痛い攻撃を受けて呻いていることに気づいてはいないだろう。というよりも、自分は誰からも顧みられていないという想いに、どれほど傷ついているだろうか。それは、何も今に始まったことではない。これまでずっとどれほど傷ついてきただろうか。最近では、思春期になった息子が返事をしなかっただけで逆上して新聞を投げつけてしまう始末である。
木田正春さん(43歳)は、家庭で独り言を言ったり奇声を発したりすることが多くなり、妻に促されて来談された。
独り言も奇声も自分ひとりでいる時ばかりでなく家族といても各人が別々のことをしている時などに唐突に口を衝いて出る。何をしていても不意に上司に駄目出しをされた場面や仕事を頼まれてもどうすればいいか分からないで動揺している時の感覚や自分が思っていることをうまく言葉に出来ずにもどかしく感じていた情景などが思い浮んで、「俺はバカだな」とか「全然ダメだな」と呟いたり、「あーぁっ!」とか「わぁーっ!」とか「ぎゃーっ!」と叫び声を上げる。
「もういやだ!」という気持ちで一杯になる。その気持ちについて、正春さんは、「仕事も上司もいやだ。なにもかもを投げ出して楽になりたいという気持ちでない。むしろ、楽をしたい自分がいて、そんな自分は駄目だ。馬鹿だなという気持ちで、自分がいやなんだな」と言う。
「いやがられる自分といやがる自分、うまくできない自分とそんな自分を叱咤する自分がいて、それぞれが口々に独り言を言ったり叫んだりしているみたいですね。」
「自分の中が割れているみたいだな。うまく折り合いをつけられない自分が問題のような気がしてきた。今まではっきり意識してはいなかったけれど、心のどこかですごい技術者でいたいという憧れのようなものがあって、それとは程遠い自分を扱いかねていたんだな。」
正春さんは、独り言や奇声の意味とそれらが発せられる文脈を自分なりに解釈された。そして、「今思った」と言って次のようなことを言葉にされた。
「憧れに振り回されてふらふらになって叫んでいたのかな。自分に主導権がなかった。自分の主導権は憧れにも不安にも、周囲の誰にも譲り渡さないで、今話している自分が握るようにできたらいい。」
?★『ダメかも』2011年10月1日(土)
自分が傷つきたくない。そう思うのは、生粋のマゾヒストでない限り、当然である。そのマゾヒストにしても、よくよく話を聴けば、一見自分が損をしたり痛い思いをしたりなどして傷つくような行動をしながら、その屈折した心理の奥底でその人ならではの快感とか利益が得られていることに気づかされる時がある。とはいえ、多くは、自分が傷つかないように、あの手この手の防衛策を意識的にも無自覚のうちにも講じている。しかし、それらがいつも効を奏するとは限らない。ただ傷つかなければいいのか。もしかすれば、その防衛策のお蔭でそのこと自体には傷つかないで済んだとしても、そのことに因って派生する予期していない負の連鎖で身を削ることにもなりかねない。
咲子さん(32歳)は、一年前に知り合った四歳年上の茂さんと一緒に暮らしている。定職に就き安定した収入がある茂さんは穏やかで優しい人柄なので、咲子さんは幼い頃から頻繁な不倫の果てに父親と離婚して家庭を壊した母親に振り回されてきたこれまでの辛い経験が解きほぐされていくかのような安らぎを覚えていた。そのためなのか、これまでぎゅっと抑え込んでいた気持ちが次から次に脹らみを増して浮かんできて、うつ状態になってしまった。派遣の仕事を辞め、何もする気にならないので、食事も洗濯などもすべて茂さんに頼っている。同棲を始めた当初は、いずれ結婚して一緒に生きていこうと二人で話し合っていて、咲子さんはずっと憧れていた〈温かい家庭〉を営む将来に夢を描いていた。今も茂さんはその気持ちが変わらないと言ってくれるが、咲子さんは自分で〈ダメかも〉と思うようにしている。
咲子さんの正直な気持ちは、今すぐにでも茂さんと結婚したいのだが、今の状態では茂さんの両親に会いに行きにくいし、茂さんも急ぐ必要はないと言う。咲子さんの想いの中では、「茂さんのお家はきちんとしていて、彼は長男だし、ご両親にはそれなりの期待があると思う。家庭が複雑で高校中退の嫁なんか厭なんじゃないか。茂さんも本当は今の私を見ていて嫌気がさしている気がする。だから結婚はダメかもと思っていた方がいい。結婚したいと一途に思ってしまったら、そうならなかった時のショックが大きくて、私には耐えられない。でも、ダメかもと思っていれば、本当にダメになっても、ああやっぱりと思って諦められそう」。
咲子さんは、茂さんと結婚したいという希望よりもダメになるかもしれないという不安に染まった憶測の方に意識の焦点を当てている。それは、両親のことなどで淡い期待を持つたびにこっぴどい失望を味わせられてきた記憶が棘になって咲子さんのこころに刺さっていて、その痛みがさらに鋭さを増して拡がるのを防ごうとする、切ないながらも已むに已まれぬ自己防衛の策である。けれども、果たして〈ダメかも〉と思うことに対してどれだけ前向きに頑張る気持ちになれるだろうか?是非ともそうしたい、そうなりたいという希望があるからこそ、私たちはその達成に向けて自分にできる最善の努力をしようとするのではないだろうか?
自分が心底望むことに対して〈ダメかも〉と最初から半分諦めてしまえば、それを実現させようと懸命になる気持ちも意欲も殺がれてしまう。そうすれば、自ずと結果としてダメになる。「このままだときっと愛想を尽かされる」と思っても、今の状態でも出来ることを何か少しでもしようとは、とても思えない。けれども、結婚したいという希望を前提にしていれば、たとえば、体調が優れなくて、どうしても身体を動かす気にはなれないとしても、「こんな私じゃもう好きでなくなるでしょ」とめそめそしたり無理矢理抱きついたりするところを「いろいろ良くしてくれてありがとう」と言ってみるとかすれば、意識の持ち方や在り方が違ってくる。もちろん、そうしたことによって相手が受ける心持にも繊細で光沢のある綾が織り込まれていくに違いない。
自分を傷つきから守ることは大切である。だからこそ、なかなか難しいことではあるけれども、守り方には色々あるので、出来る限り自分の全体像を俯瞰して有効な守り方ができるように工夫していきたいものである。
★『日新、日日新』2011年9月6日(火)
日に新たに、日々に新たなり。中国の古典『大学』に記された言葉で、経営危機に陥った企業(石川島播磨重工業の前身である石川島重工業や東芝)の再建に辣腕を揮い、第4代経団連会長として財界を牽引した土光敏夫氏の座右の銘とのことである。?
どのような心持で毎日を過ごすのか。ただ単調な繰返しに過ぎない日々に埋没して過ごすのか、思うようにならない現状で自棄になるのか、自分の中に火を熾して生きようとするのか。それらは不運とか逆境といった自分を取り囲む状況に因るのではなく、自らの生きる姿勢もしくは志の問題である。気持ちの持ち方や考え方次第で毎日の過ごし方が自ずと変わってくるのは事実だが、誰もが葛藤や不満やすっきりしない感情に呑み込まれないで前向きに進もうとすることができるわけではない。不本意な境遇であっても、より良い明日を目指してとことん力を尽くし続けるには、並々ならない心の芯の強さが必要である。
今日という日は、天地開闢以来、初めて訪れた一日である。それは成功者にも貧しい人にも平等にやってくる。その新しい一日を是が非でも有意義に過ごすことによって自分自身の目標を必ず達成させようとする執念が氏の心を貫いている。
「自分がやるべきことが決まったら、執念を持って押し進める。問題は、能力ではなく、執念の欠如である。」
「一日一日にけじめを付けていく。今日のことは今日やってしまって、先延ばしにしない。昨日を悔むこともしないし、明日を思い煩うこともしない。新たに今日という清浄無垢な日を迎える。そして、今日を精一杯生きようと誓い、全力を傾けて生きるのだ。」
どのようなことであっても、何か意味のあることを成し遂げるには、安易に諦めてしまわない執念が礎になる。執念を持つとは、自分で自分の中に火種を見つけ、自分で火を点けて、その火を燃やし続けることである。なかなか成果が出なくても、認められることがままならなくても、ひたすら執念を燃やして精一杯力を揮うことができるかどうか。
芯が通った人の生き様は、私たちに多くのことを教えてくれる。説教などではなく、その人の人生そのものが率先垂範のメッセージになっている。
★ ?中国でのメンタル・ウォッチ2011年8月9日(火)
一週間ほど中国を旅してきた。徐に頭を擡げて世界を席捲し始めた巨大な龍の息吹に飛ばされてひたすら旋回しながら現代から古代に到る長大な時間と砂塵の舞う茫洋とした空間を移動してきたかのような感がある。上海・敦煌・西安のどこにいても、凄まじい活力と勢いに気圧されて、〈今、ここ〉に生きる自分の存在が余りにも卑小に感じられて見当識を喪失してしまうことがよくあった。
先ず、上海から飛行機で嘉峪関(かよくかん)に行った。嘉峪関は万里の長城の西端に位置しており、視界を遮るものが何もない黄土色の嶺々に長城が蜿々と蛇行している。異民族の侵攻を防ぐために築かれ、数々の戦闘が繰り広げられた場所。今は果てしなく広がるだだっ広い荒地で、ぎらつく太陽の直射に曝されて肌を焦がすばかりである。一切の感傷も感慨も干上がってしまったかのように湧き起こらない。余りにも荒漠とした光景が却って遠い昔にこの地で生きていた人たちに対する畏怖を彷彿させる。けれども、茹だる暑さに抗し切れないまま、まるで地平線の彼方から不意に現われた異民族に追い散らされるように、そこから鉄道に乗り、およそ5時間位で敦煌に着いた。
沙州と呼ばれた敦煌は、流線形に起伏する砂漠の所々に三角形の砂山が蒼穹に映え、刻々と微妙に変化する風紋と幾何学的な立体が壮大なスケールの芸術を創り出していた。嘗て数頭のラクダを連ねてシルクロードを行き来した隊商たちに想いを馳せながら、鳴沙山をラクダの背に跨って登った。ラクダの乗り心地は瘤が按配な背凭れのようになって安定感があり快適だったが、乗り降りはラクダが前足を折り畳んで座るので、大きく前のめりになって揺れ、少しおっかない。日が暮れて、「月の砂漠」のメロディーがふと何処からともなく聞こえたような気がしたが、天気が良いにも拘らず、月が出ていなかった。漆黒の砂漠。歩けば、足が砂の中にめり込んで進み辛いが、砂そのものは実に肌理が細かい粉のようであり、手に付くことがなく非常にさらさらしていて、感触が心地良い。?
鳴沙山の東端の断崖に開削された大規模な石窟、莫高窟(ばっこうくつ)、がある。千五百年以上も前に僧たちがこつこつと堀り続けて窟を作り、その天井と壁に菩薩や阿弥陀の画や彫刻を施している。その「砂漠の大画廊」は、すべてを横に並べると30キロの長さになるとのことであり、来る日も来る日も狭い場所で作業を続けて生涯を終えた人たちの生き様に圧倒される。何を食べ、排泄はどうしていたのか。そんな卑近なことにさえ不可思議な力を感じてしまう。そして後ろ髪を引かれながら、敦煌から空路で西安に向かった。
嘗て長安と呼ばれた西安は、前漢や唐など13の王朝の都が置かれたところであり、シルクロードの起点/終点でもあった。西安では、世界遺産になっている秦始皇兵馬俑博物館を訪ねた。兵馬俑は、中国で初めての統一王朝である秦を建国した始皇帝の陵墓を守る陪葬物として作られた等身大の兵士や馬の陶製の像であり、数千以上もある。始皇帝は自分の死後の為に地下宮殿を建設し、歩兵隊・戦車隊・歩兵と戦車の混成部隊・騎馬隊など秦軍の構成を忠実に再現させ、不滅の支配者としての存在感を現代においても誇っている。整然と並ぶ兵士達の表情もひとり一人微妙に異なり、今にも動き出しそうな像の気配に押し潰されそうな威圧感に衝撃を覚えた。想像を絶する莫大な労力を投入し得る始皇帝の権勢がいかに絶大であったのか。一人の人間が持ち得る力の可能性について、身近な日常生活の中だけでは、なかなか計り知れないことを実感した。?
西安が古の東西文化の合流点であったとすれば、上海はグローバル化が加速する現代における中国の最大拠点である。とにかく街中が活気と熱気で漲っている。人々は我勝ちであり、おっとりと構えていれば、突き飛ばされる。上海ではそれほどでもなかったが、嘉峪関でも敦煌でも西安でも信号があっても誰も守らない。大きな道路や交差点を横断するのは、まさしく命がけと言っても過言ではないくらいで、車も人もルールなど無いかの如くに自分勝手に突き進む。車が歩道に乗り入れて歩行者を蹴散らして駐車させるのは当たり前であるし、人が横断歩道以外のあちこちの所で走行している車の間を縫って行き、時によっては車の流れを妨げるのも茶飯である。混んだ店で買物をする時、おとなしく順番を待って支払うなど愚の骨頂で人を手際よく押しのけた者勝ちである。ゴミを路上に捨てるのも平気である。飲食店やサービスを売りにする筈の営業でも、極めて行き届いたサービスに親しんでいる日本人には不十分であり、ぶっきらぼうで粗雑な印象を受ける。それでも、こうしたことに慣れてしまえば、我勝ちぶりが目に余るとはいえ、直情径行な在り方から発散される活力に共鳴して自分の中に〈もっとしっかり生きるようにした方が勝ちだ〉といったエネルギーが沸々と塒を巻いて次第に熱を帯びてくるのを感じる。龍の如くでなくても、ある確かな想いが頭を擡げてくる、密度の濃い感覚こそ、今回の旅でのなによりの土産だった。
★『あるイギリス人男性』2011年7月13日(水)
来日して10年近くになるというそのイギリス人の男性(37歳)は殆ど日本語を解さない。勿論、平仮名も読めない。それでも、アパートの部屋を借りてずっと一人暮しをしながら、日本に居住する外国籍の仲間達とEジャーナルを創刊して世界中で起きているテロリズムや人権侵害などについて主要メディアが様々な圧力や複雑な利害に拘束されて報じない情報を発信する強い使命感に駆られている。その他にも、読者数を増やすために、文化・社会・スポーツ・観光・天気などに関する幅広い記事を掲載している。創刊して5ヶ月になり、13万人もの人が閲覧しているが、なかなか採算が取れない状態が続き、生活は火の車である。広告・投資・寄付などを募っているが、現時点では、全く受注がない。年間1万円の購読料の振込みを案内しているが、無料で読めてしまうので、わざわざ支払う人がいない。掲載記事は、第一線で活動している様々なNPOやシンクタンクのスタッフおよび有識者たちが執筆しており、かなり内容的には充実しているので、こうした広報活動に共感し支援する人たちが居ても良さそうなのだが、実情は厳しい。今のところはなんとか銀行からのローンで凌いでいるが、読者数の急増に見合わない財政難で先行きが危ぶまれている。
彼は、10年前に休暇で日本に来て、一人の日本人女性と知り合った。ホリデイ・ロマンスを楽しんで帰国したが、ある日女性からの電話で妊娠を告げられた。そのまま放置することもできたが、彼は責任を感じて再来日して結婚した。その後二人の娘を得たが、3年後には妻からの申し出で離婚した。妻が娘二人を引き取り、実家で両親と暮しているが、娘の一人が先天性の病気があるので、彼は離婚後も月に10万円の仕送りを続けている。最近になり、妻が彼との再婚を希望しているが、彼は応じるつもりがない。しかも、2年前に彼自身が喀血して右肺が機能不全であり、医師に療養を勧められているが、経済的にも仕事上でも余裕がない。而も、彼はテロリズムや人権侵害を糾弾する記事を多く書いたために、あるイスラム派から懸賞金付きで命を狙われているとかで頻繁に引越し、決して居住場所を明かさない。
彼自身、かなり追いつめられた状況であるにもかかわらず、怯むことなく人権を脅かされる人たちを救うことに心血を注いでいる。また、浮世絵や春画にも関心があり、葛飾北斎の『冨嶽百景』とセザンヌの『サント・ヴィクトワール山』の描写を比較して論じたり、市橋達也がイギリス人女性リンゼイ・アン・ホーカーを殺害した事件の裁判を取り上げて被告の改悛の情が判決に影響を及ぼし得る日本の司法について述べたりするなど、一角の筆陣を張っている。彼が書く記事は、過度に人道主義的な見地に陥った甘さがなく、俯瞰的に事態を捉え、非常に論旨が明快で筋が通っている。鋭い分析力を持ち、現実認識は正確であるのに、何故自分の健康と生活苦に対してより適切な手立てを講じようとしないのだろうか。
彼の人柄を示すひとつのエピソードがある。早朝に少し喀血したために受診した帰りの電車の中でてんかんの発作を起こした子どもがいたが、誰も親身に関わろうとしなかった。彼は自分が体調不良であるにも拘らず放置することができないで、子どもの安全を確保して駅員に知らせ、即座に子どもを助けようとした。時には、自分の治療費も食事代にも事欠いて連日チーズトーストだけで済ませているにも拘らず、自虐的にさえ映るほどの熱意で国際結婚が破綻して日本人の妻に子どもを連れ去られた父親の面接権交渉に自前で出掛けて行ったりもする。
「誰かが助けなければならない。彼が家族に暴力を振るったわけではなく、このまま生涯子どもに会えなくなってしまうのは余りにも不当だ。それに、子どもには全く何も非がないし、子どもは両親からの愛情を必要としている。夫婦関係が破綻しても、妻は子どもから父親を奪うことは良くない。日本の法律は親権を持つ親がもう片方の親の子どもとの面接権を拒むことに寛容である。カナダ大使館も日本政府も彼を助けるために何もしない。」
強い道義心。決然たる選択。断固たる行動力。透徹した知性。豊かな、激しさを秘めた感情。
一体、何が彼をこうした行動に突き動かしているのだろうか?
安易な理解を阻む、非常に奥深い屈折したものが彼にはあるように感じてしまう。
「僕の力は小さな点のようなものにすぎない。けれども、世界で実際に起きている惨状を書くことによって、僕個人の一つの点が私たちの点になり、ネットワークが拡がって行く。そのようにして、いずれ新たな現実が生み出されていく。そうした希望の芽が育っていくにはかなりの時間がかかるけれども、時間の連続が歴史になっていくのだ。」
彼は、いわゆる理想主義者ではない。彼は常に世界で起きている現実の出来事を直視している。多くの人たちが自分の身の回りの安穏と利益を守るために自ずと排除して成り立っている現実を蜃気楼に見立てて、その実態の危うさを戒めている。体制側にとって不都合な事実が隠蔽されて闇に葬り去られてしまうのでなく、また、国家とか権力とか宗教間の対立とか多数派による支配でなく、誰もが基本的人権を保障されて宗教とか発言の自由を持ち、お互いの違いを尊重し合って個としての力を存分に発揮する世界の実現に向けて尽力することに情熱を持っている。
当面は、Eジャーナルが収益を生み出すように機能していくことを信じて、まさに臥薪嘗胆の日々である。それでもある水準を保って筆を揮い続ける精神力は並大抵ではない。非常に印象的な、かつ不可解な人物である。
★『俄か結婚ブーム!?』2011年6月4日(土)
ある新聞の記事に拠ると、東日本大震災後、婚活が活発化して、結婚仲介業が活況を呈しているとのことである。問い合わせや資料請求の件数が増え、入会者だけでなく寿退会する人たちの数もこれまでにないほど多くなっているらしい。これと似たような現象として、アメリカでの9.11の大惨事以後、嘗てないベビーブームが到来したとある。
また、震災後、人々の幸福観にも変化が見られるとの報告もある。これまでは、良い学歴とか高い社会的立場と経済的成功を得ることや生き甲斐を覚える活動に従事するなど自己実現に関わる事柄を幸福の指標にする傾向が大きかったが、個々人の関心が自分と他者との結びつきとか関係性の質とか社会的ネットワークなどにより一層向けられるようになった。そして、お互いに共感し合うこと、さまざまな人たちとの間で共感性を共有することが幸福の拠り所として強く意識されるようになってきたと言う。
一見平穏に暮らしていた日常が瞬時に壊滅して一切合切を失ってしまうことが実際に身近に起こり得る。まさかの出来事がいつ何時自分に降りかかってくることがあっても、それはそれで至極当然になっている。今この瞬間であっても、いきなり現状に亀裂が走り、あっという間に自分自身も自分を取り巻く環境も一変してしまうことがあるということを目の当たりにしてしまった。
そうした時、いったい何を信じて、どう生きていけばいいのか。何が自分を根底から支えてくれる力になるのか。辛うじて冷静な見通しと判断力を持つことができても、自分ひとりだけでは、生きる火種を得られない。共に寄り添い、互いの息遣いを聴くことで心に響いてくる振動や情感を通してこそ、前を向いて進んで行こうという希望が芽生えてくる。平時の時は在るのが当たり前すぎて疎ましくさえ感じていた夫婦や親子の繋がりがどれほど掛替えのないものであったのかという想いがじんわりと心の奥深くに沁み込んでくる。だからこそ、人生の伴侶を求める。あるいは、これまで曖昧にしていた互いの関係を入籍することなどでより確かにする。
俄か結婚ブームには、虚飾を剥いだ人たちの素直な心の欲求とそのダイナミクスが息づいている。
★『サバイバル・ギルト』2011年5月6日(金)
東日本大震災から2ヶ月近くが経った。東北新幹線が復旧し、物流が息を吹き返し、コンビニや薬局などが仮説店舗での営業を再開するようになるなど、廃墟と化していた被災地の一部で新たな活力が芽吹き始めた。同時に、未だ明日知れぬ不安を抱えたまま避難所生活を余儀なくされている人たちや一向に解決の目処が立たない福島原発事故で生活を根こそぎされた人たちは、どのように希望を灯せばいいのか分からないまま、厳しい現実を生きている。のみならず、たとえ仮説住宅に入居し仕事を得ることができて、とりあえず日常生活を始動させた人たちであっても、今回の災害に因る深刻なトラウマ(心的外傷)に苦しめられている人たちもいる。
サバイバル・ギルト(Survival Guilt)とかサバイバーズ・ギルト(Survivor’s Guilt)が九死に一生を得た人たちの心を苛んでいる。
「私なんかよりもずっと何でも出来る人がたくさん亡くなったのに、自分だけが生きていていいのだろうか?」
「どうして若い者でなく、こんな老いぼれの僕が死ななかったのだろうか?」
?「もしあの時俺があんなことを言わなかったら、あいつは死なずに済んだのに…」
震災では、一瞬の偶然が生死を分ける。それは、全く無作為的な結果であるにも拘らず、生き残った人が死んでいった人に対して、まるで自分が悪いことをしたせいであるかのように感じて罪悪感を覚えてしまう。そして、自分は果してそれらの人たちに比べて生きる価値があるのかと自問を続けて精神的に追い込まれていく。だからといって、〈私も家族も生きていて良かった〉という想いが全く無いわけではない。が、そうした想いが少しでも意識を掠めたのを強く戒め自責感に囚われる。おいしく食事したり、好きなことをして楽しんだりするのを自粛し、自分が亡くなった人たちを差し置いて幸せになってはいけないと思い込んで鬱々とした毎日を過ごしている。
大切な人を失ったことは最早取り返しがつかない。誰のせいでもない。災害の仕業である。その悲しみや悔しさがどんなに深くても、そのことと自分が今生きている事実を切り分けて、生存している自分自身を引き受け肯定することが非常に重要である。一瞬の偶然で生き残った強運を感謝し、現時点で自分が持っている力を存分に発揮していくことによって、ある瞬間〈生きていて良かった〉と実感することは、決して咎められることではない。むしろ、与えられた運と生命を蔑ろにして全うしようとしない在り方こそ、生命ある者として罪深いのではないだろうか。
★『天災の爪痕』2011年4月2日(土)
3月11日午後2時46分頃、三陸沖を震源にした巨大地震が発生した。マグニチュード9.0の東日本大震災は、東北・関東の太平洋側地域に壊滅的な爪痕を残し、死者と行方不明者が既に3万人に達している。大津波が見る見るうちに押し寄せて大勢の人やありとあらゆる建物や車や畑など、たった今までそこに現存していた一切合財を凄い勢いで丸ごと呑み込んでいく様子は、余りにも恐ろしくて逆に現実感を麻痺させてしまう。死と隣り合わせて漂流しながらなんとか生き長らえた人達が体験した諸々は、想像を遥かに超えている。ついさっきまで握り合っていた手が離れてしまう瞬間、その相手があっという間に視界から消えている現実…身に迫る自らの死の予感…絶望…恐怖。ほんの一瞬で自分自身も周囲も一変してしまった現状。居るのが当たり前だった人の姿が見えず、在るのが当たり前だったものがない。代わりに身元確認もままならない遺体、そして建物に被さる漁船、あちこちに散乱する瓦礫の山々…。茫然自失している猶予もなく強いられる苛酷な避難生活…。止まる所を知らない天災の爪痕に追討ちをかける福島での原発事故。放射能に汚染される恐怖。海外にまで広がる風評被害の連鎖。個々人にも地方自治体にも日本経済にも致命的な傷を負わせた今回の災厄から一体どのようにして明日を紡いでいけばいいのだろうか?
あらゆるものが破壊され、あらゆるものを失い、それでも誰もが持っている、今後の希望に繋がる確かなものの一つは、《こころ》であるような気がする。ひとり一人のこころは、拠り所を失って深く傷ついてはいても、決して感じる力を完全に失ってしまうことも麻痺しきってしまうこともない。必ず感受性を秘めている。人との繋がりを感じ、知らない者同士であっても支え合うことができれば、たとえ少しでもこころが潤い満たされる感触を得て、次第に生きる力を蓄積していけるのではないだろうか。そうした想いに立ってはいても、被災地から遠く離れて平時の生活を続ける私にできることは、今のところ節電と多少の寄付くらいであり、その余りの些少さに身を抓まされる。他に出来ることとして、必ずしも直接被災された方でなくても(被災された方はもちろん)、今回の震災に関連する様々なことで心身が不調になられた方々には、無償でお話を伺わせて頂きます。どうぞご連絡下さい。
電話044-959-5205
メールsophia@f06.itscom.net ?info@sophia-wh.com?
ホームページhttp://www.sophia-wh.com
★『存在して、ごめんなさい』2011年3月2日(水)
「私のような者が存在していること自体が悪なのです。何の役にも立っていないのに、不満ばかりがいっぱいあって、私に関わってくれる人すべてに迷惑かけて、気を遣わせて、煙たがられているだけだから、私がいない方がどれだけすっきりするか…私は誰からも必要とされていなくて、生きているのが苦しい…」
多江さん(28歳)は、転職を繰り返していて、現在も求職中である。仕事を覚えるのが速く手際も良いが、それを続けることにも人間関係にも嫌気が差して仕事を辞めてしまう。その背景にあるこころの動きを、彼女が語った言葉を繋ぎ合わせて捉えてみよう。?
「仕事に限らないけれども、何かをやり始めると、こんなことをして何の役に立つのだろうか。ただ時間を無駄にするだけじゃないのか。そのうえ、仕事上の話であっても、私のことを何も分かってない奴から、上司でもないのに、どうでもいいような細かいことでとやかく言われるのを聞いてやる意味があるのか。何か釈然としない想いが募る一方、自分はこんなことしか出来なくて、こんなふうにしか人から相手にされないような人間なのかといったようなどん底の気持ちになってくる。自分の存在って一体何なのだろうと分からなくなってきて、どんどん自分がつまらない、呼吸するだけで空気を汚染してしまうような存在に思えてくるのに、いっぱい不満を持っていることが更に途轍も無くくだらない碌でなしの証拠のように感じてきてしまう。そんな私が生きていること、私という存在があること自体が申し訳ない…誰に対しても、ごめんなさいってことになってくる。」
多江さんの苦悩は、非常に深い。 ?
そんなふうに苦悩する多江さんがいることを認めて関わり続けることができる人との交流を通してこそ、多江さんは自分の居場所を確保した気持ちになっていけるのではないか。そして、そうした人たちが意外と身近にいたことに気づくのかもしれない。それらの体験の記憶がこころの中に堆積していくことによって、多江さんは自分自身の存在と自発性とか自己主張を肯定的に感じ取れていくに違いない。
★『先ず相手ありき』2011年2月2日(水)
相手の立場に立って考えなさい」と小さい時から親に躾られてきた人たちの中には、自分自身の欲求とか気持ちとか言い分などが自分でよく分からなくなってしまっている場合がよくある。余りにも相手の立場を優先させることを奨励され、そうした振る舞いをするたびに褒められてきたのが嬉しくて、いつのまにか相手/他者本位の生き方が当たり前のこととして身についてしまった。自分がこういうことを言ったり遣ったりすれば、相手は厭じゃないかな、と思えば、それが自分にとっては大切な意味があることであっても、ほとんど自動的に自分で自分を抑制してしまう。その結果、相手との関係が良好になり、自分も楽しい思いができれば、全く何も取り沙汰する必要などないのだが…。
泰子さん(21歳)は、これまでずっと友人たちの間で〈優しい〉とか〈いい人〉と言われてきて、友達が多いのが自慢だった。けれども、最近になって友達と話したり一緒に出掛けたりするのが負担になってきた。自分でもその理由がよく分からなかったが、なんとなく自分がどの人からも「私の身にもなってみてよ」と言われているように感じて二進も三進もいかなくなってしまっていることに気づいた。ごく些細な、「何を食べようか」といったような類のことさえ、自分の好みを先に言ったらいけないような罪悪感に捉えられてしまうので、ついつい「私は何でもいいよ。あなたは何がいい?」と尋ねてしまう。それで、本当は鍋が良かったのに、焼肉を食べる羽目になる。一事が万事この調子なので、人と関わる場面を避けるようになったが、一方では淋しくもある。
「私には、自分がない。先ず相手ありきで、自分を殺してばかりいて、なんだか自分が可哀想になってきた。でも、先ず自分の都合を言うのって、自己中で我儘ですよね。それに、誰からも嫌われたくない気持ちもあるし…」
?「だけど、これからもずっと先ず相手ありきでやっていくことは、もうできない。先ず自分ありきでもいいんですよね。」
泰子さんは、それでいいんですよね、と何度も確認しないわけにはいかない様子である。
?「先ず自分ありきにした時、自分が相手に嫌だなと思われるのが辛い。その辛さをどうしたらいいのか…皆が先ず相手ありきになれるといいのに…やっぱり、それは無理ですよね。」
★『卯年が明けた』2011年1月6日(木)
ぴょんぴょんと軽やかに跳ねる兎のイメージに導かれて、新しい年が明けた。このまま一気に一年を飛び跳ねて過ごしたいが、時間がその進行速度を速めて一挙に短縮されない限り、それだけの跳躍力と心意気を保って順調に前進し続けることはどだい無理だと見定めて、早くも〈兎の下り坂〉?
とはいえ、〈卯〉という字は〈両扉を開いた門〉の形をしているとのことであり、また、〈卯〉を〈ぼう〉と音読みすることから〈冒〉に通じ、これまで未開拓であった潜在力に門扉を開いて〈上に向かって冒す〉という意味に因んでみたい。心の奥底で燻っていた想いを熾して外に向かって解き放ち、これまでとは違うことに新たに挑戦してみようか。一足飛びにでなくても徐々に成果を求めて活動し続ける。そうした〈上り坂〉への一歩を敢えて踏み出す、巡り合わせの年でもある。
?それに、〈卯〉の字は〈茆〉(かや)を模していて、〈繁茂する〉とか〈繁栄する〉という意味があるとのこと。それは、一方では、繁茂しすぎてこんがらがり、対立や競争などに搦め捕られて〈どうにもならないようになる〉とか〈動きが取れなくなる〉という事態にもなりかねない。しかし、生気が旺盛で活力に満ち、自分の世界を広げて成長発展する可能性を漲らせている。
卯年は、ダイナミックな躍動感を秘めている。人生の新たな局面が展開するのを期して、懼れず、怯まず、心密かに願っていたことの実現に向けて果敢に冒険に挑みたいものである。
★『それさえあれば…』2010年12月3日(金)
泰子さん(40歳)は、かつて摂食障害で食べ吐きを繰返し、リストカットを重ね、行きずりの男たちとのセックスに溺れていた。身を屈めてよろけるように歩き、面談中に椅子から床に滑り下りてそのまま土下座するかのようにして呟いた。
「本当に申し訳ございません…私のようなものがいて…それでも、どうぞ、どうぞお助け下さい。」
それから、状態が一進一退しながら6、7年が経過した。35歳の時に日曜日ごとに通っていた教会で知り合った男性とお互いの、世間一般的には不都合な事情を何もかも承知した上で結婚し、現在は、4歳の男の子と生後10ヶ月の女の子がいる。夫の両親と同じ敷地内の家に住み、かねてから望んでいた持ち家での専業主婦の座を手に入れた。結婚当初は、夫が母親に優しいのが不満で、事あるたびにまるで儀式のように「やっちんが一番大事だよ」と夫に言わせるものの満たされきらない気持ちがあり、好きなブランド店に出かけて数万円の買い物をしたり、近所のたこ焼き店の中年夫婦と馴染みになってほぼ毎日そこでお喋りしながら缶ビールとたこ焼きを食べるのを習慣のようにしていたり、ネット・ショッピングに嵌りこんでいた。長男を出産後、自分が母親になったという実感が薄く、育児が困難であったので、医師の診断書を提出して保育園に優先的に入れることができた。そのうち、義母が認知症になり、最近、要介護2を認定された。義母の世話は、普段は80歳を過ぎた義父と週に何回か訪れるヘルパーと週1回様子を見に来る義姉で賄われているが、義父が外出する時などは彼女が隣の家に行って義母と一緒に過ごさなければならない。夫の兄は、知的障害者で施設に入所しているが、週末はいつも帰宅する。夫は、一年ほど前からうつで、ここ数ヶ月間休職していて復職の目処はまだたっていない。長男は軽度の発達障害で定期的に療育相談に母子で通っている。長女は彼女の手元で順調に育っている。
短期間の間に、実に色々のことが次から次に起こった。中でも、長男が発達障害という宣告に泰子さんは打ちのめされた。けれども、そのことのために彼を拒絶するのでなく、障害があるために彼は健常児よりも母親を必要としているという認識が稲妻のごとく彼女の琴線を貫いた。
「彼には母親が何よりも必要で、私が居てあげなければ、彼はこれから先、生きてさえいけない」。
泰子さんは、寝ても覚めても絶えず長男のことで頭がいっぱいになり、彼の一挙手一投足に注目して少しでも不審に思うことがあれば、それを障害の兆候に結びつけて落ち込む一方、「障害があっても、彼なりに社会人としてやっていけるように育ててあげることが私たち親の使命だよねと明ちゃんと話している」と決然たる口調で言い放った。その様子は、これまでの彼女からは想像もつかないほど内実性に満ちて凛乎としていた。歩き方も上体が伸びてしっかりしてきた。顔つきが変わり、取り合わせがちぐはぐだった着こなしが洗練され、過度に謙った言動がなくなってきた。
夫のうつや休職については、自分も長年精神的不調で苦しんできていることもあって共感的である。夫が家でごろごろしていても厭わないで、このまま休職が長引くことがあれば、自分がパートに出ることも考えている。買物癖は収まり、家計簿をつけ始めた。
「私を外から見ている人は、大変だね、と言うけれど、私にしてみたら、今が一番幸せ。明ちゃんが私を大切に思ってくれているのが分かるし、子どもたちは私がいないと駄目。お義父さんも偶におかずを持っていくと喜んでくれるし、お義母さんと留守番してあげると、ご苦労さん、と言ってくれるようになった。何よりも明ちゃんとの、お互いの関係があるから…、子どもの頃、お母さんは私が話すと、うるさい、と言って私の唇を捻って黙らせたけど、明ちゃんはふむふむとよく聞いてくれる。私の今の生活って、普通に見れば、障害とかうつとかマイナスの要素が満載だけど、明ちゃんと運命共同体の気持ちさえあれば、私は、けっこう幸せにやっていける。」
★『濃いか?薄いか?』2010年11月2日(火)
コーヒーのことではない。存在感の話である。自己存在感。自分で自分を感じる感覚が自分自身の感性にぴったり合致する時に覚える、鮮やかでくっきりとした濃い感じ。心地良い重量感。
「私は、ここにいる。確かに、私だ。」
初めてのカウンセリングの日、K子さん(23歳)の目からいきなり涙が溢れた。言葉よりも先に涙がK子さんの現状を語り始めた。
「誰と一緒にいても、それが家で親といる時でも仲のいい何人かの友達といる時でも、どこにいても、自分が本当にその場にいるような気がしない。いるのに、いない。どうしてなのかなあって、いつも思ってて…」
「ふうーむ。今、そうしたことが辛いと話していらっしゃるあなたがここにいらっしゃるのよね?」
K子さんは、伏せていた目を上げて私と視線を交わし、頷いた。
「人といる時、自分が心の中で想っていることを余り言ったことがない。言っても、聞き流されたり、言い返されるのが厭なのもあるけど、言おうと思っているうちに話が他のことになっていたりして、結局、いつも曖昧に笑っているだけだったり、相手に合わせるようになってしまっている。ずっと自分でいて自分でないような状態が続いていて、濃い感じの自分を感じたい。最近は、濃い感じが欲しくて炭焼きコーヒーキャンディとチョコレートを手放せない。」
K子さんは、曖昧な笑いで鎧った、その鎧の重さで薄まっていく自分自身の存在を鮮明に感じることを切望している。ある時、ぽろりと口を突いて出た自分の冗談に対して、そこにいた人たちが笑ってくれた時、すごく濃い感じを覚えた。その快い余韻が続いている間の、えも言われぬ幸福感。〈私は、ここにいる。いていいんだ〉という確かな拠り所を得た感覚。
「自分に濃い感じが欲しければ、自分を出すのを怖がっていたらいけないんですよね。鎧を脱ぐのは勇気がいるけれど、やっぱり、自分の肌に直接触れてくる外気や人の息遣いとか言葉の方がリアルで色々あっていいのかなあ。」
★『虐待した母親を棄てられるか』2010年8月5日(木)
里子さん(57歳)の凪いでいた日常が数日前の早朝にかかってきた1本の電話で荒れ始めた。珍しく母親からだった。ナンバー・ディスプレイに表示された番号と時間を見て、里子さんの心臓がギクンと不穏な音を響かせたのと同時に、自動制御装置が作動して受話器を取り上げようと伸ばした右腕が宙で止まった。まるで突風に巻き上げられた塵芥のように、細切れになった過去の断片がいきなり意識の四方八方から舞い上がり、全身を攫われそうになる。長い時間が経ったように感じたが、実際は1秒にも満たない、けれども、重層する時間の淵に嵌り込み、深い時間が経過していた。里子さんは、一呼吸置いてから受話器を取った。
「はい。」
「ママです。」ねっとりとした猫なで声。
「明け方、パパがトイレで転んで救急車でA病院に搬送されたんよ。すぐ主治医の携帯に電話したら、待ってると言われたから、とりあえずは良かった。ママも何かふらついて具合が悪いから、今タクシーを呼んでいて病院に行く。入院になるかもしれない。昭夫が今病院に向かっていますと言うてきたわ。」
「ふうん。」何も訊く気にならない。絡みつくような沈黙を払いのけたかった。
「できるだけ、夕方、病院に行くようにするわ。」
ガシャリと電話が切れた。里子さんは、何とも言えない後味の悪さと陰鬱な気分に打ちのめされた。すぐに病院に駆けつけようという気持にはならなかった。かといって、行かないで済ませようという決断もできなかった。
里子さんの母親は、彼女が8歳の時に彼女を婚家に残して離婚し、17歳の時に彼女と同年と5歳下の二人の息子がいる大蔵官僚と再婚した。里子さんの実父が事業に失敗したこともあり、10歳の時、彼女は母親の実家に引き取られた。母親の再婚後数年して再婚相手と養子縁組をして改姓したが、引き続き祖父母と一緒に暮らした。祖父は著名な財界人で裕福だった。里子さんが祖父母宅で母親と暮らしている時、母親は里子さんの母親であるよりも娘の立場を謳歌し、育児放棄の状態で外車を乗り回して写真の勉強だか仕事をしていた。再婚後、母親は相手の息子二人と養子縁組をして「ママ」と呼ばせたが、二人を全寮制の学校に入れた。里子さんが母親を家に訪ねようとしても、いつも用事があるからと断られ、たまに行くことがあっても泊まったことも食事をご馳走になったこともない。母親の華麗な交友と自慢話を里子さんが持参した菓子類や果物を食べながら聞かされた。里子さんが結婚して子供が生まれる時も実家で過ごすことを拒否され、「あんたは嫁いだのだから、山本のお義母さんに面倒をみて貰いなさい」と突き放された。母親に子供をあやして貰ったこともなく、初節句とか入園などの節目での心遣いも全くされなかった。里子さんには、母親との懐かしい記憶が全くなく、何度も置き去りにされ、絶えず拒否されるかとことん無視されていたことばかりが印象に残っている。ずっと以前、里子さんが母親に不満をぶつけた時、「パパとも言うてるんよ。これからの残りの人生を楽しく生きようねって。もう私が不快になる人とは付き合わない。あんたとも気持の良い関係になれるんやったら会ってもいいけど…。昭夫と康夫は月に2回、いつも二人で打ち合わせてパパたちが心配やと言うて様子を見にくる。ママに手間を取らせんように、お寿司とかお弁当を買ってくるのよ」と言われた。里子さんは、これまでも母親との関係は何らかの形で母親に利するようにするものだったと感じている。それでも、どうして母親を求め続けるのか自分でもよく分からない。今も幼女のように母親に追い縋りたい衝動が湧き起こる。
里子さんは、今、母親が身近に居て世話する人間を必要としているのは分かる。ケアマネージャーが付いて、ヘルパーやナースを派遣する手筈を整えてくれるが、もっと痒いところに手が届くケアを求めている真情を、「今、遺言をどう書こうか、思案中や」という言い方で伝えられた時、里子さんは索漠たる気持になって〈母親〉を諦めた。自分が望むような母親との関係は決して持ち得ないことが心底納得されて、長い夢から覚めた感じがした。愛情を持って自分の大切なものを譲りたいという気持でなく、〈遺言〉で娘を操作しようとしている冷めた情緒を感じた。
早朝の電話を受けた日の夕方、里子さんが病院に母親を見舞うと、母親は2,3日入院することになって病室にいたが、身の回りの品が全く揃っていなかった。「朝、入院するかもしれないと言っていたのに、何も用意して来なかったの?」と訊くと、「帰るつもりでいた」と腑に落ちないことを言う。いつものことだ、と里子さんが聞き流して黙っていると、母親が「昭夫が売店でパジャマだけは買ってきた。Mサイズや」と夕飯をいかにも不味そうに箸でつつきながら言った。里子さんはやるせない想いに駆られたが、訊かないわけにもいかない。
「何が必要なの?」
「スリッパも何もない」
母親はベッドの縁に横座りになってぶら下がった両足をばたつかせた。
「今は売店が閉まっているから、明日の朝届けられたら、届けるようにするわ。」
と言って早々に引き上げ、養父の病室に顔だけ出した。帰りに深夜営業しているマーケットでタオル、下着、歯ブラシ、スリッパなどを買い、翌朝仕事に行く前に届けた。その後連絡していない。
里子さんは、母親が不自由していて可哀想だと思うが、だからといって、何かしてあげようと思いたつと直ちにそれを撃ち払う怒りとか蟠りがグイッと鎌首をもたげて優しい気持を襲撃してしまう。老いた母親を愛おしく思う気持で親身に介護したい。母親との長く辛い不毛の時を経て、最後に和解し合って母子の情愛を通わせたい。こころから願うにも拘らず、そんなふうになり得ない関係性が悲しい。
〈私がもっと人間的に大人になって、過去に囚われないで老母を慈しむことができれば、新たな関係を持てる可能性があるのではないか。人間として不人情なことをしない自分でいられるのではないか。自分の人間性を自分で信じられるだけでもいいのでないか。逆に、このまま連絡を取らないで、母親を見棄てることができるのか。かつて母親が言ったように、母親に向かって、「竹田家のことは、そちらで対処して下さい」と言ってしまえるだろうか。それとも、何某かの遺産を確保するために割り切ろうか。もし、この状況で遺産が無ければ、本当に母親を棄てられるのか。〉
?里子さんは、食欲不振と睡眠障害、絶え間ない動悸と息苦しさで毎日を過ごし辛くなり、カウンセリングを受けることにした。今後、どう母親に接することが、自分にとって一番気が済むことなのか。自分なりに見定める必要があると感じている。
★『情事』2010年7月5日(月)
灯が消えた。その時、彼女(34歳)はそう感じた。周囲が真っ暗になると同時に、両脚が崩れた。一瞬にして全身から血の気が引くような冷え冷えとした感覚に襲われ、胸を鋭い衝撃で刺された。
夫に女がいた。世間ではよくあることだ、と分かっている。「あなたにも責任があるんじゃないの?二人の生活は、楽しかった?」と長年の友人が言った。〈一緒に生活していれば、楽しいことばかりじゃない。それで浮気されたら、私が責任を感じないといけないの?〉と傷口を更に深く抉られて叫びそうになったが、それ以上言葉を続ける気力が失せた。けれども、彼女はじっと痛みに耐えることができない。断続的に強く襲い掛かる痛みに衝かれて手当たり次第に物を投げて壊し、大声を上げて暴れる。そうしていても、彼女は夫が強い力で羽交い絞めにしてくれるのを待っていた。自分を動けないようにしている夫の両腕の中で脱力し、体重を思い切り夫に預けて、彼の懺悔の表情に出会いたい。しかし、夫は警察を呼んだ。彼女の苦痛を理解しようともしないで、安易に解決の手立てを第三者に委ねてしまうかのような仕打ちに、彼女はいっそう傷ついた。
彼女はこころの痛みに翻弄され、自分で自分をどうすることもできない。パートの仕事を辞め、家事も手につかない。気分が落ち込み、奈落に堕ちていくような不快な感覚がある。何をしていても、今、この瞬間、夫は女と連絡し合っているかもしれない、女と会っているかもしれない、という疑念が湧いて振り払うことができない。営業職の夫は仕事中でも自由に女とのことに時間を当てられる、と彼女は不安で堪らないので、夫に1時間おきにメールか電話をするように求め、夫が商談や会議などで出来なければ、自分からずっとし続ける。彼女の言い分は、「彼が私の信頼を損ねることをしたのだから、その信頼を取り戻すために、とことん誠意を見せるべきだし、私が元の元気な状態に早くなれるように、多少の犠牲を払ってでも最大限の努力をするべきである」。
夫は、今のところ、半ば当惑して逃げ腰になりながら、彼女と真っ向から対立するのを避けて彼女の意に沿うように動こうとしている。が、出口の見えない状況で、どれだけ持ち堪えられるか自信がない、と言う。
夫の情事に出くわす女性たちは、けっこう多い。もちろん、妻の情事に悩む男性たちも、最近では多くなっているが、パートナーの情事をきっかけにした心身の不調で相談に訪れる人は、少なくとも私が経験した限りでは、女性の方が多い。彼女たちの傷つき方や症状は、さまざまであるが、本来の人格の健全度に大きく左右され、こうした出来事がなければ、それなりの水準を保って機能している人格が一挙に病理性を露にすることがある。
今回の事例では、夫の情事が発覚したことによって彼女は日常生活を破綻させ、自制心を失った状態を持続させ、自己崩壊の危機に瀕している。自分を傷つけた彼に執着し、自他境界を無くして彼を過剰な要求で雁字搦めにしている。彼が改心して、それを自分に信じ込ませることが唯一の解決法であり、それができなければ、自分はずっとこのままで生きていくしかない、と思い込んでいる。彼女には、自分の手で傷口を押さえ、自他間の距離を苦労してでも何とか測って主体的に動くことが難しい。自分を傷つけた相手に対して憤ることはできるが、その相手から離れることができない。まるで無力な幼児のように、ずっと受身の姿勢で終始して、生殺与奪の権を彼に預けているかのようである。一方で彼女は、自分に向けられていた眼差しを逸らされて見棄てられた痛みや悲しみを感じることを拒み続けている。そうすることで辛うじて自分を保っている。自分で自分の存在価値を疑うことほど辛いことはない。彼女には、何かそうしたことに関する深い傷が既にあり、その塞がり切れていなかった傷口が最も信頼していたい夫の裏切りによって烈しく疼いたのかもしれない。その疼痛が夫に対する敵意と拘泥を強め、彼女から足元を照らす灯を奪っている。
★『静かに兆す変調』2010年6月4日(金)
その職場では、嘱託を除けば彼女が最古参で主任である。上司の課長や係長は何人か交替し、スタッフも皆数年で異動する。彼女はできるだけ長くそこに居させて貰えるように人事に頼んでいるのが今までのところ叶えられている。彼女が一番仕事の要領などが分かっているが、「上の人に言われたら、必ずその通りにやる。自分なりに変えてしまうことは少しも考えてない」。
「こう言ってはなんだけれど、ベテランの私でもそうしているのに、異動してきたばかりのAさんとBさんは平気で自分の考えを言ったり、自分の都合で勝手に何でもやってしまって係長や私の言う通りにやらないのに、それがまかり通っている。私にしたら、そういうのっていかがなものかと思う。彼らは、事前に相談しながら一緒にやろうとしない。分からないことがあれば、私に訊かないで嘱託に訊く。それでいて、途中で上手くいかなくなって私に手伝いを求めてくる。私には自分がやっている仕事があるし、それぞれが自分の仕事をするのを遠くから見守っていてあげたい気持ちもあるのに、そんなことはお構いなしに言ってきて、私がすぐに応じないと、“冷たい”とか“自分のことしか考えていない”とか批判する。嘱託の人たちも二人に取り込まれて、私の存在が浮いている。何人かで飲みに行く時があっても、私には声をかけてこない。私が頑張るほど、周りが離れていく気がする。真面目にやれば、“そこまでしなくていい”と煙たがられる。一生懸命にやっているのに報われない。上の人たちは私の仕事ぶりを見てくれているけど、“もう少し周りに合わせなさい”と言われるのが辛い。私から見てそんなにやってない人が助けを求めるのは許せない。自分できちんとこつこつやった上で助けを求めるのなら協力する。“何でも皆で協力し合いましょう”じゃなくて、事前に皆で何を何時までにどうするのかをきちんと相談し合って決めて、自分の仕事を周りに迷惑をかけないようにしっかりやるのが先決。その場の思いつきで色々のことが流れていくのが嫌。自分の仕事は自分で一生懸命やるように心がけて、そのうえでお互いに体調が悪い時など助け合って仲良く一緒に成長していきたい。私は自分が間違ったことを言っているとは思わないのに、やってもやっても疎んじられて、私が地を出すと皆に退かれる。だけど、係長が“よく頑張るね”と声をかけてやりたいと思って下さっているのが分かる。ありがたいと思って励みになるし、課長と係長が“山田さんはよくやってくれている”とお互いに話されているのが聞こえて嬉しい。でも、AさんがBさんに“山田さんは仕事を一人で抱え込んで忙しがるのが好きだよな”とか“あんなに優等生ぶらなくてもいいのに”と聞こえよがしに言って、Bさんだけでなく他の人たちも同調したように笑うのが嫌。ちゃんと一生懸命に仕事して、どうして悪く言われないといけないのか分からない。」
幸江さんは、真面目に仕事をしているし、誰かに意地悪しているつもりもないのに、周囲から認めて貰えないばかりか疎んじられているように感じて、辛い。皆と和気藹々と仕事をしたいし、話しかけられることを待ち望んでいるのに、AさんやBさんから手助けを求められることには抵抗がある。幸江さんの想いの中には、自分はこれまでずっと他者に甘えないで一人で地道に努力していれば必ず見ていてくれる人がいる筈だと思って、辛くても頑張ってきたが、AさんやBさんは異動してきて日が浅く、大して努力しているようには見えないのに、堂々と意見を言い、安易に助言や手助けを求め、周りから受け入れられているのが腑に落ちない。
幸江さんのこころの奥で蟠っているAさんとBさんに対する羨望が抑圧された依存欲求を刺激して、彼女が辛うじて保っていた人格のバランスを揺るがせる。密やかな敵意が燻ると同時に、柔らかく温かい触感を求める欲求が膨らむ。身近に一人でも理解者がいれば、その人の温かい眼差しに見守られて安心してのびのびと仕事ができる。その焦がれるような願望が現実を意味づけていく。そして、こころに巣食った敵意が知らない間にAさんとBさん、周囲の人たちに投げかけられて、恰も彼らが自分を批判しているように感じられる。幸江さんがたまたま側を通る時に自分のことが話されている会話を耳にする回数が増えていく。こころの声と現実場面で実際に交わされる声との区別が判然としなくなってきた。
幸江さんは、相変わらず一生懸命に仕事をしている。表立っては、これまで通りである。目に見えないところで静かに兆した変調に取り込まれてしまわないように、彼女自身、実際に声を出して会話する機会をもっと持とうと直感している。
★『身体でしか語れない本音』2010年5月7日(金)
三千代さん(35歳)がいくら思い返してみても、どこでどう舵取りがおかしくなり始めたのか分からない。日々、当面する生活状況の中で精一杯頑張って生きてきたつもりなのに、いつのまにか夫と協力して操舵していた筈の舵が自動運転に切り換わってしまっていたかのように、今現在の家庭船は、全く意図しない場所を、行先不明のまま、一見これまで通りの滑らかな速度で、進行している。
三千代さんは、困惑しながらも何とか気持ちを持ち直して夫と一緒に不具合を調べて復旧作業を急ごうとするけれども、事態は一向に良くならない。何よりも夫が協力的でなく、まるで他人事のように批判ばかりする。三千代さんは、次第に食欲がなくなり、吐き気と胃痛に悩まされるようになった。いくつかの病院を受診して胃カメラを撮るなど検査を重ねたが、どこの病院でも「特に、問題はありません。治療の必要はないです」と言われた。そのうち何もやる気がなくなり、嫌々でも出来ていた家事も滞り始めた。やむなく受診した心療内科で身体表現性障害と診断され、抗うつ剤を投与されると同時にカウンセリングを勧められた。
三千代さんは、21歳の時に未婚で長男を出産し、実家で暮しながら働いて子育てをしていた。28歳の時、現在の夫と結婚し、翌々年に次男を出産した。結婚当初、夫と長男は一緒にお風呂に入ったりして仲が良く、三千代さんは気持ちに余裕を持てるようになって専業主婦の生活に充実感を覚えていた。けれども、3年前、長男が小学校6年に進級した頃、「個人面談の希望日時を記入するプリントが提出されていない」と担任から電話がかかってきたのを皮切りに、それ以降も学校で必要な提出物を親に伝えない、宿題をしない、友人にお金や物を借りて返さないので友人の親から電話がかかってくることなどが重なり、三千代さんが再三注意しても、長男は聞き流すだけである。中学入学後も同様の状態であるうえに、益々生活態度がだらしなくなり、長男の部屋は脱ぎ捨てた下着や汚れた部活のユニフォームや靴下、スナック菓子の空き袋やペットボトルなどが散乱し、異臭が立ち籠めている。
そうした長男を夫があからさまに嫌って三千代さんに悪し様に言うのが、三千代さんには辛くて堪らない。針の筵での生活を強いられているように感じて、「もういやっ!あんな子は大嫌い!家族も鬱陶しい。むかつく。家を出たい」とこころの中で叫んでいる。全身が硬くなるくらい渾身の力を籠めて叫んでいるのに、声は出ない。夫に対して、「もっとしっかりお父さんをやってよ!二人とも私たち二人の子どもじゃないの?」と当たり前のように言い放ちたいのに、その想いが言葉にならない。なまじ言ってしまえば、その途端に恐ろしいことが起こりそうな漠然とした恐怖が鳴りを潜めている。なので、言葉にならない想いが代わりに身体化されて表出されてしまった。〈もういやだ。子どもにも旦那にもむかむかする〉という想いが吐き気という身体言語に、辛い気持ちが胃の痛みに、〈こんな現実は受け容れたくない〉という不満が食欲不振に転換されて表現された。
「体調が悪い」と訴えれば、夫も多少は気遣ってくれるので、この表現方法はなかなか手放し難い。そのようにして、症状が遷延化して、三千代さんの通院は続いている。
* 私たちがこころの中で想っていることや感じている情緒は、何らかの方法で表出/表現されなければ、他者には伝わらない。他者に伝える以前に、自分自身がそれらに意識を向けて何らかの形、たとえば、言葉、絵、粘土、音など、で把握しなければ、それらは自覚されないけれども、私たちにさまざまな作用を及ぼし、三千代さんの場合のように、身体を蝕んできたりする。
私たちのこころの内容の表出/表現方法には、大きく分けて3つある。言語化、行動化、身体化である。行動化という場合、よく分かって行動するというよりも「切れた」時のような衝動的行動を指している。こころの内容に対する私たちの意識の関与が大きいほど、冷静な表出/表現形態になり、他者との関係も円滑である。三千代さんのように、こころの中で想っていることを言えずに抑えていれば、意識でコントロールされない過程が潜行して身体症状になって顕れる。言葉にできること、それを言うか言わないかは別にして、自分が想っていることや感じていることを曖昧なままにしないで、それらに言葉もしくは何某かの形を宛がおうと努めることが、不意に切れたり身体化するのを防ぐ有効な手段になる。
★『えっ?!思わず宙に浮いた瞬間』2010年4月2日(金)
真知子さんと百合さんは、中高一貫の女子校のクラスメイトで30年以上の付合いである。それぞれ違う大学に進学して就職したけれども、同じ県内に居たので、時々一緒に食事したり飲みに行ったりしてお互いの公私に亘る話を赤裸々にし合っていた。結婚後も育児と仕事の合間を見つけては会い、それが適度の気晴らしになって日々の生活を過ごし易くしているのをお互いに認めていた。?
その日、真知子さんと百合さんは、百合さんの知合いの女性が経営しているレストランで待ち合わせた。真知子さんがほぼ定刻に店に着くと、百合さんは既に席でオーナーと談笑していた。二人とも笑顔で真知子さんを迎え、40歳台位のシックな装いのオーナーは立ち上がって、「よくいらして下さいました」と明るい笑顔を更に広げて挨拶してきた。一瞬にして警戒心を解くような、爽やかで温か味のある印象を薫り立たせるような、笑みだった。〈さすが、プロ〉と真知子さんは、内心感嘆しながら、楽しい気分になっていた。百合さんが右掌を真知子さんの方に向けてオーナーに紹介した。
「こちら、私の中学時代からの仲良しの安部真知子さん。ご主人は、○○の取締役に最近なられたのよね。」
「まあぁ…」
オーナーが少し目を瞠るようにして短く余韻を残して応答したけれども、真知子さんは全く予期しない百合さんの言葉に、えっ?!とたじろいでしまった。百合さんはそのまま言葉を続けて今度はオーナーを真知子さんに紹介していたが、真知子さんは自分がその場にいる臨場感が薄れて、一瞬ふわりと宙に浮いてしまったような奇妙な感覚を覚えた。自分の実態が掻き消されてシルエットだけになってしまったような、そのシルエットを自分だと引き受けてその場をやり過ごすことに何とも不快な蟠りを感じていた。真知子さん自身、最近、勤務する高校で英語の教科主任になっていて、もちろん、そのことを百合さんは知っている。それなのに、何故百合さんは、あのような紹介の仕方をしたのだろうか?真知子さんは、ふと百合さんの屈折した感情に触れたような気がした。百合さんは、かなり前に勤めていた銀行を退職して専業主婦になっていた。夫はある総合病院の院長で、息子二人も医学生である。それなりの自負を持っていることが言葉の端々から伺えたが、ある時真知子さんと一緒に出掛けた折に、「あなたはいかにもキャリアウーマンぽい服装だけど、私はどんなふうに見えるのかしらね」とややくぐもった声で言ったことがあったのを真知子さんは思い浮かべた。仕事を続けて名刺を持つ真知子さんに対する羨望というか、主婦とか○○氏夫人という社会的肩書きしか持たない自分に対するある種の心許なさが刺激されるのを、ほぼ反射的に回避したのではないか。真知子さんは、それが必ずしも穿った考えのようには思えなかったと言うが、同時に、自分の中に職業人でもあることの優越感のようなものを百合さんに対して感じていたのかもしれないとも言い、「あるいは、よく知られた大企業の取締役の奥様の方がたかが中学教師の友人というよりも、彼女には良かったのかしら?私は別に自分のことをたかが中学教師などと思ったことはないけどね」とも付け加えた。
★『号泣したのは、何故?』2010年3月5日(金)
「その日は本当に楽しかったのに、後でまるで小さい子がワーンワーンと大声で泣くみたいに、手放しで号泣してしまった。夫がびっくりして、どうしたの?と訊くけれど、答えられない。友達が皆一斉に帰ってしまったから悲しいの?とか訊くけれど、やっと静かになってほっとしたから、そんなことじゃない。自分とは全く別のところから嗚咽が勝手に次から次に込み上げて来たみたい。」
一体何が真知子さんに起きたのか?
先ず、真知子さんの話からその日の楽しかった出来事を振り返ってみよう。
「中学の時の友達二人と前からランチ会をしようと約束していて、その日が来るのが楽しみだけれども、なんとなく憂鬱だった。二人とも親子セットで来ることになっていて、一人は2歳の娘を連れて現在妊娠中、もう一人は5歳の息子と3歳の娘のお母さん。前に来た時、男の子は挨拶しないでふてくされていて、扱い辛い。今回挨拶しないと玄関に上げないでおこうか、受け流そうか。おばちゃんちに来たら、おばちゃんちのルールがあるから、挨拶しないとどうするか、憂鬱。どういう心持でいたらいいのか…。楽しく遊べるようにテントを買って組み立てようか、クッキング・マシーンを買って一緒にクッキーを作ろうか、あれこれ考えてわくわくしながら空しいな。
当日11時位に、皆が口々に「こんにちは」と言って来た。友達は子どもたちのことはそっちのけでドシンと座りっぱなしで話を始めた。子どもに箱ごとチョコを持たせて自由に齧らせている。二人とも超いい加減に子育てしている。私が子育てしたら、手作りのお菓子を、大きくなってダイエットに困らないように、適当な量を上げるし、子どもがお母さんを呼んだら、ちゃんと返事をしてあげる。大人同士で会うのはいいけど、それが親子セットで来て、親子の営みを目の前でさまざま見せられると、あーだこーだ思って、心が揺れる。子どもたちはだんだん慣れてきて遠慮が無くなって騒ぐ。私は保育士のように子どもたちと遊んで楽しい。これぐらいの子はこんなに騒ぐのかと思って…私は、子どもの頃、騒ぐと母に怒られて、母の言うことはすべて正しいと思って、おとなしくしていて窮屈だった。
お昼に子どもたちと一緒におにぎりを作った。そこら中に水や塩を撒き散らして、ぐちゃぐちゃのおにぎりに海苔を歪んだまま巻いて、お皿に並べた。昔、保育園の先生と一緒に紙粘土で団子を作ったのを思い出した。昼寝から覚めたらおやつの時間で、本物の団子が出てきて、ミラクルだった。お母さんに何度も一緒に団子を作りたいと言って、毎回断られた。台所を汚すとすごく怒られた。子どもの頃、お母さんは忙しくて、私はいつも淋しくて不安で窮屈で愛想笑いをして大変だった。今でも肉団子を作るのが好きで、時間をかけてこねこねしている。友達は全く手伝わない。大仏のようにびくとも動かないで、ずっとお喋りに夢中。365日子どもに付き合っている彼女たちと1日の数時間だけ相手した私とは世界が違うのか。それでもうちの子になった方が、子どもたちもずっと楽しいんじゃないか。私なら子どもをほったらかしにしないで相手してあげるし…。ふてくされ息子でひねくれっ子でも、居たら可愛いですよね。ペットショップに行って、血統や容姿で気に入った子を選べるといいな。子どもっていいですよね。本当に居たら、いいなあ。泣きたい気分。」
真知子さんの話には、4組の母子関係が登場している。友人二人が親子セットで遊びに来たことによって真知子さんの幼年時代における母親との関係と長い間服薬してきたことで慎重になっている母親になりたい願望が喚び起されている。友人の子どもたちと一緒に遊んだりおにぎりを作ったことは、嘗て子どもの頃の真知子さんが母親と一緒にしたかったことであると同時に、自分の子どもと一緒にしたいことである。子どもの頃、真知子さんは母親に怒られることを怖れて自分を抑えておとなしくしていたが、本当は、無邪気に騒いだり、大声を上げて泣きたかったに違いない。そして、母親に「よしよし」と宥めて貰いたかっただろうし、「よしよし」と我が子をあやしたいと、どれほど切実に願っていることだろうか。印象的な彼女の言葉がある。
「今までは夢を意識のど真ん中に置いて来た。でも、なかなか叶わないと辛いし、もう叶わないかもしれないと思うのも苦しい。だから、最近は、風船みたいに、あの辺にフワーッと、なるべく遠くに漂わせておくのがいい。でも、風船の紐を放さないように握っていれば、今すぐ叶わなくても、いつか叶うかもしれない。」
★『メンタルウォッチ』の視点2010年 2月8日(月)
阪神淡路大震災でも、最近のハイチ大地震でも、全く予期しない出来事?僅か15秒間程の激震?で、たった今まで在ったものが崩壊し、多くの人命が奪われ、すべてが一変してしまう。それまでは全く何も無かったものが、突然、姿を現し、現状を見る影も無く変貌させてしまう凄まじい自然の猛威に圧倒されるしかない人間。しかし、同時に、世界各国から多くの人が救援に駆けつけて一日も早い復興を目指す強大な再建力を持つ人間たちの繋がりの連鎖。?
森羅万象とそれらを現出させる、奥深い所に潜む根源的な実体。宇宙空間の、自然界の、生物界の、そして人間界の、あらゆる有形の事象の背後にある、見ることも、聞くことも、嗅ぐことも、味わうことも、触れることも、想像することさえも、できないけれども、悠久の時を貫いて《今、ここ》に厳然と存在する、それぞれに固有の物質とその本性とエネルギー。
この世に在る有形無形の一切のものは、《原初の大いなる混沌》を起源にして、その厖大で未分化なエネルギーの計り知れないダイナミズムによって生じた亀裂から細分化されて独自の存在を与えられ、進化と統合を繰り返す過程で淘汰された結果、《今、ここ》に現存する個々の姿?構造体?になっている。それらは、有機的に繋がり合い、一時的に相互に秩序立てられて調和を保っているとしても、その一時的というスパンが数秒にも満たない短期なのか何百年か何千年以上というほど長期に及ぶものなのかは定かではないのだが、いずれ最終的には、互いに前後し合いながら再び固有の形を失って、アモルファスな《根源》に還っていくのではないだろうか。
『メンタルウォッチ』と題した、このブログでは、毎回、ミクロコスモスのある一点で生きる一人の人物をズームアップする。連綿とした血の系譜に印される《今、ここ》での、小さいけれども確かな存在。特定の環境で生きるその人の風貌、佇まい、表情、立居振舞、話し方、言動などを通して、場合によっては、その人自身でさえも気づいていないこころの深層での出来事やその人の生き方を司る心性などを、映し出してみたい。
もちろん、身体の内部をレントゲンやMRIなどで可視化するように、こころを画像化することも透視することもできない。ポリグラフのようなものがあっても、血圧や心拍数などの生理的現象がこころの複雑な内容や動きを把握しきれるわけではない。その点、投影法と呼ばれる心理検査、たとえば、ロールシャッハテストでは、紙にインクを落とし2つ折りにして広げて出来たインクのしみが何に見えるかを言うことによって、その人のこころの内容や仕組みや働き方などについての情報を、ある程度は得ることができる。けれども、そうした特殊な方法に依らなくても、《こころ》は、その人の普段の生き方やちょっとした言葉遣いに、たとえば、何気なく逸らされた視線とかふと言い淀んだ瞬間とか言い間違った言葉とかに、顕れている。そうした断片から、その背後にあるこころの真相を、建前の奥にある本音を、演技の裏にある実像を、《ウォッチ》しようと目と心眼を凝らしていきたい。
そして、一人の人物を注視し、その内面を掘り下げることが単に一個人の《こころ》のリアリティに行き着くだけではなく、より広範な人間にとってのリアリティ、人間性の本質、に通じて行くのではないか。その人を深追いすればするほど、個人という地平が幽かになり、より集合的な場所に居合わせることになりそうな予感がする。
見えるものから見えないものへ、表層から深層へ、と想いを巡らせる過程が今後どのように展開するにしても、『メンタルウォッチ』の視点は、見えなくても存在するもの、意識しなくても在るもの、に絶えず定めておきたい。
|